「田舎で起業したいけど、色々と不安が付きまとうので成功してる人の事例を参考にしたい。」
そう考える方も少なくありませんよね。
実際に、新しいことに挑戦する際には、先人の事例を真似するのがもっとも成功の近道です。
起業は決して簡単ではありませんが、成功するパターンと失敗するパターンは大体決まっていますので、無理に我流を進まず成功例を真似してみることをおすすめします。
田舎で起業した成功例5選

田舎で起業をし、様々なビジネスが展開されている昨今ですが、ここでは田舎での起業を成功させている5つの例を紹介します。
田舎での事業を成功させている人々がどのような経緯で田舎での起業を決め、経営を進めているのかを具体的に見ていきましょう。
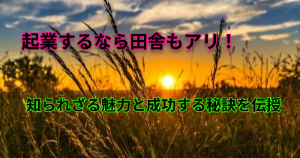
地域おこし本格化のため会社設立したKさん夫妻(北海道河西郡中札内村)
Kさん夫婦は関東で会社員として働き、地方での起業とは関係のない環境でキャリアを積んでいました。
しかし、結婚を機に旦那様は会社員としての働き方に違和感を抱くようになりました。
特に配属や異動といった自分の意志と関係なく決まる働き方に疑問を持ち、家族や自分の生活を大切にできる新たな働き方を模索し始めたのです。
一方で奥様はワインソムリエの資格を持ち、北海道・十勝なら自身の経験や資格を活かせることに気づき、夫婦で田舎への移住と起業を視野に入れ、北海道へ新たな一歩を踏み出すことを決意します。
夫婦で仕事を辞めて移住する決断は簡単ではありません。
しかしお互いのキャリアを活かす方法を柔軟に考えた結果、田舎でも新たな可能性を見出し、自信を持って挑戦を始めたことが成功への第一歩となりました。
移住後、募集枠が1名しかない「地域おこし協力隊」に夫婦で応募したところ、見事に2人とも採用され中札内村の観光復興プロデューサーとして活動を開始しました。
現在はアウトドア・フード・ワインを事業の中心に据え、イベント企画やワイン店の運営などいくつかの事業を行っており、人々を喜ばせ地域に貢献することをリアルに感じながら生きがいを持って暮らしています。
「東京で会社の一部として働く」のではなく、「心のゆとりを持ちながら挑戦を続けられる」という田舎起業の魅力を体現しているK夫婦。
これを実現させられる背景には場所を選ばずに使える資格や経験があったことも重要なポイントです。

「田舎でのんびり起業」をテーマに活動するTさん(山梨県北杜市)
Tさんは「お金よりも人生を大切にする」という目標を掲げ、田舎で新しい事業を始めるのではなく、自分の人生を自分が好きなように生きられるように仕事を選ぶという田舎起業の成功例の一つです。
現在ご自身で事業を立ち上げ、コンサルティングやコーチングをしながら山梨県でゆったりと田舎暮らしをしています。
もともとTさんは東京で外資系IT企業の会社員として働いていました。
収入に不満はありませんでしたが、コロナ禍のリモートワークを自身が所有していた山梨の別荘で行い、その生活に魅了され、会社を辞めて起業をすることを決意しました。
その背景には、不動産投資やブログ運営などの働く場所を選ばない副業収入があったことが、安心して移住を踏み切る要因となっていました。
田舎で起業する際、複数の収入源を持つことはリスク軽減につながります。
さらに、Tさんは田舎暮らしのメリットとして、生活コストを適正化できる点を挙げています。
都会では環境的にお金を使う機会が多いですが、田舎では美しい自然や四季の移り変わりを楽しむ中で、特別な出費をせずとも幸福を感じることができます。
Tさんは、「必要なだけ稼いでのんびり暮らす」という、都会では実現しづらいライフスタイルを確立しました。

日本舞踊をはじめとした文化を世界へ広めるTさん(京都府京都市)
Tさんは8歳から日本舞踊を習い始め、29歳で師範免許を取得しました。
伝統芸能業界の高齢化や伝承の課題に気づいたTさんは、京都で日本舞踊教室を開業しました。
開業当初は日本舞踊の認知度を高め、初心者が始めやすい環境を作るため、ホームページやブログを活用した情報発信に力を入れました。
その結果、現在では約20名の生徒に指導を行っています。
Tさんのビジネスは日本舞踊教室にとどまらず、着物文化を発信する取り組みも行っています。
具体的には、古着の着物をリメイクしたインテリア雑貨やハンドバッグなどの販売を手がけ、日本文化の魅力をさまざまな形で伝えています。
田舎での起業において、一つのビジネスだけに依存することはリスクが高いため、自身の目標や経験、知識を活かして複数の事業を展開することが重要です。
Tさんのビジネスは伝統舞踊に特化するのではなく、日本文化全体を伝承するという広い視点で取り組むことで、教室運営だけでなく販売事業からも収益を得ることができており、その成功例と言えます。
今後はインバウンド観光客向けのワークショップや、教室の拡大にも取り組む予定だそうで、「日本文化」というキーワードを軸に多様な事業展開が期待されます。
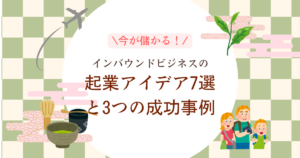
引退競走馬を引き受けて余生を支えるOさん(岡山県津山市)
Oさんは北海道の競走馬育成牧場で勤務した後、兵庫県や岡山県内の乗馬クラブで働いていました。
勤務先では引退競走馬のリトレーニング(再調教)を任されており、現在の厩舎として利用している家屋は、家主から無償で土地と建物を譲渡されたことをきっかけに起業することを決意しました。
空き家となっていた建物を厩舎として再利用し、修理や環境整備は可能な限り自分たちで行うことで初期費用を抑えました。
飼料や砂の高騰により馬場の拡大は簡単ではありませんが、田舎起業ならではの地元住民の支援と助け合いのおかげで、現在は所有馬2頭と預託馬3頭を管理しています。将来的には10頭まで増やす計画を立てています。
リトレーニングによって、競走馬として引退した馬を乗馬レッスンや観光牧場でのふれあい体験用の馬として新たに活用し、競走馬に新たな価値を見出すことでビジネスを展開しています。
地元の人々との横のつながりを活かしながら、地域に愛される牧場づくりを目指している様子はまさに田舎起業の特徴を生かしています。
村全体を1つの宿泊施設として運営するSさん(山梨県小菅村)
Sさんは「多摩川の源流を抱える小菅村の魅力を味わってほしい」という思いから山梨県小菅村全体を分散型のホテルとして運営しています。
分散型ホテルというのは一般的な一つの建物に客室が入っているのではなく、同じ地域に複数の客室があるホテルです。
小菅村の高齢化や過疎化で使わなくなった空き家をリノベーションして客室に変えることで、観光地として生まれ変わらせています。
空き家を活用することで初期費用を抑えられ、古民家ならではの日本建築の美しさを楽しめるのでメリットは多く、国内外の多くの観光客に需要があるので、こちらも田舎の良さを生かした起業例です。
田舎での空き家の活用は補助金が出る可能性があるので、古民家を活かした起業を考えているのであれば各自治体に問い合わせてみることをおすすめします。
空き家補助金の一例としてアキサポのサイトもぜひ参考にしてください。

田舎で起業しても実は失敗しやすい業種

都会とは違い、ニーズや人口の違いもあるので失敗する事業もたくさんあります。
実際に失敗しやすいと言われている業種を紹介します。
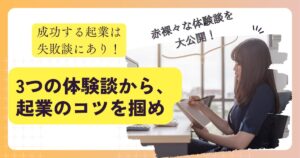
飲食店
飲食店は手軽で、どこでも需要があると思われがちです。
しかし、田舎で新規飲食店を起業し、最初から客単価を高く設定しても集客が出来ないので地域に合わせたリーズナブルな価格設定をすることで開業費を回収するまでに時間がかかるケースが多いです。
最初は物珍しさに来客が多くなるかもしれませんが、地域に根付いた飲食店はすでに多くあるので新規顧客の開拓は難しいでしょう。
田舎での起業を成功させるには、起業戦略や差別化が大きなポイントです。

農業
田舎でゆったりと農業を始めたいと思う方もいるかもしれませんが、地方にはすでに大規模農家がいるので、突然始めた小規模農家では安定した収益を得るのに時間がかかる可能性が高いです。
田舎の地域の農協は横のつながりもあるので、条件のいい土地を見つけたり流通経路を確立するのは簡単ではないのも現状です。
その土地の気候に合わせたやり方もあるので、農家を経験していたとしても突然移住して農家を手探りで始めるのはおすすめしません。

田舎で起業して成功するためのコツ

ここまでいくつかの成功例を紹介しましたが、これらの成功例から参考に出来る成功のコツがあります。
以下でまとめましたので参考にしてください。
「なぜ田舎で起業したいのか」明確にする
田舎での起業をしたいということは何かその場所を選んだ理由があるはずです。
事例のように地域の活性化を目指したい、田舎でしか出来ない事業をしたいなど、どんな理由でもいいのでまずはそれを明確にしましょう。
地域の方にも支援してくれる方にも理解してもらえるような熱い思いが成功へつながります。
田舎でのニーズを冷静に分析する
田舎で起業をしたいのであればその地域の特性やニーズを深く理解することがとても重要になります。
「田舎」と一括りに言っても、47都道府県それぞれの県民性や雰囲気、地域ならではの文化なども全然違います。
その中でどんなニーズがあるのか、実際に地域に入り込んでじっくり分析し、その地域の問題や困りごとは何かということに理解を深める必要があります。

自治体支援や補助金・助成金を活用する
土地や物価が都内に比べて安いので、比較的開業資金は抑えられる可能性がありますが、地域の補助金や助成金を有効に活用すればより費用を抑えることが出来ます。
特に高齢化が進む地域や、過疎化が進んでしまっている地域は地域活性化に力を入れているので、移住や企業に対し補助金などを提供している自治体も多く存在します。
また、補助金や助成金を利用したい場合、申請や審査がやや複雑である可能性もあります。
一人ですべて行うのが心配であれば、専門家を味方につけて一緒に進めることも可能です。
CEOパートナーは資金調達の専門家と起業者をマッチングしてくれるサービスなので、補助金の申請方法や審査通過のコツを知っているだけでなく、万が一補助金が受け取れない場合でも適切な方法で資金調達が出来るようにサポートしてくれます。
電話相談も無料で出来るので、開業資金や資金調達に不安がある方は問い合わせてみることをおすすめします。
\プロの税理士を頼るべき4つの理由をご紹介!/
地域おこし協力隊に参加してみる
地域おこし協力隊は、人口の減少や高齢化が進む地方自治体が都市部などから人材を受け入れる制度です。
地方の特産品のPR活動や地域の方の援助、農業などにも携わり、地域おこしの様々な任務を行います。
地域おこし協力隊に参加するメリットは、協力隊として得られた報酬や支援を受けながら田舎に住むことが出来ること、そしてその地域の特性を知り、地元の方とのネットワークを構築する良い機会になることです。
田舎で起業をする前に突然都市部から移住するのはハードルが高いですが、地域おこし協力隊に参加することでスムーズに地域に馴染むきっかけ作りができるでしょう。
田舎暮らしを成功させる3つのポイント

田舎に住んだことがない方はまず、起業の前に田舎に住むことに向き合わなくてはいけません。
田舎でのビジネスを行うのに必要なのは、「よそから来た部外者」としてではなく「地域のコミュニティに馴染む新しい仲間」として地元の方に受け入れてもらうことです。
そのためにどのようなポイントに注意したらいいか、3つのポイントを紹介します。

移住先を選ぶときの優先順位は明確に
まず、移住先を選ぶ際には何を優先したいかを明確にしてみましょう。
「田舎」と一括りにしても、人口が数百人程度しかいない村から地方でも便利な町もあり、その生活基準の差はかなり幅広いです。
- 人と人のとの距離が近い
- 山と川がある静かな場所
- ある程度栄えていて不便がない
- 観光業が盛ん
- 学校や病院が多い
など、その地域で暮らす・働くことをじっくり考えたときに何を重視するかを考えてみてください。
人とのつながりを大切にする
当たり前ですが、田舎ビジネスはとにかく人と人との繋がりが成功の鍵です。
地域の方との信頼関係を築いていくのは簡単ではないですが、外部から移住してくる立場として、その地域の特性やニーズを理解し、円滑な関係を築くために歩み寄る姿勢があれば必ず受け入れてくれるはずです。
日常の挨拶、イベントへの参加は積極的に行い、都会にはない人との距離感や温かさを感じてください。

過剰に怖がらず、周りをうまく頼る
田舎に住むにあたり、困ったことがあったときに助けてくれるのは人々の支えです。
自分は知らないことも地元の人々ならいろいろなことを教えてくれますし、助け合うことで繋がりは強くなっていきます。
地元の方々はきっと新しく地域に仲間入りした新参者に対して興味を持つはずです。
田舎に移住をしたのであれば受け身にならず、自発的に周囲の人を頼り、関係を深めることが大切です。
まとめ
田舎での起業は人生が大きく変わるターニングポイントとも言える大きな決断なので、もちろん不安があると思います。
しかし、いくつかの成功例を紹介したように、自分自身が本当にやりたいことが明確になっていれば必ず実現できるのです。
田舎起業を手助けしてくれる制度や補助金等もありますし、一人で不安ならCEOパートナーで自分の希望に合った専門家を探すことも出来ます。
自発的に行動を起こすことが成功への道を切り開きます。
今、人生を変える第一歩を踏み出してみてください。


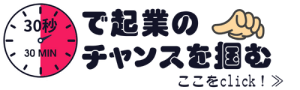








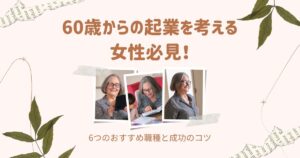

コメント