創業に必要な“資金調達”の専門サポートを受ける
CEOパートナー
会社設立後、条件に当てはまる会社は必ず消費税を納税する義務があります。
納税しなければ脱税となり、最悪の場合、逮捕なんてことも…。
1度でもトラブルがあると信頼を大きく失うことにもなりかねません。
税金は会社を経営する上では正直嬉しくない出費ですよね。
実は合法的に消費税免除する方法があるんです。
条件をしっかり理解し有効活用すれば、大いに節税することだって可能なのです。
本記事ではできる限りお得に会社を経営する方法を伝授いたします。
併せて消費税に関する豆知識も紹介いたします。
ぜひ参考にしていただき、会社経営に役立てていただければ幸いです。
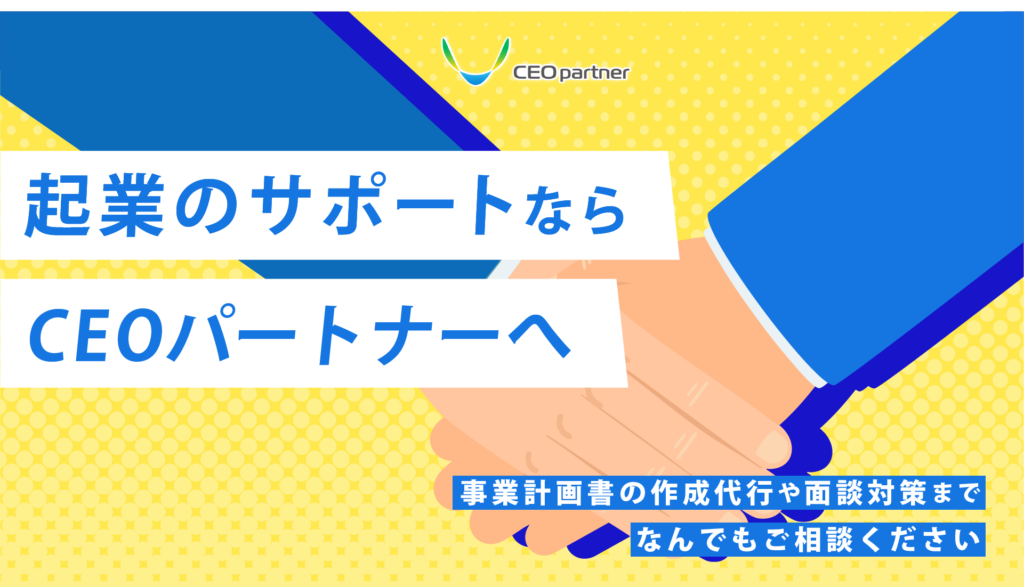
CEOパートナーでは、創業融資をはじめとした資金調達サポートをプロとする税理士法人の担当者を、即日・無料でご紹介しております。
事業計画書の作成代行や面談対策をはじめ、融資だけでなく助成金や補助金の情報提供・お申込みサポートを行っています。
創業後も顧問税理士として頼ることが可能ですので、ぜひお気軽に無料問い合わせをご活用ください。
\相談してから融資を考えてもOK!/
会社設立するなら消費税免除で節税しよう!

創業に必要な“資金調達”の専門サポートを受ける
CEOパートナー
消費税には、小規模事業者に対し、一定の条件を満たせば納税を免除する特例が設けられています。
事業開始後間もない方は、この特例を活用しない手はありません。
とはいえ、少々ややこしい設定のしかたがされていますので、ご自身がこれから免税することはできるのか、免税のために動き出す適切なタイミングはいつなのか、など詳細は税理士に相談するようにしましょう。
\プロの税理士を頼るべき4つの理由をご紹介!/
個人事業主で開業後2年間は免税
個人事業主の場合、基準となる期間(原則としてその年の前々年)における課税売上高が合計1,000万円以下、もしくは開業後2年以内であれば、消費税の納税義務が免除されます。
但し、基準となる期間の売上高が1,000万円未満であっても、その前年の1月1日から6月30日までの期間における売上高が1,000万円を超えた場合は、課税事業者とみなされ、免除が受けられません。

法人成りして2年間免税
法人の場合、設立したばかりで資本金1,000万円未満であれば、1期目については、原則として消費税の納税が免除されます。
2期目については、下記いずれかの条件を満たすことにより、納税が免除となります。
1⃣特定期間(当該年度の前年度の事業開始後6か月間)の売上高が1,000万円以下であること
2⃣特定期間の給与等支払額の合計が1,000万円以下であること
3⃣1期目の期間が7か月以下であること

会社設立時に消費税免除して事業拡大した実話
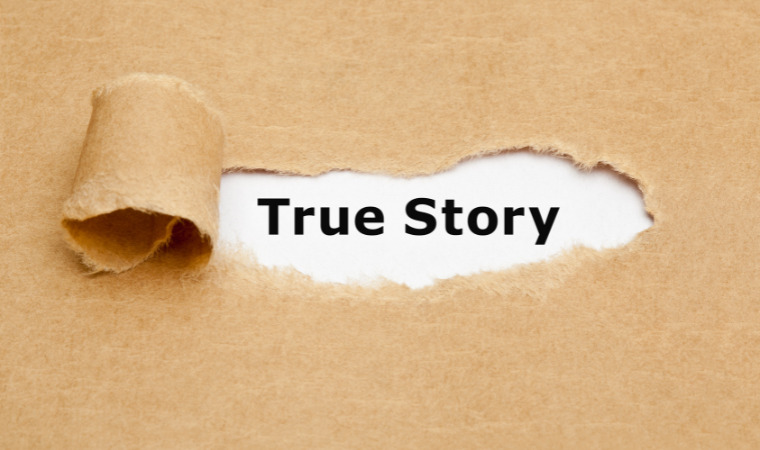
創業に必要な“資金調達”の専門サポートを受ける
CEOパートナー
ここからは節税したお金で事業拡大に成功したリアルな体験談を紹介します。
この方法は皆さんも参考にできる内容かと思います。
ぜひ皆さんも事業拡大を成功させてくださいね。
消費税免除を最大限利用し節税
居酒屋を個人経営でスタートした36歳男性Eさん。
厨房機器や店舗、営業許可申請等のその他の費用にお金がかかり、開業に700万円かかったそうです。
最寄り駅から徒歩5~7分ほどの所にお店を構えたため、立地は案外良い方で、SNSの集客だけでお客さんを呼び込むことができたという。
定休日は毎週火曜日に設定。1日の客数はだいたい6~7人、客単価は5000円。
そして1年目の売上は1010万円となり、2年後には課税対象事業者となってしまった。
徐々に常連のお客さんも増え、安定的に売上が見込めるようになっていった。
2年目は1100万を超えていた。
このまま課税事業者として経営を続けると、3年目は売上が1500万円と予想されるため消費税を150万円支払わなければならない。
そこで個人事業主から法人成りをすることで翌年からの納税を免れることにしたという。
個人事業主のまま続けていたら、その後2年間で本来300万円以上の消費税を払わなければいけないが、法人成りすることで300万円以上を節約することができる。

ポイントは【税理士】を頼ったこと
今回Eさんが節税できたのは、ある専門家を適切に頼ったからです。
確定申告の相談や、事業を長期的に見つめたときに必要となる資金調達の相談をしたくて、税理士を頼ったのです。
実は、Eさんは創業当初に創業融資を受けており、その創業融資の申請をサポートして成功まで導いたのが、「CEOパートナー」というサービスを介して出会った税理士法人でした。
CEOパートナーは国から認定を受けた支援機関のみを扱う専門家とのマッチングサービスで、一人で申請すると成功率はたったの20%と言われている創業融資を、難なく審査通過まで導いたのです。
その確かな専門性を信じて、消費税など納税において見直せる部分がないのか、尋ねたくて再度、税理士まで連絡しました。
もちろんのこと、税理士は“税務のエキスパート”です。
調べてもよくわからなかった消費税に関連する制度について、税理士からわかりやすく案内があり、制度の適用に向けて法人成りの適切なタイミングをアドバイスしてもらったのでした。
そしてEさんは結果的に、かかるはずだった税金を抑えることで、事業拡大に回すことができ、実際に店舗を一つ増やすことができました。
その店舗の売上も初年度から1000万が予想されているという。
創業融資など、創業前の資金調達から創業後の税務・経営アドバイスと一貫して相談できる税理士法人は、実はそれほど多くありません。
CEOパートナーなど、サービス内で厳選された税理士法人を頼るのが最も効率的で、事業を円滑に進める賢い方法なのです。
\創業融資のプロ・税理士法人を即日紹介/
※フォーム送信後5~10分でお電話を差し上げます
会社設立時に消費税免除して後悔しない3つのポイント

創業に必要な“資金調達”の専門サポートを受ける
CEOパートナー
「免税」と聞くと一見メリットばかりが目を引きますが、2023年10月から始まるインボイス制度では、免税事業者にとってはデメリットの影響が予想されます。
早まることなく、よく制度内容を確認して現状から変更が必要なのか、そうでないのかを判断しましょう。
インボイス制度は新しいことで前例がなく、わかりづらい部分が多いために、実際に税理士から指示を仰ぐことをおすすめします。
\プロの税理士を頼るべき4つの理由をご紹介!/
免税事業者は検討すべき!これから始まるインボイス制度
インボイス制度とは、一定の要件を満たした適格請求書(=インボイス)のやり取りを通じ、請求書を受け取った側が、消費税の仕入税額控除をできるようにする制度です。
適格請求書を発行するには、国税庁に適格請求書発行事業者として登録申請手続きを行う必要性があります。
制度導入後は、消費税を納付する際に、この適格請求書がないと、仕入税額控除が受けられなくなります。
そのため、課税事業者(消費税を納税する義務のある個人事業主や法人)、免税事業者(課税売上高1,000万円未満の個人事業主や法人)双方にとって、デメリットが起こり得ます。
課税事業者は、インボイスを発行しないと消費税の仕入税額控除ができないため、自社の税負担増につながります。
免税事業者は消費税の納税が免除される代わりにインボイスを発行することができないため、事業者や事業の内容によっては、これまでの取引を見直される可能性が出てきます。
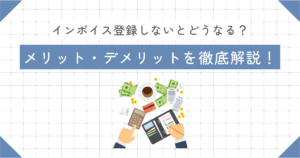
法人成りとインボイス制度の影響
インボイス制度の導入により、法人事業者の消費税免除期間に影響が出ると予想されています。
事業者に対する消費税納税は、基本的に売上高1,000万円を超えた場合に課される仕組みとなっています。
個人事業主から法人化(法人成り)した場合はどうなるのでしょうか。
現行の仕組みでは、法人になる前の2年間は課税対象期間に含まれないため、条件が整えば2年間は納税義務を免除することができました。
しかし、インボイス制度の導入に伴い、取引先によっては、適格請求書が発行できなければ、取引そのものが見直されるケースも出てくるでしょう。
適格請求書を発行できるのは課税事業者に限定されるため、課税事業者として登録せざるを得ず、結果的に消費税免税の恩恵が受けられなくなる可能性が考えられます。

消費税免除で、できる限り得をする方法
インボイス制度の導入によって影響を受けるのは、主に事業者との取引(BtoB)に限った話であり、一般消費者との取引(BtoC)が多い場合については、その影響は比較的受けづらいと考えられます。
そのため、現行の消費税免除制度を最大限活用するのであれば、以下3つの方法がオススメです!
1⃣BtoC向けの事業を個人事業主として起業
2⃣2年間は課税売上高1,000万円以内に抑える
3⃣2年を経た後に法人化
事業年度1期目が経過した後は、その時点での売上規模や取引先との関係性、今後の事業方針等を鑑みる必要性があります。
取引先との関係性を良好に保ちつつ、今後さらに事業規模の拡大が見込めるのであれば、わざわざ免除にこだわる必要性はありません。
しかし、事業拡大のための準備期間に充てるという名目で、売上規模を調整しながら、免税のメリットを受けることも1つの手です。
一定規模を維持しながら事業を継続していきたいのであれば、免税によるメリットの方が恩恵も大きいです。
その場合、更に1年間の納税免除を受けることも可能。
いずれの方法を取るにしても、選択肢は多いに越したことはありません。
会社設立後の消費税申告・納付のやり方

創業に必要な“資金調達”の専門サポートを受ける
CEOパートナー
課税売上高が1,000万円を超える場合、要件を満たす事業者には納税の義務が生じます。
ここでは、納税の申告方法について説明していきます。
正直どれも専門性の高い業務にはなりますので、間違って申告して後から面倒ごとにならないためにも、必要経費と捉えて税理士を頼るようにしましょう。
消費税の申告
個人事業主・法人共に、原則として当該年度の2年前の事業年度が消費税の課税対象の期間となります。
この期間内に課税対象となる売上高が1,000万円を超える場合、消費税の課税対象として、納税の義務が生じます。
消費税の計算方法は、「原則(一般)課税方式」と「簡易課税方式」の2通りがあります。
原則(一般)課税方式の場合は、当該事業年度における売上金額(税込)から、仕入等の経費で払った金額(税込)を引いた分で計算されます。
簡易課税方式の場合、経費で払った金額については、売上金額×業種ごとのみなし仕入率を用いて計算されます。
税金の納付と還付
申告に際し必要な書類「消費税申告書」は、国税庁のHPまたは管轄の税務署窓口で入手することができます。
先ほど前項にてご紹介した計算方法に基づいて消費税を計算し、管轄の税務署に消費税を納付するわけですが、正規の手順に則って計算してみると、中には「仕入等で支払った消費税額が、預かった消費税額よりも大きかった」という場合があるかと思います。
特に創業間もないタイミングでは、何かと設備購入資金が必要ですし、期中に不動産や機械、車両などの大きな設備投資を行うことがあるでしょう。
こうした事例によって多く払い過ぎた税金は、条件を満たせば返金(還付)されます。
しかし、還付を受けるにあたっては、原則(一般)課税方式を適用していることがひとつの条件となります。
一見すると簡単にできそうな内容ですが、ひとたび計算ミスをしてしまうと、「余分に税金を納めてしまっていた」となりかねませんので、税理士まで必ず相談するようにしましょう。
\プロの税理士を頼るべき4つの理由をご紹介!/
万が一資金が足りなくなった時の対処法
先ずもって行うべきは、各取引先との交渉です。
現在の状況を伝えた上で、可能な限りリスケ交渉に臨みましょう。
日頃から関係性が構築できていれば、相手も人間ですから一定の猶予には応じてくれると思いますが、こちら一辺倒の要望ばかりでは、やがて相手も愛想を尽かしてしまいます。
また、せっかく取り交わした約束を反故にしてしまっては、元も子もありません。
相手方との話し合いにおいては、事実や根拠に基づきこちらの要望を伝えること、そして相手方の要望も汲み取りながら、お互いの歩み寄り(譲歩)を見出すことが目的だと、私は考えています。
実務面においては、万が一に備え、メインバンク以外に取引や口座を作ることをおすすめしますが、個人的にはその中にノンバンクとの取引も入れておくことをおススメします。
銀行と比べると借入金額は少なく金利は高いですが、いざという時の融資のスピード感は、銀行とは比べ物になりません。
いざ資金繰りに窮し支払が滞ってしまった場合も、日頃からきちんと関係性を構築できていれば、比較的融通や相談に乗ってくれることもあります。
ですが焦ったときこそ、冷静に第三者目線からアドバイスしてくれる税理士を頼りましょう。
CEOパートナーからご紹介する税理士法人は、税務はもちろん、資金繰りに困ったときの適切な調達手段を提案・申請サポートまで行っています。
「お申し込みフォーム」に必要事項を入力し、「送信する」をクリック。入力から送信までは1~2分程度です。
フォーム送信後、通常ですと5~10分以内にスタッフから電話連絡があります。電話の所要時間は3分程度で、税理士法人の担当者への相談日時を調整します。
※万が一電話に出られなかった場合は、メールアドレス宛に連絡が入ります。
お約束の日時に税理士法人の担当者から直接、電話連絡が入ります。ヒアリングが行われますので、そのままご相談内容をお話ください。担当者よりサポート可能と判断されたら、一人ひとりの状況に沿って次のステップ(事業計画書の作成面談など)が提示されます。
\今すぐお申し込みはこちらから/
\審査に強い理由をもっと知るなら/
 小久保さん
小久保さん融資成功までは一切請求のない「完全成功報酬型」ですのでご安心ください!
まとめ
今回は主に、消費税の免除要件を中心に述べてきました。
2023年10月から導入されるインボイス制度に伴い、免除の恩恵を受けられなくなる可能性があることは、小規模事業者にとって頭の痛いところではあります。
しかし、これまで紹介してきた各種補助金や助成金、節税対策など、事業者にとって様々な恩恵を受けられる機会や制度があることも事実です。
「木を見て森を見ず」という諺がある通り、全体を俯瞰してみることで見えることや分かることがあるのではないでしょうか。
自分一人ではなく、取引先や専門家と呼ばれる方々の力も借りながら、自らの事業の糧にしていただければ幸いです。
節税など税務の相談だけでなく、運転資金の確保や、事業拡大を見据えている方は一貫してサポート可能な【CEOパートナー】を頼りましょう。

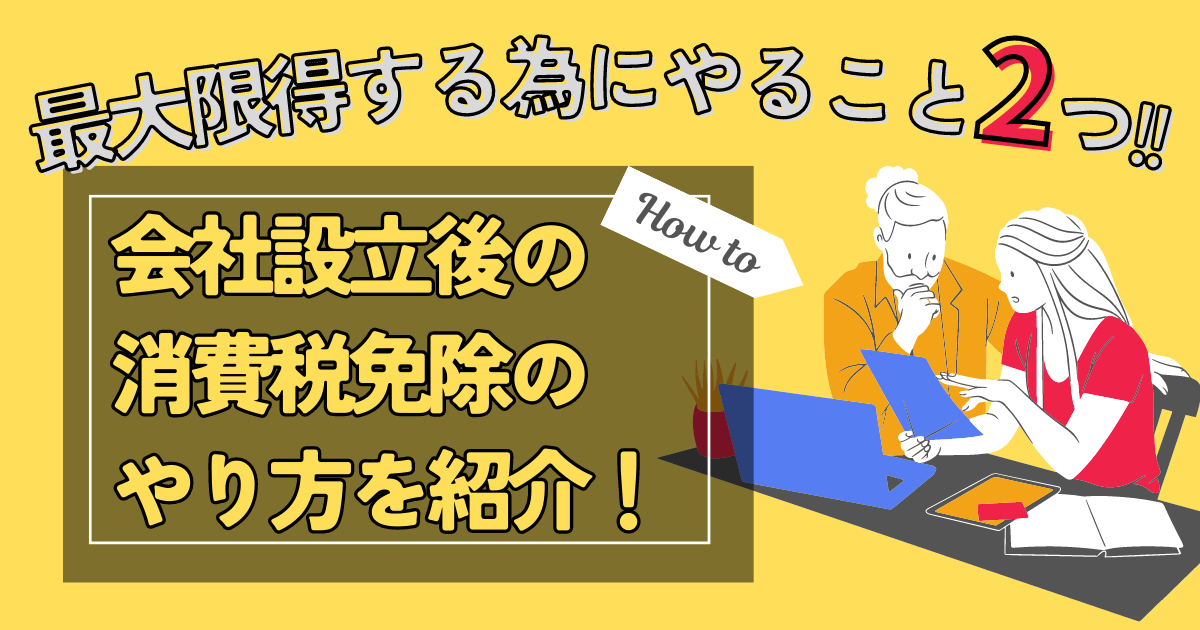


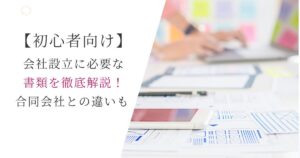
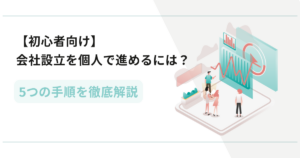
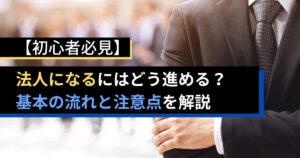


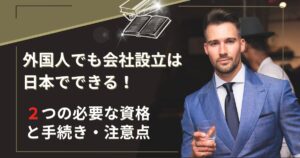
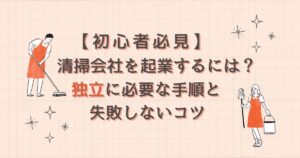

コメント
コメント一覧 (10件)
[…] ②事業売上高が1000万円を超えている場合 2つ目は事業売上高が1000万円を超えている場合です。個人事業主でも法人でも売上が1000万円を超えると、その2年後から消費税課税事業者となり消費税を納めなければなりません。個人事業主として事業を続け、年間の売上高が1000万円を超えた翌年に法人成りすることで、さらに2年は消費税の納税が免除されます。もちろん納税から免れることはできませんが、2年間免除されるのは大幅に節税に繋がります!節税するために法人成りをする方はいないと思いますが、法人成りをする目安にすると良いでしょう! […]
[…] […]
[…] […]
[…] が消費税が2年間免除されるのは大幅に節税に繋がります。 この事業売上高も法人化の目安の1つです。 関連記事:会社設立後の消費税免除のやり方を紹介!最大限得する為にやること2つ […]
[…] あわせて読みたい 会社設立後の消費税免除のやり方を紹介!最大限得する為にやること2つ 会社設立後、条件に当てはまる会社は必ず消費税を納税する義務があります。実は合法的に消 […]
[…] と複雑で会社側はその計算をして国に納税しなければいけません。 会社設立をした場合、消費税の納税義務は課税売上高が1000万円超えた場合に発生します。法人の場合の基準期間におけ […]
[…] あわせて読みたい 会社設立後の消費税免除のやり方を紹介!最大限得する為にやること2つ 会社設立後、条件に当てはまる会社は必ず消費税を納税する義務があります。実は合法的に消 […]
[…] あわせて読みたい 会社設立後の消費税免除のやり方を紹介!最大限得する為にやること2つ 会社設立後、条件に当てはまる会社は必ず消費税を納税する義務があります。実は合法的に消 […]
[…] あわせて読みたい 会社設立後の消費税免除のやり方を紹介!最大限得する為にやること2つ 会社設立後、条件に当てはまる会社は必ず消費税を納税する義務があります。実は合法的に消 […]
[…] あわせて読みたい 会社設立後の消費税免除のやり方を紹介!最大限得する為にやること2つ 会社設立後、条件に当てはまる会社は必ず消費税を納税する義務があります。実は合法的に消 […]