創業に必要な“資金調達”の専門サポートを受ける
CEOパートナー
ChatGPTやMidjourneyといった生成AIの登場により、ビジネスの在り方が大きく変わっています。
世界中のスタートアップがAIを活用し新しい価値を生み出している中、日本でもAIを活用した起業のチャンスが広がっているのです。
本記事では、AI起業の基本的な知識と成功事例、押さえておきたいポイントを解説します。
あなたも、AIを活用したビジネスの第一歩を踏み出してみませんか?
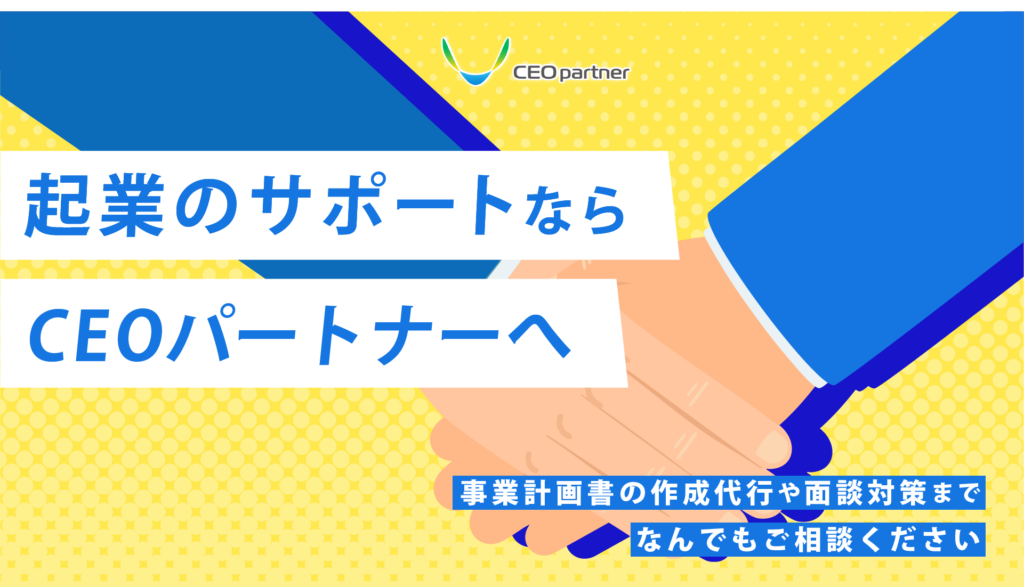
CEOパートナーでは、創業融資をはじめとした資金調達サポートをプロとする税理士法人の担当者を、即日・無料でご紹介しております。
事業計画書の作成代行や面談対策をはじめ、融資だけでなく助成金や補助金の情報提供・お申込みサポートを行っています。
創業後も顧問税理士として頼ることが可能ですので、ぜひお気軽に無料問い合わせをご活用ください。
\相談してから融資を考えてもOK!/
AI起業の基礎知識
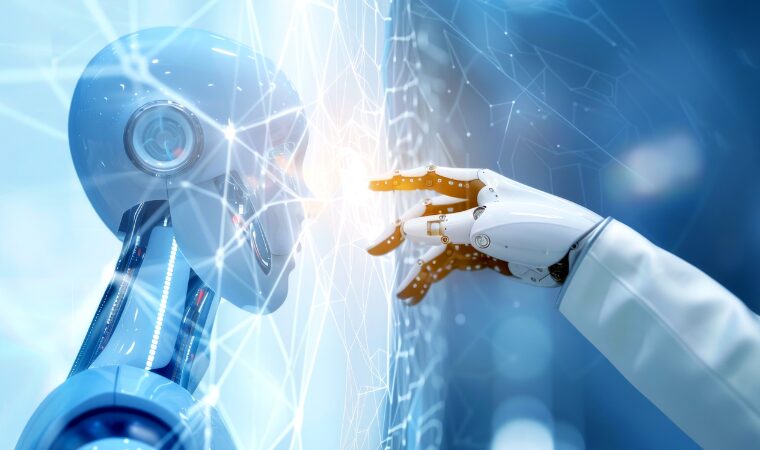
創業に必要な“資金調達”の専門サポートを受ける
CEOパートナー
AI(ArtificialIntelligence)技術の進化により、AIを活用したビジネスに注目が集まっており、AI起業を目指す方にとっては、技術の選定やビジネスモデルの構築など、市場での競争に対応する戦略は欠かせない要素となっています。
そのために、まずはAIを活用して起業するためのポイントを順を追って見ていきましょう。
「AI起業」とは
AI起業とは、人工知能(AI)を活用して新しいビジネスを創出することを指します。
その本質は単なる技術導入にとどまりません。
AIは膨大なデータを解析、学習し、意思決定を自動で行う能力を持っており、今までのビジネスプロセスを効率化するだけでなく、新しい価値の創造や市場開拓を促します。
AI起業に必要な資格・スキル
AIに関する知識やスキルを客観的に証明するために資格を取得しておいたほうが、自己レベルの見える化や他との差別化につながります。
また、クライアントなどの取引先に対しても安心感や信頼度が増します。
以下にAI関連の資格についてご紹介いたします。
【E資格】
E資格は一般社団法人「JDLA(日本ディープラーニング協会)」が主催する、ディープラーニングに関する資格で、E資格の「E」は「Engineer」の略称です。
ディープラーニングを扱うエンジニア向けのスキルを証明するための資格です。
尚、E資格の受験資格として、試験以外で必要な知識を習得するために「JDLA認定プログラム」と呼ばれる講座を受講することが必要となっています。
【G検定】
G検定は、E資格と同じく一般社団法人ディープラーニング協会が主催する、ディープラーニングの基礎知識としてのスキルを証明する資格です。
前述のE資格よりもG検定は「ディープラーニングの知識を生かして応用する」ことに特化した資格です。
難易度としてはE資格よりも優しく、受験資格も必要ないため、E資格取得に向けたファーストステップとして受験する 人もいます。
【AI実装検定】
AIに関する知識と実装力を認定する資格です。
ディープラーニングやAI実装のプログラミング知識などを問われる検定で、B級・A級・S級という段階があり、自分のレベルによって受けることができます。
また、特徴としてG検定とE検定の実装レベルを意識した設定となっており、S級はE検定の上をいくAIの最難関資格に位置づけられます。
【AWS専門知識認定資格】
Amazonが提供するクラウドサービス「AWS(Amazon Web Services)」を活用するための資格です。
AmazonのサービスであるAWSに関する知識を証明でき、さまざまな分野やレベルの資格があるため、エンジニアにとって自身の保有スキルの種類及びレベルを見える化するために有効な資格です。
近年では、情報処理安全確保支援士の次にこれから取りたいIT資格2位を獲得するなど、人気が高くなっている資格です。
【認定AI・IoTコンサルタント(AIC)】
認定AI・IoTコンサルタントは、日本初のAI×IoTに特化したコンサルタント資格です。
認定を受けるためには、指定された研修試験を受講する必要があり、オンラインだけでも、またはオンラインとオンサイトを組み合わせたハイブリッド式という形でも研修を受けることができます。
ジュニア・シニア・マスターと3種類あり、コンサルティングスキルを身につけるには、シニア以上が必要です。
但し、シニア以上からいきなり受講することはできず、まずはジュニアから段階的に認定を受けなければなりません。
試験内容としては基本的には研修受講範囲から出題されますが、主に①DX実践のためのAI・IoTを代表とするデジタル化②ケーススタディで学ぶDXProcess(DXP)③AIPA認定資格の紹介となっています。
【Professional Data Engineer】
Professional Data Engineerは、Googleが主催する「Google Cloud認定」のうちの一つです。
データ主導の意思決定を支援するためのシステム設計・構築・運用に関する専門知識を証明します。
日頃からGCPを利用していたり開発していたりする人にとって、さらなるスキルの習得の機会や保有スキルの棚卸しになる資格です。
受験するためには、業界経験が3年以上かつ、Google Cloud を使用したソリューションの設計と管理の経験が1年以上ある方が推奨されています。
AI起業のメリット
AI起業をするメリットは、どのようなものがあるのでしょうか。以下に挙げてみました。
・新しいビジネスの創出
AIを活用することで、これまでになかった新しいビジネスを創り出すことができ、チャンスの幅が拡大します。
・業務の効率化
AIを活用することで、従来は人間がおこなっていた作業を自動化が可能となり、時間短縮や人件費削減など業務効 率化を図ることができます。
・新たな価値の創造
AIを活用することで、新たな付加価値を創り出すことも可能になります。
AI起業のデメリット
AI起業は、前述のようにメリットがとても多くありますが、良いところばかりではなくデメリットもあります。
・技術が複雑
AIは、ディープラーニングや機械学習など、高度な技術を活用しています。そのためAI起業するにあたり、これらの技術を理解および実装できる技術力が必要です。また、AIの技術は日々進化しているので常に最新技術の習得が不可欠となります。
・競争の激化
近年AIは、さまざまな分野で活用の可能性が広がっており、AIを活用したビジネスは競争が激化しているというデメリットがあります。AIで起業する際には、競合他社との差別化を図ることがカギとなります。
・資金調達の難しさ
AI起業は、初期投資額が大きい傾向にあるため、資金調達について考慮しなければなりません。AI起業をする際にはVC(ベンチャーキャピタル)やエンジェル投資家から資金調達するという選択もあります。
AIを活用したビジネスモデルの例

創業に必要な“資金調達”の専門サポートを受ける
CEOパートナー
上記で述べた通り、AI起業には様々なメリット・デメリットがあります。
しかしながら、人手不足や技術の継承など課題を抱えている多くの企業が存在しています。
それらを解消するためにAIで新ビジネスを生み出し、活用している事例についてみていきましょう。
AI面接サービス「SHaiN」
AI面接サービス「SHaiN」は、24時間365日いつでも世界中どの場所でも面接することを可能にした、世界初※の対話型AI面接サービスです。(※SHaiN調べ)
AIがヒアリングを行い、AIがSHaiN独自の構造化面接手法「戦略採用メソッド」に基づき、面接評価レポートを作成するサービスを提供しています。
導入企業は、飲食業・サービス業・金融業など、様々な業種で利用されています。
蔵書管理サポートサービス「SHELF EYE」
AI蔵書管理サポートサービス「SHELF EYE(シェルフ アイ)」は、図書館の蔵書点検の効率化を図るため、AIで本の背表紙画像を解析することで蔵書管理を支援するサービスです。
蔵書点検は図書館の重要な業務のひとつですが、図書館運営の大きな負担にもなっています。
人手不足が深刻であるにも関わらず、職員総出での数万冊におよぶ蔵書をバーコードで1冊ずつ読み取る作業は、膨大な時間と工数を要するため「SHELF EYE(シェルフ アイ)」によって作業を効率化することができます。
AIコピーライター「AICO」
AIコピーライター「AICO」は、電通が開発した人工知能による広告コピー生成システムです。
自然言語処理の専門家と同社のクリエイティブディレクターや広告制作の実務に携わるコピーライターもプロジェクトに参加し、人工知能の学習をサポートすることで、より人間に近いコピーの生成を可能にし、1度に2万案ものクリエイティブを作成します。
AI職人「THEO(テオ)」によるバウムクーヘン製造
THEO は株式会社ユーハイムが開発したバウムクーヘン AI 職人です。
職人が焼く生地の焼き具合を各層ごとに画像センサーで解析して、データ化された技術をAIに機械学習させ、THEO だけで職人と同じレベルのバウムクーヘンを焼き上げます。
THEO開発の背景には、添加物を使わずに菓子を製造したいという思いから、材料メーカーと共に、加工材料から添加物の排除を実践する「純正自然宣言」を行いましたが、純正自然の菓子作りを進めていきながら、生産性を高めるためには、添加物のなかった頃の職人の技術復活や継承、新たな職人の育成が必要となります。
その時間も手間もかかる過程のブレイクスルーとして、技術革新が相次ぐIOTやAIの技術を活用しました。
AI起業のビジネスモデルの考え方

創業に必要な“資金調達”の専門サポートを受ける
CEOパートナー
AI起業をおこなうにあたり、アイデアや技術力をどのようにビジネスに結びつけ、クライアントのニーズに応えられるかが重要となってきます。
また、収益を生むためのビジネスモデルの確立は、成功するための重要なポイントです。
AI起業のビジネスモデルでは、以下のことを考慮する必要があります。
顧客ニーズを調査する
AIを活用したビジネスで成功するためには、顧客ニーズを敏感に捉え、それに基づくビジネスモデルを構築することが非常に重要です。
顧客の声を積極的に収集・分析し、顧客の行動を観察するなど、潜在的なニーズを如何に把握できるかも大切です。

AIを活用する領域を決める
AIを活用する際には、領域を決めておくことが大切です。
AIを活用すると時間や労力が大幅に削減されますが、あくまでも補助ツールであり、最終的にはAIを活用している人が判断しなければなりません。
また、AIが生成した文章や画像などは著作権や個人情報および倫理面での問題はないか、必ずチェックをするなど防衛策も必要です。
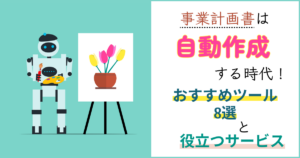
収益モデルの設計
AI起業では、持続可能な収益モデルの構築がとても重要です。
以下に挙げる収益モデルが一般的に採用されています。
・プロジェクト型モデル
顧客ごとのニーズを汲みとり、カスタマイズされたAIソリューションの提供。
(例)AIを活用した健康管理アプリは、ユーザーのデータを分析し個別に最適化された健康アドバイスを提供する仕組みの構築など
・サブスクリプションモデル
月額料金でAIソリューションを提供して、収益を安定的に確保。
・データ収益化モデル
AIが解析したデータを顧客に提供し、利用料を収益源とする。
他の分野や技術と組み合わせる
AIをさまざまな分野や技術と組み合わせると、日常生活においても今までより一層便利な製品が誕生しています。
AIの技術を応用し、どのようなことに活用されているのか、実際の事例を以下にご紹介いたします。
【AI×家電:AI電子レンジ「ヘルシオAX-XW400」】
電子レンジ「ヘルシオAX-XW400」は、音声操作や会話による献立の相談ができ、過去の相談内容や利用状況から、AIがその家庭の好みに合った献立を提案します。
【AI×モビリティ:自動運転車】
高速道路渋滞時など一定の条件下で、ドライバーに代わって運転操作を行います。
自動運行装置は、下界認識・自社位置認識・ドライバー状態検知・機能冗長化の装備から、周囲の状況を認識して状況にあった運転操作を行います。
【AI×機械】
AI搭載ロボット「Pepper」は、クラウドAIと感情エンジンを搭載している感情認識ヒューマノイドロボットです。
活躍場所は商業施設や教育施設、介護施設、オフィスなどさまざまです。
【AI×宇宙】
NASAは月のクレーターマップ作成をAIで自動化に成功しました。
CNNで画像認識し、影や地面の形からクレーターマップを作成でき、3時間かけて人間がおこなっていた作業をわずか1分で終わらせます。
【AI×カメラ】
「Pixellot」は今まで人間が時間と手間をかけて行なっていた、カメラ撮影・ハイライト作成・CM挿入・データ分析などの作業を独自のオートメーション・テクノロジーで簡単に処理されます。
対応スポーツはサッカー、バスケットボール、ラグビー、アメフト、バレーボールなど多岐に渡り、90%以上の製作コスト削減を実現します。
AI起業で押さえておきたいポイント
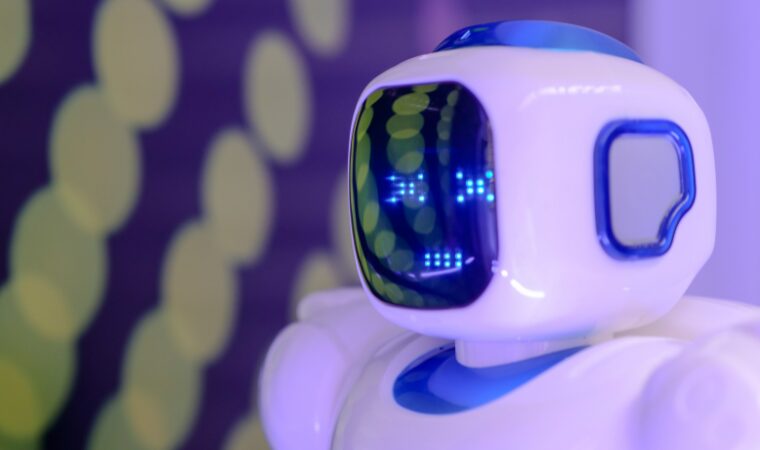
創業に必要な“資金調達”の専門サポートを受ける
CEOパートナー
AI起業することは、社会に新しい価値を提供できる大きな可能性を秘めています。
しかしその反面、多くの注意点があり、怠ると大きな問題に発展する可能性があります。
AI起業に際して押さえておくべきポイントについてみていきましょう。
目的と目標の明確化
まず、目的と目標の明確化が必要です。
市場調査を通じて、顧客が直面している問題や、業界が抱える非効率性を特定するなど、AIを活用したサービスが、どのように価値を提供できるかを明確化することが大切です。
セキュリティ対策の徹底
AIシステムは膨大なデータを扱うため、セキュリティ対策とプライバシー保護は最重要課題です。
データ漏洩や不正アクセスを防ぐために、万全なセキュリティ対策が求められます。
必要な人材の育成
単なる技術の知識を持っているだけではなく、ビジネス課題を理解し解決できる能力を持っている人材育成が重要です。
AI技術の本質を理解しつつも、クライアントのニーズに合わせた実用的なソリューションを提案できる存在が求められています。
継続的な評価と改善
継続的に評価を得るためには、最新かつ実践的スキルや情報を常にアップデートしておくことが重要です。
また、顧客や市場のニーズに対応し、社会的な課題に積極的に取り組み改善することにより、さらに必要とされる存在となるでしょう。
起業の相談は「CEOパートナー」へ

CEOパートナーでは、起業相談を行なっております。
AI起業するにあたり、資金調達が最重要課題です。
融資の申請には多くの書類や満たすべき条件があり、一つでも欠けていると却下される可能性があります。
起業支援申請を自分だけで行うのが不安な場合は、開業のプロと一緒に進めましょう。

【当サイト限定】融資決定までは完全無料の徹底サポートです
無料で即日、創業融資など資金調達に詳しい税理士法人を紹介してもらえるのは正直、ここだけ。
自力で適切な専門家を探すのは効率的ではありません。
資金調達のタイミングを逃さないで!
全国相談件数NO.1の税理士法人と提携
CEOパートナーでは、AI起業をするにあたり、適切な税理士を選定してくれるので、自分自身の事業に合った税理士を見つけられます。
メールや電話相談もできるので、まずはお気軽に相談から始めてみてください。
事業計画書の作成をサポート
CEOパートナーでは、事業計画書の作成をサポートしています。
面倒な資料作成などは全て代行・丸投げ可能な支援機関のみとタッグを組んでいるので安心してお任せできます。
資金調達の成功率アップ
自力での創業融資の成功率はたったの20%と言われています。
また、一度失敗すると再挑戦するためには半年以上かかり、二回目以降はますます不利な状況になるそうです。
そうなる前にぜひ一度CEOパートナーへお問い合わせください。
「お申し込みフォーム」に必要事項を入力し、「送信する」をクリック。入力から送信までは1~2分程度です。
フォーム送信後、通常ですと5~10分以内にスタッフから電話連絡があります。電話の所要時間は3分程度で、税理士法人の担当者への相談日時を調整します。
※万が一電話に出られなかった場合は、メールアドレス宛に連絡が入ります。
お約束の日時に税理士法人の担当者から直接、電話連絡が入ります。ヒアリングが行われますので、そのままご相談内容をお話ください。担当者よりサポート可能と判断されたら、一人ひとりの状況に沿って次のステップ(事業計画書の作成面談など)が提示されます。
\今すぐお申し込みはこちらから/
\審査に強い理由をもっと知るなら/
 小久保さん
小久保さん融資成功までは一切請求のない「完全成功報酬型」ですのでご安心ください!
まとめ
今回は、AI起業をする際のメリット・デメリットや成功事例、押さえておきたいポイントについてご紹介いたしました。
AIはめざましい進化を遂げており、それにともないビジネスの場にAIを導入する企業も増加しています。
今後AIスキルは幅広い業界の新たなサービスの開発に必須となってきます。
AI起業される方にとって、この記事が参考になりましたら嬉しいです。









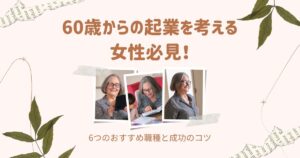


コメント