創業に必要な“資金調達”の専門サポートを受ける
CEOパートナー
すべての国民が、医療保険制度などの社会保険に加入することを義務づけられている日本。
会社勤めの方は、会社が社会保険の加入手続きを代行してくれます。
入社時に沢山の書類を渡され、記入した覚えはありませんか?
いわゆるアレが、社会保険加入手続きになっていたんです。
しかし独立したら、医療保険や年金などの社会保険手続きを自身で行わなければなりません。
社会保険にはいくつか種類があり、加入時期や加入条件、保険料などそれぞれ異なります。
独立したら、いつまでにどの保険に入らなければいけないのかを本記事ではわかりやすく、徹底解説していきます。
会社にとっては負担となる制度ではありますが、事業主と会社を守る重要な制度ですので、しっかりと知識として落とし込みましょう。
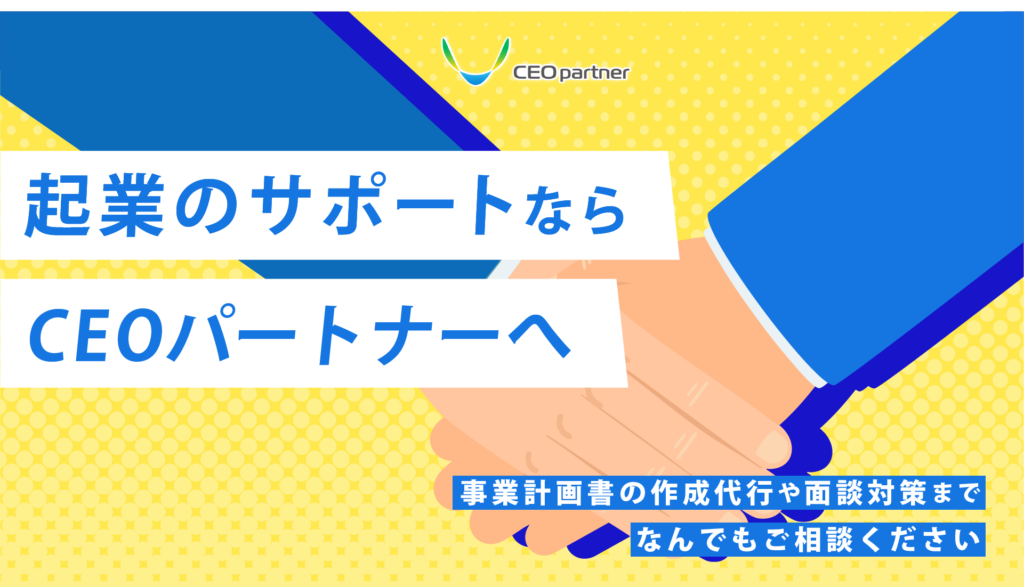
CEOパートナーでは、創業融資をはじめとした資金調達サポートをプロとする税理士法人の担当者を、即日・無料でご紹介しております。
事業計画書の作成代行や面談対策をはじめ、融資だけでなく助成金や補助金の情報提供・お申込みサポートを行っています。
創業後も顧問税理士として頼ることが可能ですので、ぜひお気軽に無料問い合わせをご活用ください。
\相談してから融資を考えてもOK!/
独立したら加入すべき社会保険は3つ

創業に必要な“資金調達”の専門サポートを受ける
CEOパートナー
独立を決意したそこのあなた。
今まで会社勤めだったために、保険のことが分からなくてお困りではないですか?
独立後の生活において、安心して仕事を続けるためには保険への加入は欠かせません。
そこで、独立したら加入すべき「3つの主要な保険」について、ここでは徹底的に解説していきます。
自分を守るための知識にもなります。
最後までしっかり読んで、独立への第一歩に備えて準備していきましょう。
医療保険
医療保険は、突然の病気やケガに備えたり、健康的な生活を維持したりする上で医療費を抑えることのできる重要な保険です。
一般的な医療保険は2種類
・健康保険
・国民健康保険
健康なうちから充分な保障を受けるためにも、加入のタイミングや条件をよく理解しておくことが重要。
それぞれの違いや加入条件、保険料についてはこのあとに詳しく解説していきます。
年金保険(国民年金保険・厚生年金保険)
年金保険は、将来の生活や老後の資金を確保するためにも重要な保険のひとつです。
主な年金保険は2種類
・国民年金保険
・厚生年金保険
独立後の将来の不安を軽減する為にも、しっかり理解しておきましょう。
それぞれの違いや加入条件、保険料についてはこのあとに詳しく解説していきます。
労働保険(雇用保険・労災保険)
労働保険は、労働者が仕事をする上での安全や安心を確保するための保険です。
主な労働保険は2種類
・雇用保険
・労災保険
労働保険に加入すると、仕事によるリスクから守られるだけでなく、突然の失業や労災に対しても備えることができるため、とても重要な役割のある保険といえます。
それぞれの違いや加入条件、保険料についてはこのあとに詳しく解説していきます。
独立時の医療保険を理解しよう

創業に必要な“資金調達”の専門サポートを受ける
CEOパートナー
病気予防のための通院・突然の病気やケガによる手術や入院、これらの医療費負担を軽減するのが「医療保険」です。
あなた自身の健康を守るためにも、適切な医療保険に加入することが重要。
医療保険は「健康保険」と「国民健康保険」の2種類があると説明してきましたが、それぞれ異なる特徴や加入条件がありますので、さらに深く解説していきます。
健康保険と国民健康保険の違い
決定的な違いは、加入条件です。
「健康保険」は企業や団体に勤務する従業員が加入する保険ですが、「国民健康保険」は、自営業者や学生、無職者など、健康保険の加入条件に満たない人が、加入する保険です。
加入条件が異なることで、加入時の手続きにも違いがあります。
「健康保険」は、雇用者によって加入の手続きが行われ、労働者は会社に勤務することで自動的に加入することができます。
「国民健康保険」に加入するには、まずは居住地の役所に行き、あなたご自身でお申し込みを行い、手続きを完了させる必要があります。
このように、加入条件や加入方法は異なりますが、いずれも医療費の補償を目的とした重要な制度です。
加入条件
加入条件は加入保険によって異なります。
それでは健康保険と、国民健康保険の2つの加入条件を紹介していきます。
健康保険の加入条件
①企業や団体に勤務していること(例:会社員・公務員)
②一定の時間以上勤務しているか、特定の条件を満たすパートタイマー
→一般的には週30時間以上 ※具体的な条件は雇用主や企業によって異なります。
国民健康保険の加入条件
①従業員としての加入資格がない個人であること(例:自営業・学生・無職者)
②日本国内に住んでいること
③一定の時間以上勤務しているか、特定の条件を満たすパートタイマー
→一般的には週30時間以上 ※具体的な条件は雇用主や企業によって異なります。
保険料
加入保険によって保険料もそれぞれ異なります。
それでは健康保険と、国民健康保険の2つの保険料を紹介していきます。
健康保険の保険料
保険料の金額は、所属する会社や加入者の年収・所得によって異なりますが、一般的には収入が多い人ほど、高い保険料を支払うことになります。
それは一般的な健康保険の場合、年収の一定割合を保険料として支払うことになるためです。
健康保険料のお支払いについて、多くの場合は、毎月給与から天引きされます。
国民健康保険の保険料
保険料の金額は、加入者の所得によって決定されます。
また、世帯の人数によっても保険料が異なります。
一般的に、所得が高いほど保険料も高くなり、世帯の人数が多いほど保険料が割安になる傾向があります。
国民健康保険料のお支払いについては、以下の方法が一般的です。
- 郵便振替:自治体から指定された銀行口座より、毎月の保険料が自動的に引き落とされます。
- 窓口での現金支払い:自治体の役所や区役所または指定された支払い窓口にて、現金で保険料を支払うことができます。
- 銀行振り込み:毎月の保険料を、指定された銀行口座に手動で振り込む方法です。
これらの支払い方法は、自治体によって異なる場合があります。
詳細については、所属する自治体の役所や国民健康保険組合に問い合わせて確認してください。
独立時の年金保険を理解しよう

創業に必要な“資金調達”の専門サポートを受ける
CEOパートナー
年金保険は、老後の生活を支える基盤を築くことができる保険です。
年金保険には、「国民健康保険」と「厚生年金保険」の2つのタイプがあります。
それぞれの特徴や違い、加入条件、保険料について理解しましょう。
国民年金保険と厚生年金保険の違い
国民年金保険は、すべての日本国民が加入する基本的な年金制度です。
一方、厚生年金保険は、会社員や公務員など特定の職業に就いている人が加入する年金制度で、給与に応じた年金を受け取ることができます。
加入条件
国民年金保険に加入するためには、日本国籍または永住者であることが必要です。
また、20歳以上60歳未満のすべての方が対象となります。
一方、厚生年金保険への加入は、会社員や一部の公務員が雇用される際に自動的に加入されます。
保険料
国民年金の保険料は、全国一律の額が設定されていますが、支払い能力に応じた減免制度も存在します。
厚生年金保険の保険料は、収入に応じて異なります。
雇用者と使用者が折半で支払うシステムになっており、毎月給与から天引きされて支払われています。
独立時の労働保険を理解しよう

創業に必要な“資金調達”の専門サポートを受ける
CEOパートナー
労働保険とは、雇用保険と労災保険をまとめて呼ぶ総称です。
雇用形態に関わらず、一人でも労働者を雇っている事業は、強制的に適用となります。
「雇用保険」「労災保険」それぞれに特徴や違いがありますので、そちらの解説と合わせて、加入条件、保険料について述べていきましょう。
雇用保険と労災保険の違い
「雇用保険」は労働者が失業・休業をした際に、国から給付金が出たり、再就職の支援が出たりする公的保険制度です。
一方の「労災保険」とは「労働者災害補償保険」が正式名称で、その名の通り、業務や通勤中に起こった傷病などに対して行われる保険の制度です。
労災保険は原則として、事業主の負担となります。
加入条件
「雇用保険」の加入条件は、従業員を一人でも雇用する事業であれば、必ず適用となります。
主に下記条件を満たす労働者が対象です。雇用形態は問いません。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用見込みがある
一方の「労災保険」は、一人でも従業員の雇用がある場合、規模に関わらず加入が必要です。
ただし労働者が常時5人未満の場合は「暫定任意適用事業所」として、加入は任意となります。
労災保険には「特別加入制度」というものも設けられており、本来は労働者に行う制度であるところ、次に当てはまる場合は任意加入が認められます。
- 中小事業主等
- 一人親方その他の自営業者
- 特定作業従事者
- 海外派遣者
災害の発生状況などを考慮して、保護の必要があると判断された場合は任意加入できるのです。
保険料
「雇用保険」の場合は、労働者に対して企業が支払った1年間の賃金総額に対し、雇用保険の保険料率を掛けることで算出します。
雇用保険料率は3種類の事業の種類、負担者は誰か、そして年度によって異なります。
厚生労働省「令和6年度の雇用保険料率」
また、同様に「労災保険」の場合、労働者に対して企業が支払った1年間の賃金総額に対し、労災保険の保険料率を掛けることで算出します。
労災保険料率は、年度や業種によって異なります。
厚生労働省「令和6年労災保険率表」
【形態別】加入できる保険とその手続き
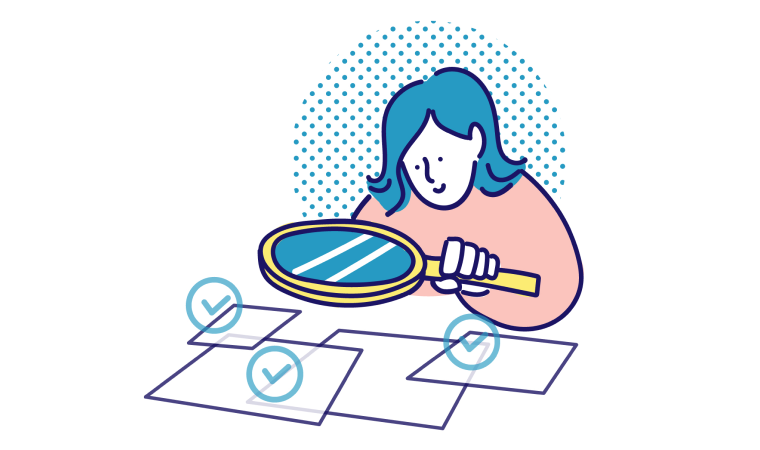
創業に必要な“資金調達”の専門サポートを受ける
CEOパートナー
個人事業主と法人では立場が違うため、保険に加入する方法も異なります。
この章では、個人と法人で加入できる保険の違いと、その手続き方法について解説します。
個人事業主が加入できる保険
個人事業主が加入できる保険には、以下のようなものがあります。
| 保険 | 加入方法 | 手続き |
| 国民年金保険 | 市区町村役場に提出する「国民年金保険料納付書」を用いて手続きを行います。 また、自動的に加入される場合もあります。 | 市区町村役場で必要書類を提出し、保険料を納付します。 |
| 国民健康保険 | 市区町村の健康保険課に直接申し込みます。 | 健康保険課に必要書類を提出し、加入手続きを行います。 |
| 労災保険 | 労働基準監督署に提出する「労働保険料納付書」を用いて手続きを行います。 | 労働基準監督署に必要書類を提出し、加入手続きを行います。 |
個人事業主は、国民健康保険や国民年金保険に加入する以外にも、ご自身の意志で厚生年金保険に加入することも可能ですが、これには特定の条件が必要になる場合があります。
また、労災保険への加入をすることもできます。
労災保険は事業に関連した怪我や病気をカバーすることのできる保険です。
法人が加入できる保険
法人として事業を行う場合、従業員を雇用している場合には健康保険や厚生年金保険への加入が義務付けられます。
法人が加入できる保険には、以下のようなものがあります。
| 保険 | 加入方法 | 手続き |
| 厚生年金保険 | 厚生年金保険事務所に必要書類を提出し、手続きを行います。 | 必要書類を厚生年金保険事務所の窓口に提出するか、年金機構の事務センターに郵送して、手続きを行います。 |
| 労災保険 | 労働基準監督署に必要書類を提出し、手続きを行います。 | 必要書類を労働基準監督署の労災課に提出し、加入手続きを行います。 |
| 雇用保険 | 労働基準監督署に必要書類を提出し、手続きを行います。 | 必要書類を労働基準監督署に提出した後、管轄のハローワークに必要書類の提出を行います。 |
法人と個人とでは、加入できる保険も内容も異なるので注意して加入しましょう。
独立時の社会保険についてQ&A
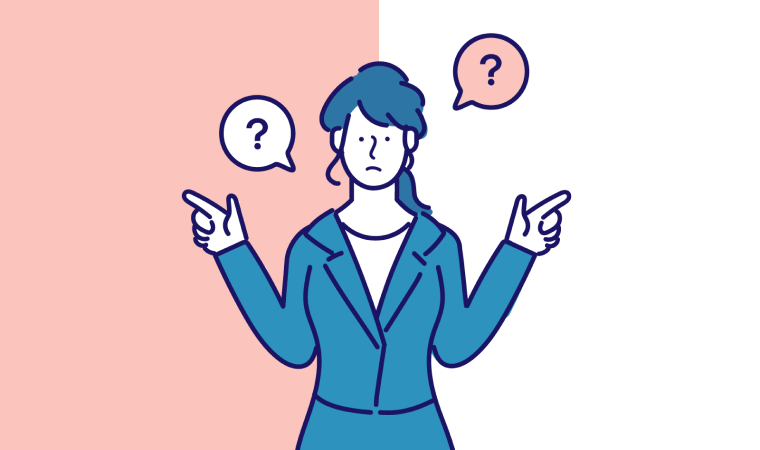
保険未加入だとどうなる?
・医療費の負担:
健康保険に加入していない場合、医療費が全額自己負担となります。
突然の病気やケガで高額な医療費負担が必要になった場合、日常の生活を圧迫する可能性があります。
・年金受給の制限:
年金は老後の生活を支える重要な要素です。
年金保険に加入していない場合は、将来の年金受給額が制限される可能性があります。
・労働災害の不安:
労災保険に加入していない場合、労働災害が発生した際の補償が受けられません。
仕事中のケガや災害による障害があった場合、収入の喪失や医療費の負担が大きくなる可能性があります。
・法的リスク:
一部の保険には、法律で加入が義務付けられているものもあります。
加入義務のある保険に加入しないことは、法的なリスクを伴う場合があります。
加入義務を怠った場合、罰則や違反金の支払いが課される可能性があります。
保険未加入のリスクは個々の状況によって異なりますが、生活や健康、将来の安定を考える上でも、適切な保険に加入することが重要です。
いつまでに加入すればいいの?
独立後は早めに保険に加入することが望ましいです。
具体的な加入時期は個々の状況によって異なりますので、自身の生活状況や保険の種類、加入手続きにかかる時間などを考慮して判断する必要があります。
加入時期には制限もありますので、あらかじめ期限を確認しておくことをオススメします。
一番安い医療保険は?
一番安い医療保険は、個々の状況によって異なります。
一概には言えませんが、国民健康保険は収入に応じた保険料が設定されており、比較的安価で加入できるケースが多いです。
ただし、サービス内容やカバー範囲をよく確認し、自分に合った保険選びをしましょう。
月収20万の社会保険料はいくら?
社会保険料は収入に応じて異なります。
月収20万円の場合、国民年金保険や健康保険などの保険料率を考慮すると、おおよそ月額10,000円から15,000円程度になるでしょう。
ただし、具体的な金額は所得や家族構成などによって異なるため、保険加入後に保険料が確定します。
まとめ
独立する際には様々なリスクに備えるために、保険に加入することが重要です。
特に、医療保険や年金保険の2つは独立後に必須の保険で、医療保険は突然の病気やケガに備え、年金保険は将来の安定した生活を支えるためにも必要です。
また、保険に加入する際には加入条件や保険料などを理解し、自身の状況に合った保険を選ぶことが大切です。
個人事業主や法人としての立場によっても、加入する保険や手続き方法が異なるので、しっかりと準備して適切な手続きを行いましょう。










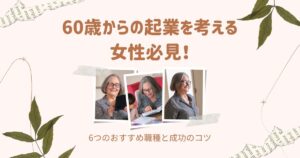

コメント
コメント一覧 (7件)
[…] あわせて読みたい 独立したら加入すべき3つの保険!加入条件と保険料を徹底解説 社会保険にはいくつか種類があり加入時期や加入条件、保険料などそれぞれ異なります。 独立したら […]
[…] あわせて読みたい 独立したら加入すべき3つの保険!加入条件と保険料を徹底解説 社会保険にはいくつか種類があり加入時期や加入条件、保険料などそれぞれ異なります。 独立したら […]
[…] あわせて読みたい 独立したら加入すべき3つの保険!加入条件と保険料を徹底解説 社会保険にはいくつか種類があり加入時期や加入条件、保険料などそれぞれ異なります。 独立したら […]
[…] あわせて読みたい 独立したら加入すべき3つの保険!加入条件と保険料を徹底解説 社会保険にはいくつか種類があり加入時期や加入条件、保険料などそれぞれ異なります。 独立したら […]
[…] あわせて読みたい 独立したら加入すべき3つの保険!加入条件と保険料を徹底解説 社会保険にはいくつか種類があり加入時期や加入条件、保険料などそれぞれ異なります。 独立したら […]
[…] あわせて読みたい 独立したら加入すべき3つの保険!加入条件と保険料を徹底解説 社会保険にはいくつか種類があり加入時期や加入条件、保険料などそれぞれ異なります。 独立したら […]
[…] あわせて読みたい 独立したら加入すべき3つの保険!加入条件と保険料を徹底解説 社会保険にはいくつか種類があり加入時期や加入条件、保険料などそれぞれ異なります。 独立したら […]