夢見た自分の飲食店を開くこと、想像するだけでワクワクしますよね。
でも、実際には「開業のやり方が複雑でどこから手をつけていいかわからない」
「資金はどうやって集めればいいの?」と、不安に思っているかもしれません。
ご安心ください。
あなたのそんな悩みをこの記事でしっかりとサポートします。
この記事を読めば、効果的なビジネスプランの立て方から資金調達のコツ、さらには成功店舗の事例まで、一つ一つ丁寧に解説しています。
夢を実現するための第一歩を、ここから踏み出しましょう。

飲食店開業の流れは6ステップ

飲食店の開業をするためには6つのステップを踏み、開業の方法を定めていく必要があります。
飲食店の業態や提供の仕方によって準備が変わってくるので注意しましょう。
事業のコンセプトは何か
コンセプトをしっかりと決めておくことで、事業計画に一貫性を持たせることができ、メニューや内装なども決めやすくなります。
コンセプトを決める際、もちろん自分のやりたいテーマを考えると思いますが、立地、客層、金額も合わせて考える事が大切です。
「どの場所で、どんな人をターゲットに、どんな料理を提供したいのか?」をまずは紙などに書き出し、自分の構想を練ってみましょう。
業態選択!自分に合った形式発見

業種選択もかなり重要になってきます。コロナ禍の影響で店舗を持たないデリバリーのみの「ゴーストレストラン」も注目を集めました。
野外フェス等の開催も通常通りになり、移動販売も再び人気が高まっています。
もちろん自分の飲食店の実店舗を夢見る人も多いかと思います。
飲食店で開業すると言っても、移動販売、実店舗、デリバリー、間取り店舗等の形式があります。
自分に合った、あなたの開業したい業態を決めるのも戦略ですので、予算や提供スタイルを考えていきましょう!
物件、提供方法を決める
飲食店を開業する際、手続きや資金調達を最初にするイメージかと思いますが、実は物件探しが先になります。
なぜかというと融資を受ける際に際に必要な事業計画書には物件や出店エリアを記入しなければならないからです。
開業の6か月から10か月前に物件探しをするのが目安です。
認可資格所得・届出申請
飲食店を開業する際には店舗完成の10日前までに自分の住む地域の自治体の保健所から「飲食店営業許可書」を取得しなくてはいけません。
提出をして許可がおりるまで2〜3週間かかります。届出の申請は開業前に余裕をもって行いましょう。
施工・備品の準備
施工する前の店舗の図面が出来たらまずは保健所へ持っていき、相談することをおすすめします。
事前に相談しておくことで必要な対応が先にできるので許可書をもらう際の審査がスムーズに進みます。
施工が始まったらお皿や内装の備品、事務用品等の準備に取り掛かりましょう。
開店前の準備
開店前にはコンセプトに合ったメニュー作り、従業員の採用、集客(ポスティングやSNS投稿など)、仕入れ会社の契約などを行います。
開店前に接客やオーダーのロールプレイングをするのも一般的です。
成功する事業計画書の作り方

飲食店を開業する際、銀行や融資機関から資金調達をするためには事業計画書が必要となります。
書類として必要なだけでなく、事業計画を立てることで実際の事業に見通しがたち、ビジョンが明確になるメリットもあります。
事業を成功させるための事業計画書のポイントを紹介しますので参考にしてください。
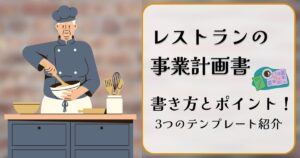
コンセプトは明確に
コンセプトが明確になっていると店の強みがわかりやすく、他の店との差別化が図れます。
また、事業計画書を書くときにはコンセプトを軸に説明が出来るので、自店がどのような飲食店を目指し、どのようなサービスを提供していくかが第三者にわかりやすくなります。
必要な情報と数字を取り入れる
事業計画書には実際の売り上げや人件費等の数字を記載することで事業内容に信頼性が生まれます。
メニューや売り上げもだた想像してなんとなく入力するのではなく、店のコンセプトに合わせた他の競合や、地域性なども加味して入力してください。
日本政策金融公庫では、事業計画書の記入例を見ることが出来るので参考にしてください。
データと事実に基づける
もちろん事業が始まる前なので憶測になってしまうかもしれませんが、あくまでも根拠のある情報をもとにして自分で計算をし、しっかりと説明できるようにしましょう。

見やすさと整合性を重視
事業計画書は長くたくさん書く事がベストなわけではありません。
審査をする際に相手に重点がわかりやすいか、内容に一貫性があるかを確認してください。
理想の物件探しの4つのコツ

飲食店の店舗を作るのであれば、物件探しはとても重要です。
物件探しをしながら立地調査も行い、自分の店のコンセプトと物件の立地、価格帯、客層などが一致しているかを確認しましょう。
物件を探す際にどんなことに注意したらよいか、コツを4つ紹介します。
条件を明確に洗い出す
物件探しの際、まずは物件の場所、家賃など、自分の求める条件を明確にするところから始めます。
求める条件の優先順位を決めておくと重要視するところと妥協するところがわかりやすいですね。
コンセプトの優先度で選ぶ
自分の求めるコンセプトはどのような条件の物件が必要かを考え、譲れない条件があるのであればその条件をクリアする物件を探します。
譲れない物件の条件があるときは立地やエリアを変えながら柔軟に探すことも大切です。
不動産屋さんに根回しする
物件探しは自分で地域を歩き回って空き物件を探したり、Webサイトを活用したり出来ますが、不動産屋さんに自分の求める条件を相談し、いい物件が見つかるまで情報交換をし続けるのも有効です。
妥協することも忘れずに
理想の物件を見つけることは簡単ではありません。
一般的には一階の人通りが多い物件が人気ですが、現在は”隠れ家風”や”見つけづらい店”というコンセプトでもSNSで話題性があり、流行る可能性もあります。
物件が決まらないと事業計画書が進められないので妥協もしつつ、物件探しを進めましょう。
開業に必要な資格と届出
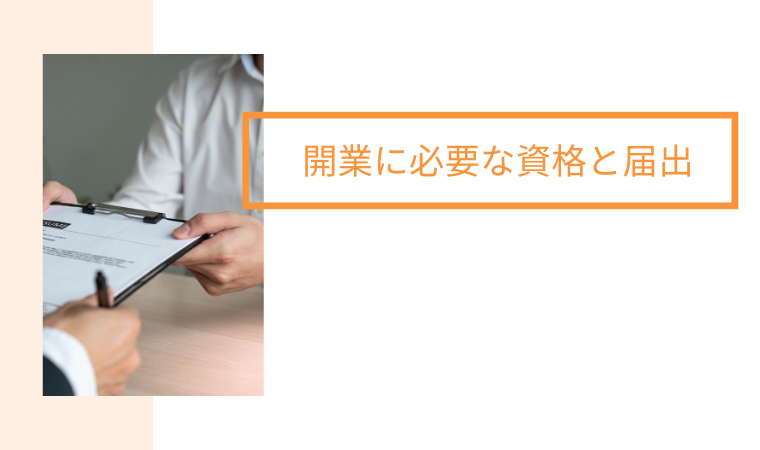
開業には必ず必要な資格や、その他自分の業態に合わせて申請すべき届出があります。
これらは開業前に必ず確認し、抜かりないようにしましょう。
必須資格とその取得方法(食品衛生責任者・防火管理者)
飲食店に必要な資格として食品衛生責任者と防火管理者の二つの資格があります。
自分一人で開業する際、二つの資格を自身で取得し、兼任することは問題ありません。
これらの資格の内容と習得方法を紹介します。
<食品衛生責任者>
食品衛生管理者は店舗の食品を管理している人を指します。食中毒や食品表示などを正しく理解し、食品を扱う際に安全に提供できるようにする必要があるためです。大体10000円程度で受講できます。
現在、オンラインでも受講が可能です。日本食品衛生協会のサイトに詳しく書いてありますので参考にしてください。
<防火管理者>
防火管理者は、火災による被害が起こらないように対策を行う責任者を指します。店舗の席が30席以上の店舗のみ必要な資格です。大体7000〜8000円程度で受講できます。
条件により取得する資格が変わるので、申し込みの際に自分の店舗の最寄りの消防署に相談することをおすすめします。
開業に向けた届出手続き
飲食店を開業するにあたり、店の大きさや業態などによって必要になる届け出があります。
自身の飲食店で何をどう提供するのかを1つずつ確認し、必要な申請・免許・届出を提出しましょう!
以下の表には、飲食店で多い申請や届出の一部になります。
店舗スタイルや提供するものによって、必要な届出は変わってきますので、同業者に確認したり、多くの店舗をサポートしてきた税理士に相談することをおすすめします。
| 飲食店営業許可申請 | 全店舗が対象。保健所に届出。定期的に更新が必要。 |
| 防火管理者選任届 | 建物の収容人数30以上の店舗。消防署に届出。 防火管理資格を所持している管理者のなかから選任。 |
| 防火対象設備使用開始届 | 建物や建物一部を新たに使用する場合に必要。消防署に届出。 |
| 火を使用する設備等の設置届 | 火を使用する設備の場合、必須。消防署に提出。 |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書 | 深夜12時以降にお酒を提供する場合、必要。警察署に届出。 |
| 風俗営業許可申請 | お客さんと接待、ダンス、遊技等が行われるサービス店舗。 |
| 個人事業の開廃業等届出書 | 個人事業主として開業するなら、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出」。 都道府県税事務所に「個人事業税の事業開始等申告書」 |
| 菓子製造業許可申請 | ケーキやパンをテイクアウトで販売する場合、必須。保健所に届出。 |
| 酒類販売業免許 | 店内でお酒の提供・販売をする場合、必要。税務署に届出。 |
資金調達と費用を賢く抑える方法

飲食店はどうしても大きな初期費用がかかってしまうので、資金調達が必要になります。
資金調達の方法と、費用を抑える事が出来る方法や補助金について紹介します。
開業費用は最低300万円程度
飲食店の開業費は一般的に1000万円程度と言われていますが、居抜きの物件をそのまま再利用したり、備品を中古品で揃えたりなど、開業費用を抑える方法もあります。
それでも最低300万円はかかることは想定し、資金調達をしましょう。
見積もりを出して開業費用算出
事業計画を立てる前にまずは自分の開きたい飲食店で何にどの程度費用がかかるのか算出してみましょう。
まずは自分の理想の飲食店を開くための見積もりを出してから、どこを妥協して費用を削るか、他に方法があるかを検討し、何度も見直して最終的にいくら必要になるかを考えます。
融資制度・補助金制度を活用
開業時に不安な資金調達ですが、実は国や自治体から受けることが出来る融資制度や補助金制度があります。
日本政策金融公庫では開業資金の融資を低金利、無担保で融資を受けることが出来ます。リスクが低く、自己資金が少なくても利用できる融資制度です。
また、予約やシフト管理などにITを導入して事業を効率化したい場合にはIT導入補助金がもらえます。
そのほかにも新規開業を支援してくれる仕組みは多くありますが、支援を受けるためには審査が必要になります。
どうすれば審査を通過できるか、必要な書類は何かなど、困ったときには経験のある税理士事務所と一緒に開業を進める選択肢もあります。
CEOパートナーでは、自分の開業スタイルに合った税理士事務所とのマッチングをしてくれます。
開業支援を有効に使うためにも、プロに相談してみましょう。
売上を伸ばす運営戦略! 繁盛店の秘訣
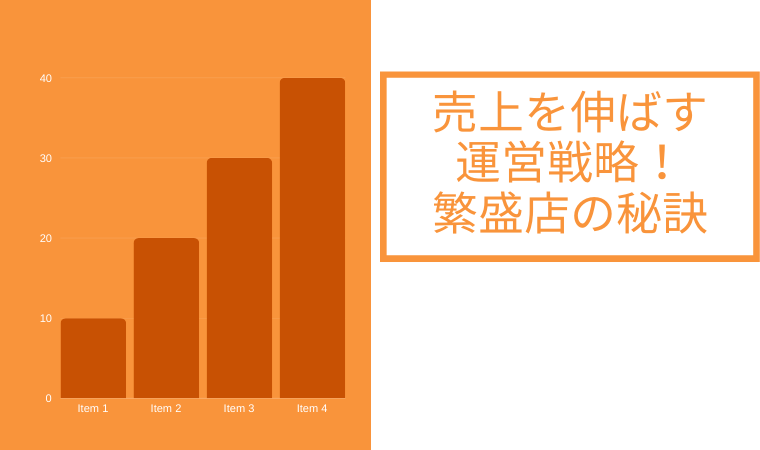
飲食店は競合が多い業界です。
しかし、経営戦略を立てることで、自分の店にたくさんのお客さんがくるのも夢ではありません!
どんな経営戦略があるのかをいくつか紹介します。
売上アップは客数と客単価
売り上げを上げたいのであれば、集客に集中してとにかく客数を上げる、メニューやサービスを見直して客単価を上げるなどの方法が一般的です。
例えば
- 流行を敏感に取り入れる
- 売り上げデータから客層や人気メニューについて分析する
など、様々な角度から売り上げアップを狙ってみましょう。
コスト削減で収益を上げる
飲食店では様々なコストがかかりますが、コスト削減を目指すことで収支に大きく影響します。
- モバイルオーダーを取り入れて人件費を削減
- 省エネ機器を導入して光熱費削減
など、小さなこともコツコツと節約できるよう工夫する必要があります。
常連客を増やす戦略
常連客を増やすことは店の安定した売り上げのためにとても重要なポイントです。
- ポイントカードや次回割引カードの導入
- 常連客の特徴や好みのメニューをスタッフで共有し、接客で親近感を持ってもらう
など、「また来よう」と思えるようなリピーター獲得戦略と、「また来てよかった」と思える常連客のケアを大切にしましょう。
まとめ

飲食店の廃業率は、開業から3年以内に70%、5年以内で80%と言われています。
飲食店の流行は変化しやすく、社会情勢に影響されやすいので簡単な業界ではありませんが、それでも熱意をもって自分の飲食店を開業するからには毎日アップデートしながら愛される店作りを目指しましょう。
開業時の資金調達や営業の不安があるのであればCEOパートナーを利用し、タッグを組める税理士事務所を探して見てください。
飲食店成功までの道のりも楽しみながら、理想の自分の飲食店を作ってくださいね。










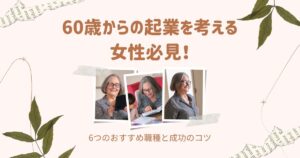

コメント
コメント一覧 (11件)
[…] あわせて読みたい 0から始める飲食店独立!開業資金と具体的6ステップ解説 夢の自分の飲食店!飲食店の独立は簡単ですが、やるなら成功させたいですよね。そこで飲食店開業の流れ […]
[…] あわせて読みたい 0から始める飲食店独立!開業資金と具体的6ステップ解説 夢の自分の飲食店!飲食店の独立は簡単ですが、やるなら成功させたいですよね。そこで飲食店開業の流れ […]
[…] あわせて読みたい 0から始める飲食店独立!開業資金と具体的6ステップ解説 夢の自分の飲食店!飲食店の独立は簡単ですが、やるなら成功させたいですよね。そこで飲食店開業の流れ […]
[…] あわせて読みたい 0から始める飲食店独立!開業資金と具体的6ステップ解説 夢の自分の飲食店!飲食店の独立は簡単ですが、やるなら成功させたいですよね。そこで飲食店開業の流れ […]
[…] あわせて読みたい 0から始める飲食店独立!開業資金と具体的6ステップ解説 夢の自分の飲食店!飲食店の独立は簡単ですが、やるなら成功させたいですよね。そこで飲食店開業の流れ […]
[…] あわせて読みたい 0から始める飲食店独立!開業資金と具体的6ステップ解説 夢の自分の飲食店!飲食店の独立は簡単ですが、やるなら成功させたいですよね。そこで飲食店開業の流れ […]
[…] あわせて読みたい 0から始める飲食店独立!開業資金と具体的6ステップ解説 夢の自分の飲食店!飲食店の独立は簡単ですが、やるなら成功させたいですよね。そこで飲食店開業の流れ […]
[…] あわせて読みたい 0から始める飲食店独立!開業資金と具体的6ステップ解説 夢の自分の飲食店!飲食店の独立は簡単ですが、やるなら成功させたいですよね。そこで飲食店開業の流れ […]
[…] あわせて読みたい 0から始める飲食店独立!開業資金と具体的6ステップ解説 夢の自分の飲食店!飲食店の独立は簡単ですが、やるなら成功させたいですよね。そこで飲食店開業の流れ […]
[…] あわせて読みたい 0から始める飲食店独立!開業資金と具体的6ステップ解説 夢の自分の飲食店!飲食店の独立は簡単ですが、やるなら成功させたいですよね。そこで飲食店開業の流れ […]
[…] あわせて読みたい 0から始める飲食店独立!開業資金と具体的6ステップ解説 夢の自分の飲食店!飲食店の独立は簡単ですが、やるなら成功させたいですよね。そこで飲食店開業の流れ […]