「患者一人ひとりに寄り添った医療を提供する病院を作りたい。」その夢を叶えるために、病院開業を目指す医師が増えています。
この記事では、開業のための手続きと具体的な費用の解説、病院開業に利用できる資金調達について詳しく解説します。
開業の夢を叶えるための第一歩を、ここから踏み出しましょう。
病院を開業するまでの流れ

まずは、実際に病院を開業するまでの流れから確認していきましょう。
個人事業主か、医療法人かを選ぶ
病院を開業する際は、個人事業主として開業するか、医療法人を設立するかの選択が必要です。
個人事業主として開業する場合は、税務や財務面での管理が簡易というメリットがありますが、リスク負担はすべて自分自身にかかります。
一方、医療法人の場合は、都道府県知事の認可が必要です。
医療法人は非営利性を求められるうえ、剰余金の配当が禁止されています。
ただ、分院や事業承継がしやすく、社会的信用性も高い点は大きなメリットです。
事業規模や将来の展望などをきちんと考慮しながら選択しましょう。
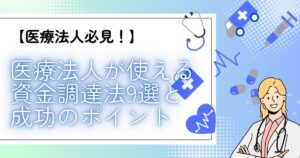
事業計画を立てる
病院開業に向けて重要となるのは、事業計画を立てることです。
提供する医療サービスや診療科目、地域の需要に基づいた具体的な戦略を策定します。
また、開業後の収益予測や支出計画、必要な設備やスタッフの配置といった細かな情報も事業計画に記載します。
事業計画は、銀行からの融資を受ける際にも必要な準備です。
完成度が融資の成否を分けるので、丁寧に作りこみましょう。

必要な許可を取得する
病院を開業するには、各種許可や届出を適切に行う必要があります。
保健所への開業届の提出や、各専門分野に応じた許可を取得しなければなりません。
ほかにも、防火管理者や厚生局への保険医療機関指定申請等が必要になります。
これらの手続きを怠ると、開業後に行政指導や営業停止のリスクがあるためご注意ください。
開業資金を調達する
病院を開業するには多額の資金が必要です。
資金調達方法としては、自己資金、銀行からの融資、日本政策金融公庫の創業融資、または医療機器リースなどが考えられます。
まずは、事業計画書をもとに金融機関から融資を受けることを検討しましょう。
また、開業資金の調達には、投資家や医療法人のパートナーを募る方法もあります。
必要な資金額を正確に算出し、無理なく返済できる計画を立てることが重要です。
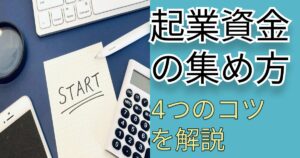
物件を探す・契約する
病院開業において、立地選びは非常に重要です。
都市部では競争が激しくなるため、周辺地域の人口や競合状況を調査し、最適なエリアを選定します。
物件が決まったら、賃貸契約や購入契約を進める前に、保健所などと事前協議を行い、開業に必要な要件を満たしているか確認しましょう。
契約後は内装や設備工事を行い、診療がスムーズに始められるように準備します。
医療機器や設備を整える
病院を開業するためには、医療機器や設備の整備が不可欠です。
診療科目に応じた機器を選定し、品質やコストを考慮して購入します。
最新の医療機器を導入することで、患者の信頼を得やすくなりますが、一定の初期費用がかかってしまいます。
リースや中古機器の利用も選択肢として検討しておきましょう。
法的手続きを行う
病院を開業するためには、医療法にもとづく法的手続きを適切に行う必要があります。
まずは、医療機関としての開設届を提出し、医師や看護師の資格を持ったスタッフの雇用契約を結びます。
また、医療機器の管理、感染症対策、患者情報の取り扱いに関する法的義務を守ることも必須です。
法的な手続きを怠ると、後々のトラブルや事業停止にもつながるため、くれぐれもご注意ください。
スタッフを雇用する
病院開業にあたり、医師や看護師などの専門スタッフを雇用する必要があります。
必要な人員数やスキルを明確にしたうえで、採用活動を進めましょう。
求人広告の掲載や面接の準備、採用後の研修なども行う必要があります。
よい病院にするためには、スタッフの教育や福利厚生制度の整備も重要なポイントです。
患者へのサービス品質の向上はもちろん、スタッフが働きやすい環境を整えることも求められます。
集客準備をする
病院を長く運営するために必要なことは集客です。
開業前からマーケティングを開始し、地域に向けた宣伝活動やウェブサイトの作成を行いましょう。
診療案内やスタッフ紹介、患者の声などを載せたサイト作りも、信頼性を高めるために効果的です。
また、地域住民への情報提供を行うことも、知名度向上、患者獲得のためには有効です。
集客活動は早めにスタートさせ、開業後すぐにでも患者を迎えられるようにしましょう。
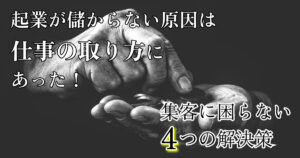
病院の開業費用とその内訳

続いて、病院を開業するために必要な費用とその内訳について解説します。
土地や物件などのテナント費用
病院開業時に最も重要な支出のひとつが、土地や物件にかかる費用です。
特に都市部では土地代が高いため、開業場所の選定は慎重に行う必要があります。
商業地域や住宅地に近い場所に立地することで患者の集客が見込まれる一方、テナント費用も高くなるため、バランスを考慮した選定が重要です。
立地に加えて物件の規模や条件によっても費用は異なるため、長期的に安定した経営ができる場所を選びましょう。
また、初期の賃貸契約時に必要な敷金や保証金も負担となるため、あらかじめ準備が必要です。
内装工事費用
患者にとって快適な空間を提供する内装工事も、病院開業のために必要な費用です。
内装費用は診療科目や物件の状態によって大きく異なります。
元が病院ではない施設だった場合は、電気や水道などの工事も必要になるでしょう。
また、スタッフ、患者の導線を考慮し、双方が快適に過ごせる環境を整える必要があります。
病院の外観や待合室、診察室の内装も重要な要素となるため、専門家に依頼して理想的なデザインを実現しましょう。
医療機器の設置費用
病院開業において、医療機器の設置費用は大きな割合を占めます。
診療科目によって異なりますが、高度な診療を行うための機器(CT、MRI、内視鏡など)は、非常に高額です。
最新の機器を導入するか、リースを選択するかも予算に応じて考慮しなければなりません。
また、メンテナンス費用や修理費用もあるため、開業前に必要な機器のリストを作成し、予算を立てておきましょう。
開業後の運転資金
開業後に発生する人件費や医薬品、医療材料費、光熱費などの運転資金も事前に考慮しておく必要があります。
特に開業初期は、患者数が安定するまで収入が少ない場合があるため、十分な運転資金を準備しておきましょう。
最低でも6ヶ月分の運転資金を確保しておくことで、資金繰りに余裕を持たせることができます。
さらに、スタッフの給与や社会保険料といった費用も予算に組み込んでおかなければなりません。
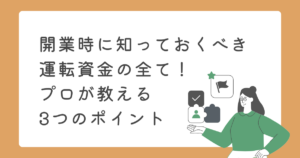
診療科目ごとの目安
病院を開業する際、診療科目に応じて開業費用は大きく異なります。
以下は診療科目ごとに必要とされる大まかな開業資金です。
| 診療科目 | 開業資金目安 |
|---|---|
| 精神科・心療内科 | 1,500万〜3,000万円 |
| 皮膚科 | 2,000万〜6,000万円 |
| 泌尿器科 | 3,000万〜5,000万円 |
| 小児科 | 4,000万〜5,000万円 |
| 耳鼻咽頭科 | 4,000万〜6,000万円 |
| 産婦人科 | 5,000万〜6,000万円 |
| 眼科 | 5,000万〜7,500万円 |
| 内科 | 5,000万〜8,000万円 |
| 整形外科 | 5,000万〜9,000万円 |
| 脳神経内科・外科 | 6,000万〜2億5,000万円 |
得意分野に合わせて診療科目を決める方法もある一方、コストパフォーマンスを重視して開業するのも一つの手段です。
患者数が見込まれる場所や、地域の医療ニーズを調査して診療科目を決めるのも、費用対効果を高めるための重要なポイントとなります。
病院開業に利用できる資金調達

では、病院開業を行うにはどのような資金調達方法があるのでしょうか。
以下9個が候補となります。
日本政策金融公庫の創業融資
まずは、中小企業や小規模事業者への資金提供を主に行っている日本政策金融公庫の創業融資がおすすめです。
低金利かつ政府系金融機関のため、安心して融資を受けられます。
さらに、返済期間も長期にわたるため、開業医にとっては魅力的な選択肢です。
新規開業資金を活用すると、最大7,200万円の融資を受けられます。
開業には大きな資金が必要となるため、ぜひ利用したい創業融資です。
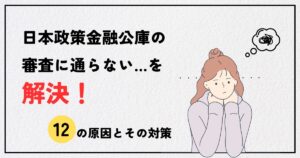
金融機関の融資
病院開業に必要な資金を調達するためには、民間の金融機関から融資を受ける方法もあります。
日本政策金融公庫に比べると金利が若干高く、融資条件も厳しくなるものの、信用があれば比較的短期間で融資を受けられる場合もあります。
金融機関からの融資を受けるには、きちんとした事業計画と高い返済能力を証明しなければなりません。
なるべく多くの自己資金を持っていることで大きなアピールとなるので、事前に集めておきましょう。
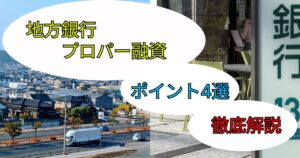
医師会・地方自治体の融資
医師会や地方自治体は、地域医療の発展を目的として、開業医への支援を行っています。
医師会では、設備資金や運転資金として必要な開業支援ローンを用意しているためおすすめです。
ただし、医師会への加入が必須となります。
地方自治体からの融資は「制度融資」と呼ばれるもので、地元の金融機関や信用保証会社と連携して融資を行います。
信用保証料を支払うことで、金利が優遇される点がメリットです。
まずは、開業地にある医師信用組合に相談してみましょう。
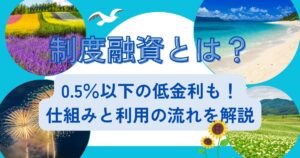
福祉医療機構やリース企業
福祉医療機構やリース企業からの支援も、病院開業において重要な資金調達手段となります。
設立する病院が無床診療所の場合、福祉医療機構で融資を受けるには、開業場所が「診療所不足地域」でなければなりません。
リース企業の場合は、融資と合わせて医療機器のリースが可能です。
機器購入をしなくてよいため初期投資を抑えることができ、運転資金に余裕を持たせることにつながります。
創業補助金
創業補助金は、開業にかかる初期費用を支援するために、政府や自治体から提供される資金です。
病院開業時の医療機器の購入費用や、内装工事に対して補助金が支給されることがあります。
申請には、支払いが確認できるように証拠書類がなければなりません。
補助限度額は200万円で、一定の利益が出た場合は返還義務が生じる場合もあります。
事業承継・引継ぎ補助金
事業承継・引継ぎ補助金は、既存の病院や診療所を引き継ぐ際に活用できる支援金です。
以下の2種類に分けられます。
- 後継者承継支援型
事業を引き継いだ際に支給される補助金です。
| 補助率 | 補助上限金額 |
|---|---|
| 1/2 | 225万円 |
| 2/3 | 330万円 |
- 事業再編・事業統合支援型
企業を統合、再編成する際に受給できる補助金です。
| 補助率 | 補助上限金額 |
|---|---|
| 1/2 | 450万円 |
| 2/3 | 600万円 |
IT導入補助金
IT導入補助金は、病院や診療所がIT化を進めるために活用できる補助金です。
医療業務の効率化や電子カルテの導入、診療支援システムの導入にかかる費用の一部を補助します。
患者の管理やデータ分析など業務のデジタル化を進めることで、病院の運営がスムーズになるためおすすめです。
創業間もない事業者も利用できる通常枠の補助率、補助額は以下の通りです。
- 補助率:1/2以内 ※3カ月の間地域別最低賃⾦の+50円以内で雇⽤している従業員が全体の30%いる場合は2/3以内
- 補助上限金額:5万円~450万円

医療施設等施設設備費補助金
医療施設等施設設備費補助金は、特にへき地や過疎地域の医療施設に対して、設備の充実を目的に支給される補助金です。
クリニックや病院を開業する際、診療所の改修や設備投資に活用できます。
へき地診療所には1施設あたり100万円が補助され、過疎地域の特定診療所には最大250万円が支給されます。
| 補助率 | 下限額 | |
|---|---|---|
| へき地診療所 | 1/2 | 1か所100万円 |
| 過疎地域等特定診療所 | 1/2 | 1か所250万円※ただし改修の場合は100万円 |
| へき地保健所 | 1/3※沖縄県は1/2 | 1か所166.6万円※ただし沖縄県の場合は250万円 |
| 研修医のための研修施設 | 1/2 | 1か所100万円 |
| 臨床研修病院 | 1/2 | 1か所100万円 |
| へき地医療拠点病院 | 1/2 | 1か所250万円 |
| 医師臨床研修病院研修医環境整備 | 1/3 | |
| 離島等患者宿泊施設施設整備事業 | 1/3 | |
| 産科医療機関施設整備事業 | 1/3 | 1か所66.6万円 |
| 死亡時画像診断システム施設整備 | 1/2 |
※参考:厚生労働省「医療施設等施設整備費補助金交付要綱」
感染拡大防止支援金
感染拡大防止支援金は、新型コロナウイルス感染症対策として、医療機関に提供される補助金です。
病院や診療所が感染拡大を防止するために行う衛生管理や設備の改修、従業員の感染対策を強化するための費用に対して支援されます。
受取額は以下の通りです。
- 無床診療所:100万円
- 有床診療所:200万円
感染拡大防止措置が適切に取られていることをアピールすることで、地域社会や患者からの信頼にもつながります。
病院開業のサポートは「CEOパートナー」へ
最後に、病院開業のためのおすすめサポートであるCEOパートナーについて紹介します。
\プロの税理士を頼るべき4つの理由をご紹介!/
最適な資金調達をアドバイス
CEOパートナーでは、経営や資金調達に詳しい税理士を紹介するサービスを行っています。
そのため、病院開業のような大きな資金が必要な際にも、適切な調達方法のアドバイスが可能です。
さらに、「○○銀行の▲という制度がおすすめ」「○○が実施している補助金がよい」といった具体的な支援事業も提案してくれます。
イチから探す手間が省けるため、効率的な事業運営にもつながります。
融資の審査通過率アップ
CEOパートナーから紹介される税理士は、融資の際の審査サポートも行っています。
これまで多くの企業の資金調達を支えてきたので、融資審査のポイントも熟知している点が強みです。
金融機関が行う融資の審査は厳しく、実績がなければなかなか通らないことも多いでしょう。
だからこそ、プロに任せれば有利に審査が進められるのです。
何度も審査に申し込む必要もないため、より事業に集中できる環境が作れます。
書類作成や手続きに負担減
紹介される税理士の特徴として、書類作成を代行してくれる点が挙げられます。
融資審査や税金の手続き時においては、さまざまな書類作成や手続きが発生します。
非常に煩雑であり、開業準備に追われている事業者には大きな負担となるでしょう。
適切な書類を漏れなく作成することで、申請がスムーズに進み、開業準備を効率的に進めることが可能になります。
トラブルやリスクも最小限に抑えられるため、健全な経営にもつながります。

まとめ
自分の病院を持つことは、多くの人が夢見ていることかもしれません。
しかし、そのためには多くの必要経費が発生するため事前に診療科目をきちんと選定したり内装工事にどの程度こだわったりするか決める必要があります。
資金調達や開業について困ったことがあれば、CEOパートナーに相談することをおすすめします。
適切な資金調達方法はもちろん、経営アドバイスも行っているため、安定した事業運営をするためのヒントを数多く得られるでしょう。
費用は完全成功報酬型を採用しているため、相談だけなら無料で受け付けています。
病院開業の具体的な構想がある方は、ぜひお話を聞かせてください。
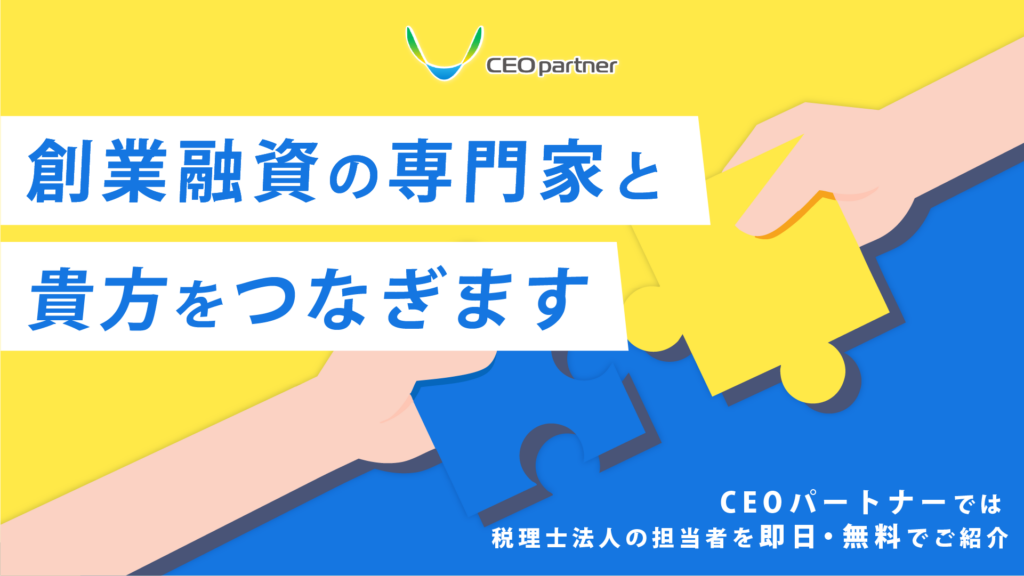
CEOパートナーでは、創業融資をはじめとした資金調達サポートをプロとする税理士法人の担当者を、即日・無料でご紹介しております。
事業計画書の作成代行や面談対策をはじめ、融資だけでなく助成金や補助金の情報提供・お申込みサポートを行っています。
創業後も顧問税理士として頼ることが可能ですので、ぜひお気軽に無料問い合わせをご活用ください。
\相談してから融資を考えてもOK!/

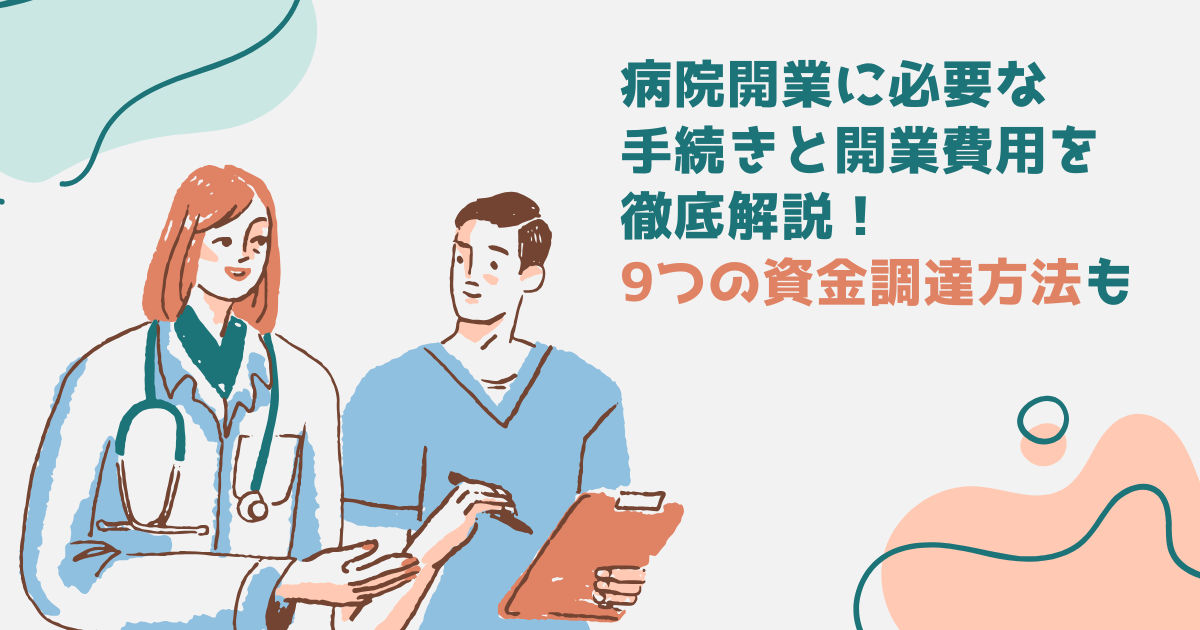
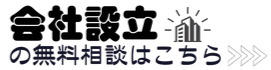








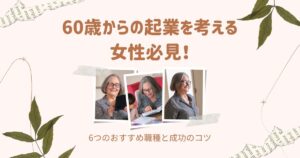

コメント