個人事業主が最短30分で資金調達するなら!
labol(ラボル)個人事業主として開業予定だけど、個人事業主の特権とも言える、自身の裁量で経費計上できる利点を活かして開業費を賢く申告したい!と考える方も少なくないはず。
果たして開業準備に使ったお金のうち、いつまでの分を開業費として申告していいのかは、大いに気になる部分ですよね。
今回は開業費として個人事業主が申告できるのはいつまでの分なのかをメインに、開業費はいつまで償却可能なのか、さらに償却するときの具体例や節税につながる4つのポイントまで、個人事業主のみなさんにとって役立つこと間違いなしな情報をお伝えしていきます。
ただし開業費のことで迷ったら、専門家に相談することが一番確実とも言えます。
我々が開業サポートとしておすすめしている「CEOパートナー」という税理士によるコンサルサービスも、併せてぜひチェックしてみてくださいね。
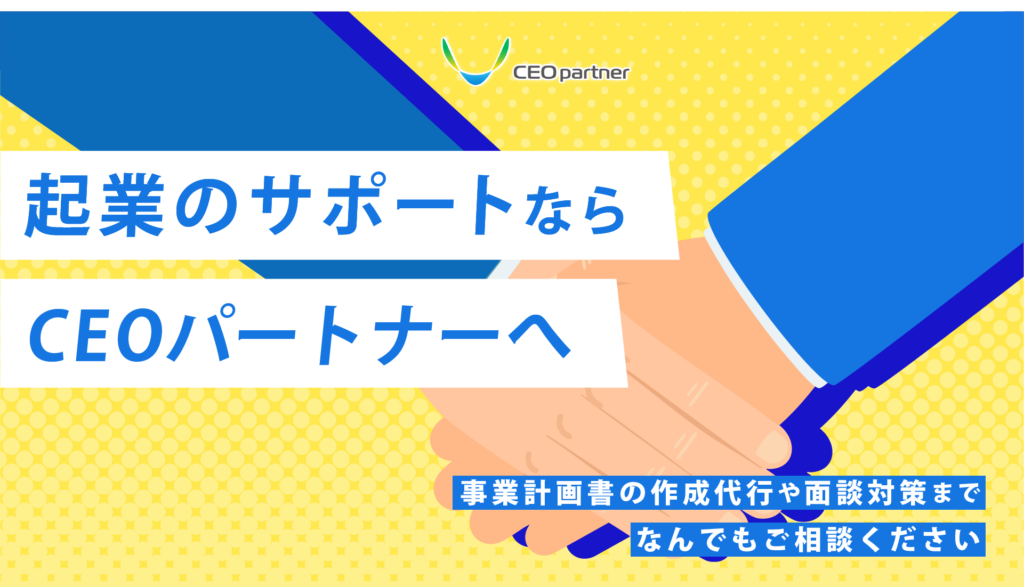
CEOパートナーでは、創業融資をはじめとした資金調達サポートをプロとする税理士法人の担当者を、即日・無料でご紹介しております。
事業計画書の作成代行や面談対策をはじめ、融資だけでなく助成金や補助金の情報提供・お申込みサポートを行っています。
創業後も顧問税理士として頼ることが可能ですので、ぜひお気軽に無料問い合わせをご活用ください。
\相談してから融資を考えてもOK!/
開業費として個人事業主が申告できるのはいつまで?

開業費は、事業で使用するPC・情報機器の購入費、市場調査費やセミナーへの参加費用など開業のための必要費用にはおおむね使用することが可能です。
では、個人事業主が開業費を申告できる期限はいつまでなのか解説していきます。
なかには例外などもあるので、きちんと理解しておくようにしましょう。
開業費については税理士が詳しいので、一人で解決できなければ適宜頼ることで業務効率が上がります。
\プロの税理士を頼るべき4つの理由をご紹介!/
開業日までの支出ならすべて対象
結論から申し上げますと、開業費を計上する期限は法律で定められていないので、いつでも可能です。
事業を始めるにあたって必要と思われる費用と判断されれば、どれだけさかのぼっても開業費として認められます。
重要なのはその出費が開業のために使用されているかどうかなので、きちんと根拠が示せるようにも領収書や明細書を残しておくことが重要です。
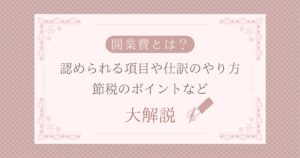
一般的にさかのぼれるのは半年~1年前
とはいえ、10年も前のものが開業費として認められるケースは多くはないでしょう。
事業を始めるための備品と主張しても、その間は別のことに使うなどしている可能性を疑われても仕方ありません。
そのため、開業費として認められるおおよその目安としては開業前の半年から1年前までが妥当なラインとされています。
この期間を越えてしまうと、審査の目も厳しくなるかもしれません。
法人と比べ制限が少ないのがポイント
個人事業主が開業費として申請する際、法人よりも認められる範囲が広いというメリットがあります。
法人の場合は、「特別に支出する費用」と限定されている一方で、個人事業主は経常的に発生する費用でも開業費にすることができるからです。
以下にその例を挙げていきますので、参考にしてください。
- 広告宣伝費
- 市場調査費用
- 研修費用
- その他特別に支出した費用
- 広告宣伝費
- 市場調査費用
- 研修費用
- 通信費用
- 打ち合わせ費用
- PC購入費用
- 家賃
- 水道光熱費
家賃や光熱費も認められる個人事業主に比べて、法人の場合は特別費用ではないため認められません。
大きな違いなので、覚えておくと良いでしょう。
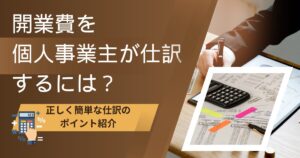
開業費を個人事業主が償却できるのはいつまで?

実は開業費は、繰延資産という資産科目で償却が可能です。
それは、開業前の準備費用が以降の年度にも影響するためという考え方があるからです。
償却とは、収益に貢献した資産を費用化することをいいます。
そのため、開業費は以降の年も毎年少しずつ経費にできるので節税にもなるのです。
個人事業主の開業費と言っても定義の難しい部分があり、人によっても異なりますので、開業前から税理士を頼ってスムーズに手続きを進めていくことをおすすめしています。
\プロの税理士を頼るべき4つの理由をご紹介!/
会計上は5年にわたる均等償却
償却方法については、2つの方法があります。
一つ目は5年にわたる均等償却です。
会計上の考え方であり、その名の通り以降5年にわたり同じ金額を償却するというもの。
例えば、総償却額が100,000円だった場合は毎年20,000円ずつの償却をします。
税法上は任意償却でいつまででも可能
続いては、任意償却という方法です。
こちらは税法上での考え方で、償却期間や金額を自由に決められるというもの。
極端にいえば、最初の年に全額償却することや一円も償却しないということも可能です。
そのため、売上が大きい年はその分多めに償却したり売上が低い年は少なめにしたりということもできます。
節税効果も大きいので、任意償却がおすすめです。
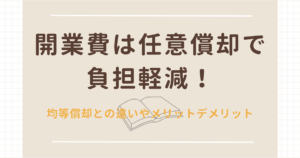
信用を得るには適切な期間設定が必要
とはいえ、何年も償却を続けていると金融機関などから不審に思われてしまう可能性があります。
不安な方は、税務署や税理士に相談してみると良いでしょう。
CEOパートナーでは、開業を目指す方の頼れる相談先として税理士の紹介サービスを行っています。
税務に関しては、税務の専門家である税理士を頼るのが一番です。
誤った確定申告をしてしまえば、やり直しの手間や税金の払い直しほか、規模によっては税務調査が入るかもしれません。
もちろん楽する目的で税理士まで依頼する方もいらっしゃいますが、必要経費と思って専門家に任せてしまうことで、本業に支障をきたすといったリスクも防げます。
相談は無料で、紹介もスピーディーなので一度問い合わせてみてはいかがでしょうか。
【解説】開業費を個人事業主が償却する具体例

続いては、実際に開業費の償却方法について解説します。
仕訳記入例も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
経費でなく「繰延資産」として計上
まず、開業費は経費ではなく繰延資産として計上します。
貸借対照表の資産の部に記載しましょう。
資産の部には流動資産と固定資産がありますが、繰延資産はどちらにも該当しないという点に注意してください。

帳簿の記入先は「仕訳帳」と「減価償却資産台帳」
先に述べたように、開業費は資産科目に該当するため仕訳帳に記入しなければなりません。
さらに、開業費が10万円を超えた場合には減価償却資産台帳に記帳することも義務付けられています。
仕訳帳だけ記入して減価償却資産台帳は忘れてしまうことが多いので、忘れないようにしましょう。

開業日の仕訳記入例
一般的に、開業費については開業日に仕訳をします。
その記入例がこちらです。
<2024年6月1日開業>
- 2024年2月に事業用の事務所に敷金10万円、3か月分の家賃30万円を支払った。
- 2024年5月に、開業セミナー代として1万円を支払った。
- 2024年5月に、PCや備品などを20万円で購入した。
| 借方 | 貸方 | |||
| 6/1 | 敷金(資産) 長期前払費用(資産) | 100,000 300,000 | 元入金 | 400,000 |
| 6/1 | 開業費(資産) | 10,000 | 元入金 | 10,000 |
| 6/1 | 備品(資産) | 200,000 | 元入金 | 200,000 |

確定申告時の仕訳記入例
続いては、確定申告をした際の仕訳の記入例です。
上記の例を引き継いで行います。
| 借方 | 貸方 | |||
| 12/31 | 開業費償却 | 100,000 | 開業費 | 100,000 |
合計の償却額は610,000円ですが、今回は任意償却として100,000円としました。
残りの510,000円を次年度以降に繰り越して償却します。
以上が、開業費を償却する際の流れです。
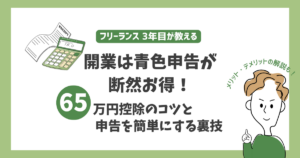
開業費を個人事業主が節税につなげる4つのポイント

何度かお伝えしていますが、開業費は上手に活用すれば節税効果をもたらしてくれます。
しかし、そのためにはいくつかのポイントが存在します。
以下で紹介するポイントを抑えつつ、適切に節税を行いましょう。
領収書は必ず取得・保管する
こちらもすでにお伝えしていますが、開業費として計上した費用の領収書や明細書などは必ず取得・保管しておいてください。
万が一手元にない場合は、費用として計上するための根拠がなくなってしまいます。
普段領収書などを受け取らない方は、これを機に習慣化しても良いかもしれません。
仕訳帳および減価償却資産台帳へ記帳を怠らない
領収書の保管と同様に大切なのが、仕訳帳と減価償却資産台帳への記帳です。
これがなければ、開業費がいくらなのか分からなくなってしまいます。
また、開業費が10万円を超える場合は減価償却資産台帳に記帳というのも忘れがちなので、気を付けましょう。

任意償却にて償却タイミングをうまく調整する
均等償却と任意償却の2つの方法がありますが、おすすめは任意償却です。
その年の事業収入に応じて、償却費を変えれば大きな節税効果を発揮します。
先々の収入も見越して、上手に調整しましょう。
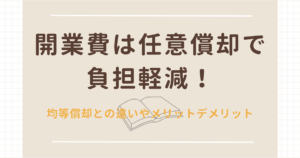
税理士コンサル「CEOパートナー」に相談する
そうはいっても、開業費に関する疑問や不安な点はいくつもあるでしょう。
償却タイミングをどのように分けたら良いのかなどを知りたい場合は、CEOパートナーに相談すればお悩みにピッタリの税理士を紹介してくれるはずです。
開業費以外にも、融資や資金調達についても専門家としての立場からアドバイス可能なので、ぜひ一度お問い合わせください。
「お申し込みフォーム」に必要事項を入力し、「送信する」をクリック。入力から送信までは1~2分程度です。
フォーム送信後、通常ですと5~10分以内にスタッフから電話連絡があります。電話の所要時間は3分程度で、税理士法人の担当者への相談日時を調整します。
※万が一電話に出られなかった場合は、メールアドレス宛に連絡が入ります。
お約束の日時に税理士法人の担当者から直接、電話連絡が入ります。ヒアリングが行われますので、そのままご相談内容をお話ください。担当者よりサポート可能と判断されたら、一人ひとりの状況に沿って次のステップ(事業計画書の作成面談など)が提示されます。
\今すぐお申し込みはこちらから/
\審査に強い理由をもっと知るなら/
 小久保さん
小久保さん融資成功までは一切請求のない「完全成功報酬型」ですのでご安心ください!
まとめ
開業費は上手に活用すれば、節税効果を発揮するため多くの人におすすめです。
そのためには注意しておくべきポイントがあるので事前にチェックしておきましょう。
ただし税務に関しては税理士など、専門家の判断でないと難しい部分も多々ありますので、ぜひCEOパートナーから無料で税理士の紹介を受けることをおすすめします。
ご自身でまとめられた償却したい経費に関して、最終チェックの観点から税理士を頼るといったことも可能です。

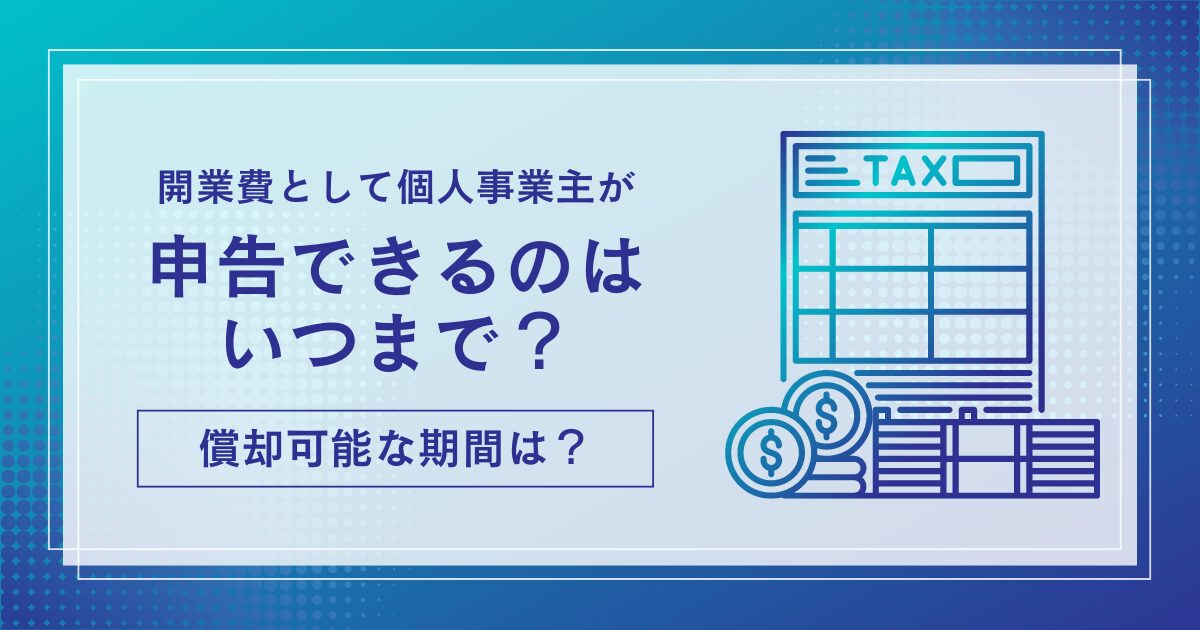








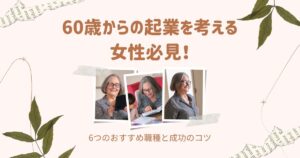

コメント
コメント一覧 (1件)
[…] あわせて読みたい 開業費として個人事業主が申告できるのはいつまで?償却可能な期間は? 開業費としていつまで遡って申告できるのか、償却はいつまで可能なのか、個人事業主が一 […]