「何か新しくビジネスを始めよう!あれ?自分は開業と起業どっちで始めればいいんだ?」
なんて思ったことはありませんか?
そこで本記事では開業を考えている方へ、「開業」と「起業」の違いから、開業のメリット・デメリット、そして開業するための具体的な方法や準備について詳しく解説します。
ビジネスを始めるには多くの疑問や不安がつきものですが、ここで提供する情報を通じて、皆さんの夢を実現するための道筋が見えてくるはずです。
さあ、第一歩を踏み出す準備を始めましょう!
開業と起業は何が違うの?
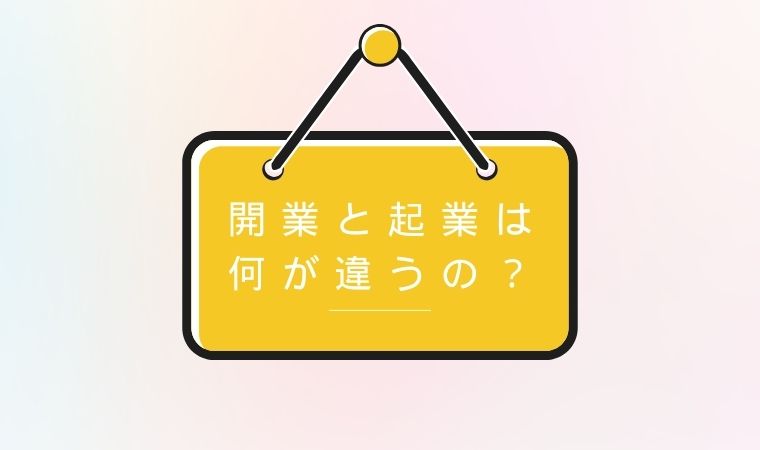
では早速、開業と起業の違いについて解説していきます。
開業と起業、どちらで始めるべきか悩んでいる方は必見です。
開業と起業の違い
それぞれ言葉の成り立ちから見てみると、開業は「事業を開き」、起業は「事業を起こす」という違いがあることが分かります。
いずれも新しく事業を始めるという意味では同じなので、現状ではどのように使い分けるべきか定かになっていません。
そこでそれぞれの言葉を辞書を使って調べてみると、開業が「新しく事業や商売を始めること」であり、起業が「新しく事業を始めること」とありました。
ほとんど同じではありますが、商売という言葉が入っているかどうかに違いがあるようですね。
それぞれの言葉の使い方
このことから分かる通り、開業とは「お店を開いたりして商売を始める時」に使い、起業は「ベンチャー企業やスタートアップ企業をこれから立ち上げるという時」に使うと良いでしょう。
はっきりとした違いがあるというわけではなく、ニュアンスが微妙に異なるという程度ではあるものの、これでご自身がどちらに該当するか認識していただけたのではないでしょうか。
開業の3つのメリット

続いては、開業がもたらす有利な面やメリットをお伝えいたします。
まずは1つ1つ見ていきましょう!
自由に働ける
最初に挙げたいのは、自由に働けるという点です。
開業すれば、働く場所や時間、仕事内容も自分で決めることができます。
近年は会社員であっても、リモートワークやフレックスタイム制度などを用意されている場合もありますが、組織で働く上ではある程度の制限や制約は必要でしょう。
そんな縛りを気にせず働けるのは開業の大きなメリットといえます。
収入UPの可能性も
会社員は、いくら仕事をしても毎月の給与は決まっています。
その点、開業すれば仕事をした分はすべて自分の収入にすることが可能です。
開業した多くの人が、会社員時代よりも多い収入を得ているのはそのためでしょう。
ただし、そのためには確かなスキルや大口のクライアントを持っていることが大事なので、その点は開業前に確認が必要です。
節税ができる
開業すると、商品の仕入れや移動のための交通費、自宅や店舗・オフィスでの光熱費や通信費も経費として計上可能です。
上手に活用することで、節税効果を発揮します。
また、青色申告を選択すると最大65万円の青色申告特別控除も受けることが可能です。
青色申告とは、確定申告の申告方法の一つ。
一定の手続きが必要ではあるものの節税面で有利な制度が数多くあるので、申請しておくことをおすすめします。
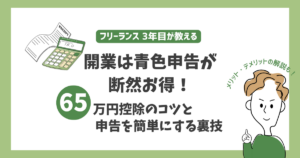
開業する3つのデメリット

一方で、開業した際のデメリットはどのようなものがあるのでしょうか。
そちらも詳しく解説していきます。
収入が不安定に
収入が安定しないというのが最大の懸念点という方も多いでしょう。
会社員であれば基本的に決まった収入が毎月振り込まれてきますが、開業してしまうとそうもいきません。
今月の売上が良くても、来月は一気に下がってしまうということも考えられます。
なるべく収入を安定させられるように、固定のクライアントを付けるなどの施策が必要でしょう。
リスクが常につきまとう
自由度が高い分、すべて自己責任であるということも頭に入れておいてください。
開業したからといって、すべての人が成功するとは限りません。
仕事でのミスや失敗も自分自身で対処しなければなりませんし、売上が思うように伸びないということもあるでしょう。
そういったリスクがあることも考えた上で開業することをおすすめします。
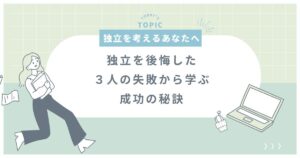
労力がかかる
開業すると、やりたい仕事だけできると思う方もいるかもしれませんが、実はそうはいきません。
会社員時代は、会社の経理担当が対応していた税金や保険料の天引き、仕事を獲得するための営業活動も基本的には自分で行う必要があります。
本業以外の仕事をする場面はどうしても増えてくるので、それ相応の労力が必要ということをあらかじめ理解しておきましょう。
開業する5つのステップ

実際に開業するまでは、いくつかの工程が必要です。
本章では開業するまでの5つのステップをご紹介していきます。
参考記事:年齢なんて関係ない!起業したい30代のための手引き
アイデア出し
まずは開業するにしても、どんな事業を行うのか何をしたいのかというアイデアを具体的に出す必要があります。
誰に、何を、どのように提供するのかをイメージすることで自分が今何をすべきなのかが見えてくるはずです。
事業のコンセプトや競合との差別化ポイントも明確にすることで、具体的な動きも見えてくるでしょう。
事業計画書の作成
次はアイデア出しで見えてきた形をまとめる作業、で事業計画書の作成です。
事業の具体的な内容やターゲット像、必要費用、今後の収支見込みなどをまとめた資料を事業計画書といいます。
頭で考えていたことを実際に書き出すことで、改善点や課題も見つかるのでより現実的な事業計画につながるでしょう。
事業計画書は資金調達にも必要になることもあるので、これを機に書き方を覚えておくと便利です。
資金調達
続いては、前項で少しお話した資金調達についてです。
PC1台あればできる仕事から、店舗を構える必要があるものまで始める事業によって必要な資金は異なります。
自己資金で足りないようなら、金融機関からの融資や国や自治体の補助金・助成金なども活用しなければなりません。
開業手続き
資金も集まったら、開業に必要な手続きに進みます。
開業届は事業を開始してから1ヶ月以内に所轄の税務署に提出しなくてはならないので、忘れないように手続きをしておきましょう。
そこまで難しいものではありませんが、事業開始前後はバタバタと忙しくなりがちなので時間があればなるべく早めに行ってください。
税務署に持参しても郵送で提出してもどちらでも構いません。
開業準備
ここまで来たら、いよいよ開業までカウントダウンが始まります。
必要な道具や備品を取りそろえたり、環境を整えたりと新しい事業がスムーズに始められるような準備を行いましょう。
先にも述べた通り、開業後は忙しくなることが多いのでこの段階できちんとした事前準備をすることが大切です。
開業で苦労する4つのこと

実際に開業するまでの大まかな流れを解説しましたが、すべて思ったように上手くいくことは少ないでしょう。
ここでは開業で苦労することについてご紹介していきます。
苦労することも往々にしてあるので、事前に把握しておいてください。
開業の難関「資金調達」
まずは、そもそも資金が集まらないという点が挙げられます。
エンジニアやライターのようにPC一つでできる仕事であれば良いですが、新しく飲食店や会社を立ち上げるとなると必要資金は必然的に多くなるでしょう。
資金を得るためには、融資や補助金制度という方法が一般的です。
しかし、必ずしも必要資金を得られるという保証はなく、審査や手続きが必要な場合がほとんど。
審査に落ちてしまったり資金調達が間に合わなかったりということもあるので、苦労することも多いでしょう。
一筋縄ではいかない「顧客獲得」
資金も集まって無事に開業できたとしても、顧客獲得に苦労するというパターンもあります。
会社員時代からの顧客を活かして事業を始めるというケースでない限り、ゼロから顧客開拓をしなければなりません。
営業をかけたり、チラシやネット広告などで広報活動をしたりして固定の顧客を獲得する必要があります。
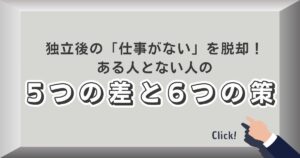
開業したからこその「不安やプレッシャー」
事業が軌道に乗らない時は営業活動などに忙しく、軌道に乗ったら乗ったで本業が忙しくなるなどやることに終わりはないため、常に仕事に追われる日々になる可能性はあります。
家庭がある場合は、収入が落ち込んでしまったら家族を養えないという不安もあるでしょう。
収入が安定した会社員と比べると、プレッシャーや心労とは常に付き合っていく必要があるかもしれません。
やらないとわからない「法的手続きの複雑さ」
開業する際には、開業届や事業開始等申告書の提出等が必要です。
従業員を雇う場合は、社会保険の加入手続きなども行わないといけません。
これらの手続きは非常に複雑で、時間もかかります。
もちろん自身で全て行うことは可能ですが、実際にやってみないとわからない複雑さがあるのがこの法的手続きです。
成功のポイントとしては、社労士や税理士など専門家に相談しながら進めるのが良いでしょう。
気になる開業に関するQ&A

最後に、開業についてのよくある質問とその回答についてご紹介します。
開業したいと思っても悩みや不安が払拭できないため踏み出せないという方もいらっしゃるでしょう。
今回ご紹介するQ&Aでその悩みや不安が少しでも払拭し、一歩を踏み出すきっかけとなれれば幸いです。
開業するタイミングはいつがいい?
開業するタイミングは自由です。
事業を始めたいと思ってきちんとした準備ができたら、いつ始めても構いません。
ただし、開業届はその年度で確定申告をするなら早めに出しておいた方が良いでしょう。
また、始める事業によっては繁忙期があったりするでしょう。
その繁忙期と開業の時期がかぶってしまうと慌ただしくなってしまう可能性があります。
なので繁忙期より少し前に開業、というのが個人的おすすめです。
参考記事:起業の成功率を上げる7つのベストタイミング!人生の転機を掴み取れ
どれぐらいの費用が必要なのかわからない
始める事業によって必要資金は異なるのでこれぐらい必要、と断言するのは難しいです。
急いで開業をしなければならないというケースでなければ、できる限り多くの開業資金を用意しておいてください。
事業開始後は、利益が出る前に設備投資や家賃といった支出が発生します。
そういった時でも対応できるような余剰資金はあるに越したことはありません。
開業を考えているけれど、資金が全くないという場合は融資や補助金制度などをうまく活用しましょう。
アイデアが浮かばない
ぼんやりとこんな事業がやりたい一方で、具体的なアイデアが浮かばないということもあるでしょう。
そんな時は、市場調査をしたり他社の成功事例を参考にしたりしてみると顧客が何を求めているのかが見えてきて具体的な動きにつながるかもしれません。
また、第三者の声を聞くというのも有効な手段です。
起業家コミュニティやワークショップに参加してみると、同じような境遇の方々が集まっています。
話してみると、新しい視点を発見できるかもしれません。
参考記事:起業アイデアは出し方にコツあり!誰でも起業できる4つのアイデア例
始めたはいいものの集客がない
固定の顧客がつくまでは、集客に苦労するでしょう。
地道な営業活動やプロモーションを行っても、なかなか効果が現れないという場合もあるはずです。
その場合もやはり、他の成功例を参考にしたり集客できている人の話に耳を傾けたりしてみてください。
今までの自分にはなかった施策を思いつくきっかけになるかもしれません。
集客に関してより詳しく書かれている記事があるのでこちらも併せて参考にしてみてください。
参考記事:起業が儲からない原因は仕事の取り方にあった!集客に困らない4つの解決策
誰にも相談できない
開業を考えていると困ったことや悩んでいることなどが出てくると思います。
しかし、誰に相談すればいいのかわからないという方が多くいらっしゃるでしょう。
話を聞く人も相談できる人もいないという場合は、商工会議所やよろず支援拠点といった無料で相談を受け付けている機関に相談してみてはいかがでしょうか。
開業に関することであればどんなことでも相談に乗ってくれます。
お金に関することで相談したい、ということであればCEOパートナーをおすすめします。
創業周りに強い税理士を紹介するというサービスを行っており、独立開業に関する相談は大歓迎。
融資を成功させるための書類作成もおまかせできるので、その分本業に集中できるというメリットもあります。
困った時の相談パートナーとして豊富な実績があるので、初めての開業でも適格なアドバイスを受けられるでしょう。
親身になって相談に乗ってくれるので困った時にはぜひ相談してみてください。
\創業融資のプロ・税理士法人を即日紹介/
※フォーム送信後5~10分でお電話を差し上げます
まとめ

開業と起業の違いから、開業についてのメリットや流れ、苦労する点などを解説してきましたがいかがだったでしょうか。
自由度が高くなり、やりたい仕事ができる一方でプレッシャーやリスクも持ち合わせているのが開業です。
法的手続きや税制面で複雑なことも多くて苦労が絶えないという場合は、CEOパートナーに相談してみてください。
ご連絡いただいてから24時間以内にお悩みにピッタリの税理士を紹介してくれます。
あなたの夢をかなえるために不可欠な存在になってくれるはずです。
開業の道は険しいかもしれませんが、それだけの価値がある旅です。
自分を信じて、新たな一歩を踏み出しましょう!

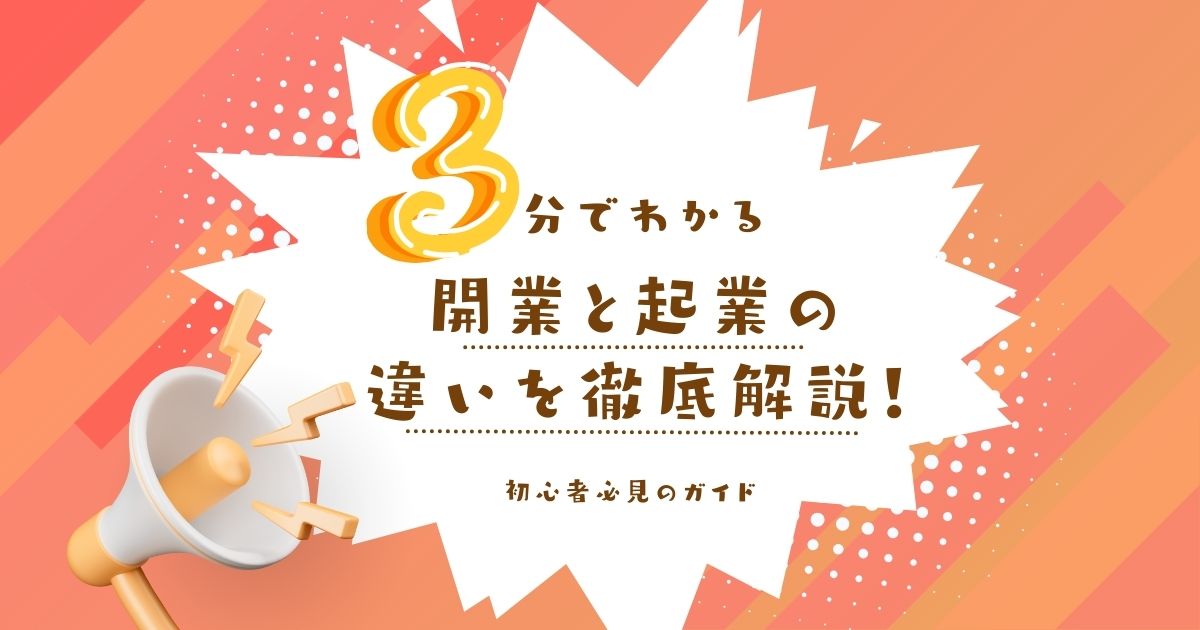







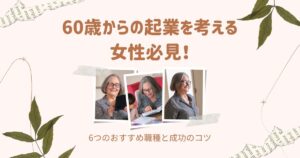

コメント
コメント一覧 (1件)
[…] あわせて読みたい 【3分でわかる】開業と起業の違いを徹底解説!初心者必見のガイド 開業と起業はなにが違うのでしょうか。本記事では開業を考えている方へ、「開業」と「起業」の […]