個人事業主が最短30分で資金調達するなら!
labol(ラボル)開業費はスクール代の計上ができるのでしょうか?
結論、開業に関係するものであれば計上は可能です!
開業前に受講したスクール代なら、「開業費」として計上が可能となります。
ここでは開業費としてスクール代を計上するための正しい知識を解説していくとともに、開業費として認められるもの・認められないものや節税のために知っておきたいポイントなど、豆知識をご紹介していきます。
本記事である程度の知識を身に付けることは可能ですが、開業費の項目は一人ひとり異なるはずですので、多少迷ってしまうことも珍しくはないでしょう。
一人で正しく税務を行なうのはなかなか難しいですので、税理士を頼って効率よく・正しく開業費の管理を行なうことがおすすめです。
開業に詳しい税理士によるサポートサービス「CEOパートナー」について紹介している章もありますので、ぜひ最後まで確認してみてくださいね。
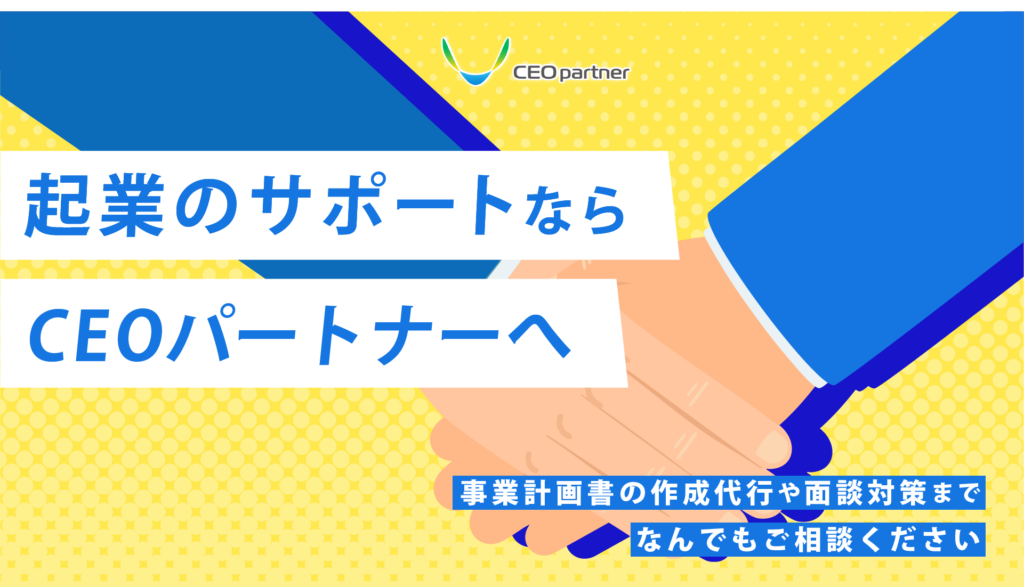
CEOパートナーでは、創業融資をはじめとした資金調達サポートをプロとする税理士法人の担当者を、即日・無料でご紹介しております。
事業計画書の作成代行や面談対策をはじめ、融資だけでなく助成金や補助金の情報提供・お申込みサポートを行っています。
創業後も顧問税理士として頼ることが可能ですので、ぜひお気軽に無料問い合わせをご活用ください。
\相談してから融資を考えてもOK!/
開業費にスクール代は計上できる!

創業に必要な“資金調達”の専門サポートを受ける
CEOパートナー
開業費としてスクール代は計上できるものとなります。
計上可能なスクール代の概念を見ていきましょう。
曖昧な場合は、税務の専門家である税理士を頼ることをおすすめします。
開業にまつわるものならOK
開業にまつわるスクールへ通ったのであれば、開業費として計上は可能になります。
例えば、Webデザイナーとして独立するために通ったWebデザインのスクール代は、開業費として対象になると言えます。
曖昧なものについては、適宜、税理士法人まで相談してみることがおすすめです。
開業前のスクール代も計上可能
開業してから受講が必要になったスクール代はもちろん、開業準備の段階で受講していたスクール代についても経費として計上は可能です。
開業前のスクール代なのか、開業後のスクール代なのかで勘定科目は異なります。
そもそも勘定科目ってなに?という方は、次の記事も併せて確認してみてくださいね。
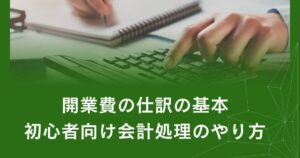
開業前なら勘定科目は「開業費」
開業に必要な準備として、開業前に受講したスクール代であれば勘定科目は「開業費」となります。
一方で、開業後に受講のスクール代に関しては、開業前準備とは無関係のため勘定科目は「研修費」や「教育費」などとなります。
開業費としてスクール代を仕訳する例

創業に必要な“資金調達”の専門サポートを受ける
CEOパートナー
スクール代と一言に言っても、発生のパターンは一つではないでしょう。
ここではよくある例をもとに、開業費として仕訳する方法をご紹介していきます。
実際の仕訳については専門性の高い業務になりますので、仕訳で間違えてペナルティを受けるといった事態にならないためにも、適切に税理士を頼ることをおすすめしています。
スクール代をまとめて支払ったとき
例えば、1回1万円×15回で1コースのスクール代を、まとめて支払ったときの仕訳例を見ていきましょう。
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
| 開業費 | 150,000円 | 元入金 | 150,000円 | 〇/〇(月日) スクール代 |
摘要には支払いが発生した日を記載し、仕訳の登録日付は開業日とします。
また、個人事業主の場合は開業前に事業用の現金がないため、貸方勘定科目には「元入金」と入力します。
元入金とは個人の純資産を指します。
プライベートの資金と事業用資金にやり取りが発生するときに使用します。
開業費は合計で10万円を超えると減価償却の対象となりますので、例として挙げた合計15万円のスクール代は計画的に経費に落とし込んでいきましょう。
支払回数や方法がバラバラなとき
開業前に複数のスクールを受講していて、支払回数や支払方法がバラバラとなることは珍しくないでしょう。
クレジットカードの分割払いを利用していた場合には、金利や手数料などの発生により、スクールからの請求と実際の支払額が異なることもあると考えられます。
ただし仕訳のやり方は上記「スクール代をまとめて支払ったとき」と変わりありません。
領収書さえあれば説明がつきますので、支払方法によって分けて記載しなければならないというわけでもなく、金利や手数料などすべて含んだ総額の記載でよいとされています。
開業費として認められるもの

創業に必要な“資金調達”の専門サポートを受ける
CEOパートナー
開業費は決してスクール代だけにとどまらないはず。
仕訳に失敗しないためにも、開業費として認められるもの・認められないものを把握していきましょう。
個人と法人で計上範囲が異なる
開業費として計上できる範囲が、個人事業主と法人によって異なっています。
個人事業主は広い範囲で開業費として計上することが可能で、開業の数年前であっても開業準備のために使用した費用であれば、開業費として計上が可能です。
一方で法人の場合は、個人事業主と比べ開業費として計上できる範囲は狭いです。
法人の設立後、営業開始までの間に開業準備として特別に支出する費用を開業費として定義づけられています。
そのため、法人設立から開業日までの間、開業のために支払った費用が開業費とされます。
開業費として認められるもの
個人事業主と法人、それぞれの代表的なケースを確認していきましょう。
| 個人事業主 | 法人 |
| 開業にまつわるスクール代 | 研修費 |
| 通信費用 | 広告宣伝費 |
| 打ち合わせ費用 | 名刺制作費 |
| 取引先との食事・手土産 | 印鑑作成費 |
| 開業準備に必要な旅費・ガソリン代 | 市場調査費 |
| 広告宣伝費 | その他特別に支出した費用 |
| パソコン等設備購入費 | |
| 開業に充てる借入金利子 |
こうして見ても、個人事業主の開業費とできる範囲が広いことがわかりますね。
開業費として認められるものについては、次の記事も併せて参考にしてみてください。
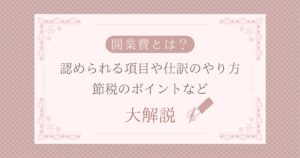
開業費として認められないもの
認められないものについても、個人事業主と法人それぞれのケースで見ていきます。
| 個人事業主 | 法人 |
| 1つで10万円以上するもの | 1つで10万円以上するもの |
| 仕入代金 | 仕入代金 |
| 敷金 | 敷金 |
| 礼金 | 礼金 |
| 事務所の家賃 | |
| 事務所の水道光熱費 |
1つにおいて10万円以上する備品の購入は、固定資産に該当してしまい開業費としては認められません。
また、仕入代金は売上原価となり、開業費として扱うことができません。
10万円以上する開業費の扱いについては、次の記事をぜひご覧ください。

絶対ではない資格取得のスクール代は認められない
注意したいのが、開業にあたって必要があるとは言い難い資格取得などのためのスクール受講に関しては、開業費として計上が認められないことです。
例えばWebデザイナーなど資格がなくとも開業できる職種だったとして、興味本位でファイナンシャルプランナーの資格取得スクールに通った場合、開業とは無関係のために開業費として計上はできません。
一方で医師など、資格や免許がなければそもそも業務が行なえない職種の場合、開業準備うんぬんの問題ではなく、前提として資格や免許を取得していなければ開業したいという考えに至らないという観点から、開業費に計上するのが難しくなります。
ただし詳細については、税理士の意見を聞いて進めていくのが確実です。
開業費を節税するための4つのポイント

創業に必要な“資金調達”の専門サポートを受ける
CEOパートナー
開業費を節税へとつなげるには、4つのポイントを押さえた管理が求められます。
正しく管理することで、税負担を賢く軽減していきましょう。
無駄なく開業費を扱うためには、税理士を頼るのが節税の近道となります。
ただし、確定申告や決算時の一時的な対策だけでは、節税に結び付かせるのは難しいです。
前向きに節税に取り組みたい方は、経営相談から一貫してまずは相談してみることをおすすめします。
領収書を必ず発行してもらう
領収書は必ず発行を依頼しましょう。
スクール代として費用を使ったことの証明がなければ、開業費としての経費計上が難しくなってしまいます。
確定申告や決算時には、領収書と仕訳帳など帳簿が揃っている必要がありますので、徹底しましょう。
償却の方法を理解しておく
合計で10万円を超える開業費は減価償却の対象となります。
減価償却には「任意償却」と「均等償却」の2種類があり、個人事業主と法人で扱うべき種類が異なってきます。
一般的には個人事業主は均等償却を、法人は任意償却を選択する場合が多いですが、個人事業主でも任意償却を選択することはできます。
償却の特徴など、大枠を理解するには次の記事を参考にしてみてください。
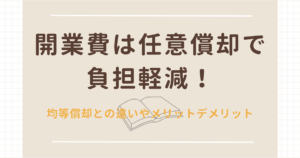
記帳は正確に行なう
開業費の管理には次の記帳が必要になります。
- 仕訳帳
- 減価償却資産台帳
仕訳帳に開業費を記帳するとき、「開業費」は資産の科目に、「開業償却費」は経費の科目に記帳しましょう。
減価償却資産台帳では開業費は繰越資産となり、減価償却・取得・売却などの経緯を正確に記帳する必要があります。
記帳については、一部次の記事も参考にしてみてください。
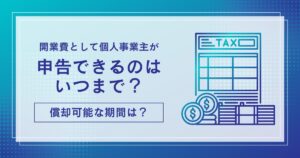
税理士の確認を取るのが一番確実
開業費の経費計上や減価償却に関しては、正直一人ですべてを管理するのは手間がかかる上、専門知識が必要になりますので苦労が伴います。
おすすめは、税理士を頼った管理を行なうことです。
CEOパートナーでは開業に詳しい税理士のみを紹介しており、問い合わせたその日中に税理士まで相談することが可能になります。
税務はもちろん、開業時に必要となることの多い資金調達のサポートにも強みを持っていて、資金調達に成功するまでは何度でも無料で相談できます。
開業前からの相談で、開業費の管理も税理士と確実に行ないましょう。
\プロの税理士を頼るべき4つの理由をご紹介!/
まとめ
開業にまつわるスクール代に関しては、開業費として計上してうまく節税へとつなげていきましょう。
記帳のやり方や償却のやり方など、正直なところ事業によって異なってくる部分が多い上、専門知識がなければ難しい部分が多いです。
CEOパートナーなど、開業サポートを専門としたサポートサービスを活用することで、開業準備や開業に関する手続き、税務などの不安を一気に解消しましょう。
些細な相談でも問題ないようですので、まずは気軽に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

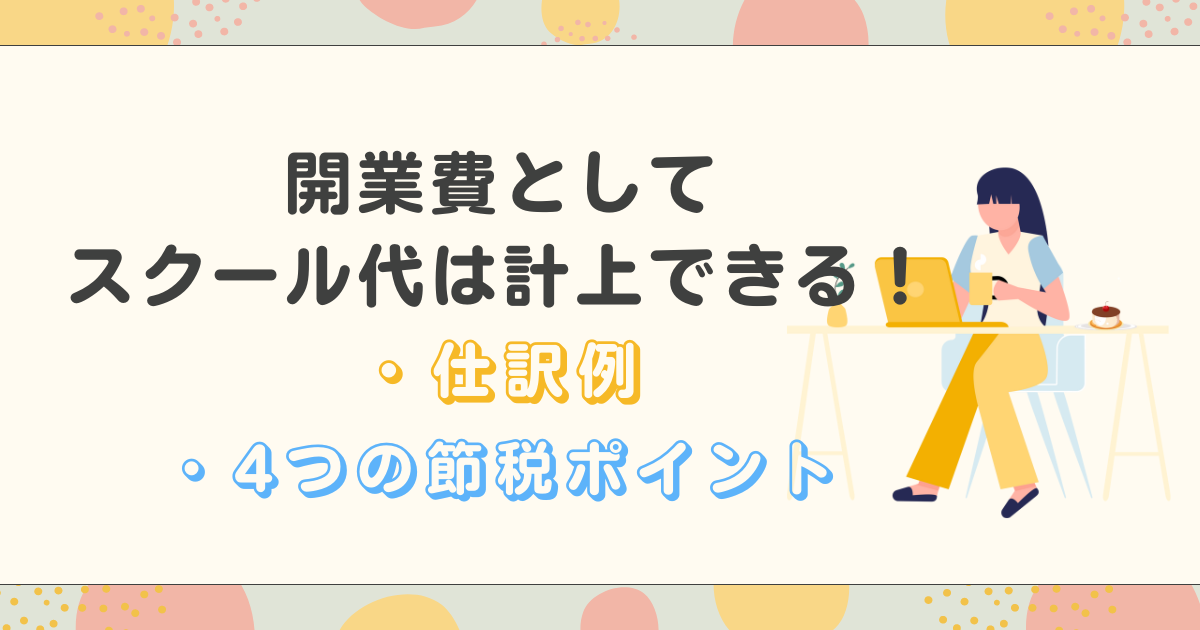








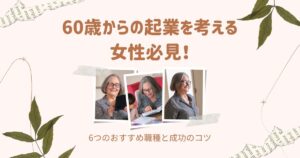

コメント
コメント一覧 (4件)
[…] 関連記事:開業費としてスクール代は計上できる!仕訳例と4つの節税ポイント […]
[…] あわせて読みたい 開業費としてスクール代は計上できる!仕訳例と4つの節税ポイント 開業費としてスクール代を計上するのは結論、開業に関係するものであれば可能です。計上のポイ […]
[…] あわせて読みたい 開業費としてスクール代は計上できる!仕訳例と4つの節税ポイント 開業費としてスクール代を計上するのは結論、開業に関係するものであれば可能です。計上のポイ […]
[…] ザインの資格を取る際に必要なスクールの受講費を運転資金として調達希望としている場合。 […]