開業を考える個人事業主にとって、費用の管理や税金問題は避けて通れませんよね。
開業費とは、開業日までの準備期間にかかった費用のことを指します。
しかし、どれくらいの範囲なのか、逆に開業費として当てはまらないモノはないのか区別しづらいですよね。
そこで、今回では開業費用の具体的な内容や節税方法を理解することで、仕訳の不安を軽減することができます。
本記事では、開業費の具体的な範囲はもちろんのこと、節税に役立つポイントを詳しく解説します。
最後まで記事を読めば、開業費用の全貌が明らかになり、仕分けの範囲が分かりますので、安心して事業をスタートさせていきましょう!
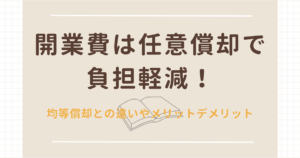
個人事業主の開業費の仕訳!費用の範囲
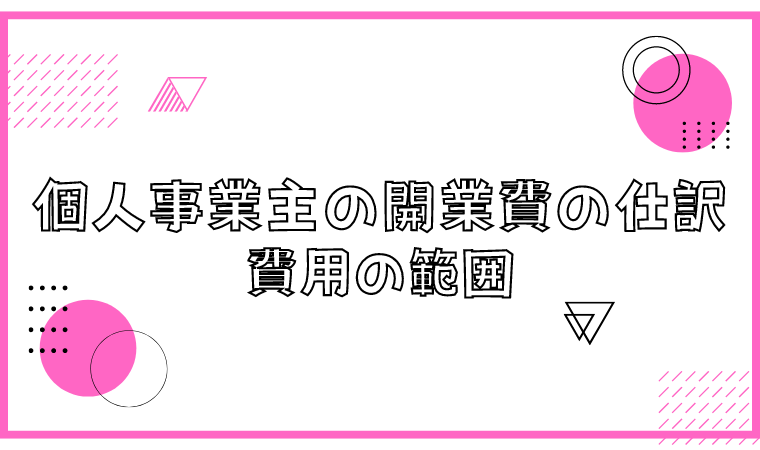
個人事業主として開業する前に発生した支出した費用、これを「開業費」と呼びます。
また、「開業準備費」とも言われています。
開業費は経費とは異なり、資産の一部として扱われます。
開業費は、事業開始に直接関連する具体的な費用を指し、その範囲と認識されるものには個人と法人で違いがあります。
ここでは個人事業主の「開業費」について説明していきます。
開業費として認められる具体的な費用
開業費とは仕訳では以下のようになります。
例として4月1日に開業したとして、開業前に支出した場合です。
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
| 開業費 | 4,110円 | 元入金 | 4,110円 | 3/28 文房具 |
| 開業費 | 2,500円 | 元入金 | 2,500円 | 3/29 打合せ交通費 |
明細ごとに記載することが理想ですが、別で開業費の内訳をまとめて計上している場合は、明細をまとめて入力しても問題ありません。
開業費として認められる具体例はこちらになります。
- 開業・独立のためのセミナー参加費
- 市場調査の旅費、ガソリン代
- 通信費
- 打合せ
- 交際費
- 広告宣伝費
事業に関わるのものであれば、開業費に含めることができますので、開業費の領収書を別途まとめて保管するようにしましょう。
開業費として認められない費用
開業費として、さまざまな費用を含めることができますが、認められない費用もあります。
一般的に開業費として、認められていません。
- 敷金
- 10万円以上の固定資産
- 商品の仕入代金
敷金は退去時に返金されるので、今後返金される可能性がある費用に関しては、開業費として認められません。また、礼金は20万円以下の場合は経費として、20万円以上は長期前払費用として繰延資産にすることができます。
10万円以上する備品は固定資産に該当するため、開業費として認められていません。
商品の仕入代金は売上原価として、経費ですので開業費になりません。
開業費の計上できる期間

開業をいきなりやり始める人はなかなかいません。
人によっては10年以上準備してから開業に臨む人もいるでしょう。
しかし、開業費はいつから計上ができるのでしょうか。
この章は開業費として計上できる期間についてまとめていきます。
開業届を出した日が開業日に
そもそも開業費は開業費の前に支出した費用になります。
個人事業主として開業したと認められる日は、一般的に開業届を提出日です。
しかし、開業届は提出義務やペナルティがないため提出しない方もいますが、屋号や青色申告ができない等デメリットが多いため提出することをおすすめします。
開業届を提出しなかった場合、事業を開始した日になるので注意しましょう。
開業日の半年~数カ月前の支出はOK
開業費として計上できる期間は一般的に開業日から半年、数カ月前とされています。
しかし、法律上で定められている期間は特にありませんので、開業のための支出の場合は何年前でも開業費として扱うことは可能です。
ただし、何年前の支出の場合は開業費として認められないケースもありますので、判断が難しい場合は税理士に相談しましょう!
開業費で節税するための3つのポイント
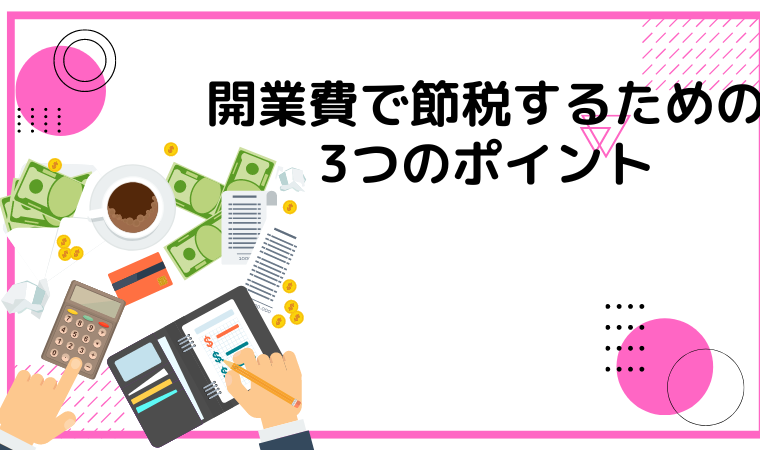
開業費は前述した通り、開業日から半年前の費用を計上することができます。
しかも、5年以上にわたって繰延資産として償却することができるので、活用することによって節税することができます。
ここでは開業費で節税する方法とポイントについてまとめています。
開業前の費用もOK
開業費は半年前の支出でも計上することは可能です。
しかし、何年も前の支出の場合は、本当に事業のための支出なのか疑われる可能性もありますので、購入した理由や用途をメモするようにしましょう。
もちろん、購入した際にはレシートや領収書を保管することを忘れずに。
領収書は画像で保管OK
レシートや領収書は必ず、保管するようにしましょう。
紛失するのが不安な方はスマホなどで写真として画像を残すことをおすすめします。
電子帳簿保存法によって、レシートや領収書が明細に写真で残っているのではあれば、計上することが可能だからです。
会計ソフトによってはスマホの画像を添付することも可能ですので、領収書の保管で大変な目に遭う前に会計ソフトの導入や写真として撮影するようにしましょう。
任意償却なら5年以上で自由に設定
開業費は一般的に5年で均等償却しますが、任意償却の場合は毎年異なる金額で計上しても問題ありません。
なぜ任意償却にすると節税になるかというと、その計上方法によって税金の負担が大きく変わるからです。
事業が利益を出している年には、開業費を多く償却することで、その年の課税所得を減少させることができます。
課税所得が少なくなれば、支払う税金も少なくなるため、税負担が軽減されます。
逆に、事業が損失を出している年には、あえて開業費を多く償却する必要はありません。
なぜなら、すでに損失が出ているため、さらに課税所得を減らしても税金の負担減にはつながらないからです。このような年に償却を控えることで、将来的に利益が出た時に償却額を増やし、税負担を効果的に減らすことが可能です。
確定申告を楽にする方法
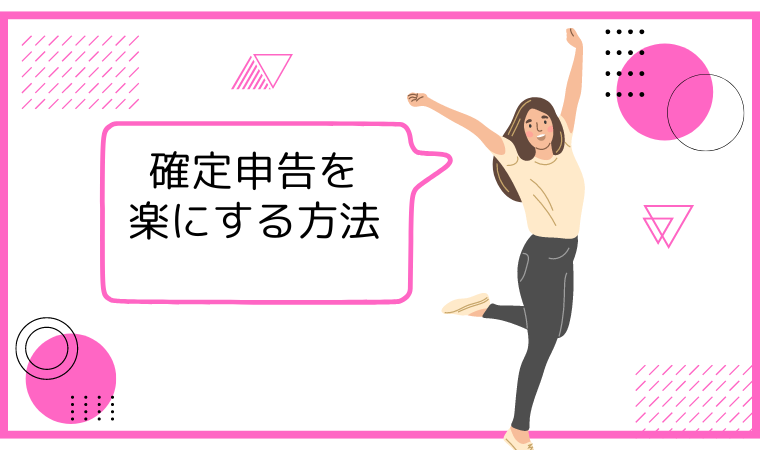
開業費のことが気になる時は確定申告前か、これから経費にする予定の方が多いのではないでしょうか。
個人事業主に必須の確定申告を少しでも楽にする方法を紹介します。
私が1番におすすめするのは、税理士に依頼することです。
会計の知識がゼロの私が学習して仕訳・帳簿をするより、節税対策ができますし、何よりその学習時間に営業や仕事を行った方が効率よく稼ぐことが分かったからです。
特にCEOパートナーでは国に認められた税理士事務所が登録されていますので、ぜひ活用してください。
ビジネスカードを作成する
ビジネス専用のクレジットカードを持つことは、個人事業主にとって大変おすすめします。
これにより、個人の支出と事業の支出を明確に分けることができるため、確定申告時に支出の整理が簡単になります。さらに、ビジネスカードの利用明細は、必要な経費の記録としてそのまま使うことができ、領収書を一つ一つ管理する手間を軽減できます。
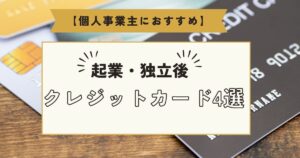
会計ソフトとクレジットカード・銀行口座を同期
最新の会計ソフトを利用して、ビジネスカードや銀行口座を同期することで、収支の管理が格段に楽になります。
このシステムは自動で取引を記録し、カテゴリー分けまでしてくれるため、確定申告の際に必要なデータの準備が直感的で簡単になります。
また、多くの会計ソフトは確定申告書類を自動で生成する機能も備えており、複雑な計算や書類作成の手間を大幅に削減できます。
税理士に依頼する
確定申告のプロセスを完全に楽にするためには、専門家である税理士に依頼することも一つの有効な手段です。
税理士は税に関する複雑な問題を解決できるだけでなく、ビジネスの成長をサポートするアドバイスも提供してくれます。
税理士に相談することで、税務のみならず、融資相談や事業戦略についても助言を得ることが可能です。これにより、事業のあらゆる側面でのサポートが期待できます。
CEOパートナーでは、融資の専門家以外にも税金や経営の相談できる税理士が登録しています。
一人で悩む前に、相談してみてください。
まとめ
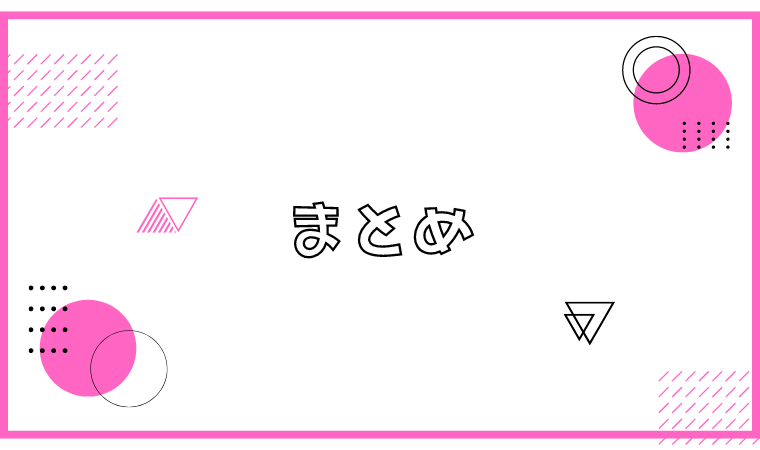
開業費として計上できる費用は、事業開始前の準備に関連するものが多く、その正確な管理が今後の税負担を軽減します。
また、確定申告を効率的かつ簡単に進めるための具体的な手法も紹介しました。
ビジネス専用のクレジットカードの利用、会計ソフトとの同期、そして最も効果的な方法として税理士への依頼があります。これらを利用することで、確定申告の手間を大幅に削減し、より事業に集中することができます。
最終的には、事前の準備と適切なツールの活用が、開業後の経営をスムーズにし、経済的な負担を軽減する鍵となります。
個人事業主として成功を目指すなら、今回の情報を活用して、開業費の管理と確定申告のプロセスを賢く進めましょう。










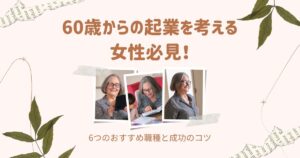

コメント
コメント一覧 (7件)
[…] あわせて読みたい 開業費で節税できる!個人事業主向けの節税対策3つのポイント 開業費は個人事業主と法人では計上のやり方や範囲が異なっています。今回個人事業主の開業費の仕訳 […]
[…] あわせて読みたい 開業費で節税できる!個人事業主向けの節税対策3つのポイント 開業費は個人事業主と法人では計上のやり方や範囲が異なっています。今回個人事業主の開業費の仕訳 […]
[…] あわせて読みたい 開業費で節税できる!個人事業主向けの節税対策3つのポイント 開業費は個人事業主と法人では計上のやり方や範囲が異なっています。今回個人事業主の開業費の仕訳 […]
[…] あわせて読みたい 開業費で節税できる!個人事業主向けの節税対策3つのポイント 開業費は個人事業主と法人では計上のやり方や範囲が異なっています。今回個人事業主の開業費の仕訳 […]
[…] あわせて読みたい 開業費で節税できる!個人事業主向けの節税対策3つのポイント 開業費は個人事業主と法人では計上のやり方や範囲が異なっています。今回個人事業主の開業費の仕訳 […]
[…] あわせて読みたい 開業費で節税できる!個人事業主向けの節税対策3つのポイント 開業費は個人事業主と法人では計上のやり方や範囲が異なっています。今回個人事業主の開業費の仕訳 […]
[…] あわせて読みたい 開業費で節税できる!個人事業主向けの節税対策3つのポイント 開業費は個人事業主と法人では計上のやり方や範囲が異なっています。今回個人事業主の開業費の仕訳 […]