
SAO税理士法人監修
月間支援創業融資面談数 80件以上
年間創業融資支援総額 40億円
創業融資をはじめとした資金調達サポート数 全国No.1
インボイス制度について、税理士から話を聞いてみたい、と考える人は少なくないのでは。
結局のところインボイス制度ってなに?と、よくわかっていない方もいらっしゃるでしょう。
会社を設立している方からすれば、登録しなければ消費税額において損する可能性がありますし、個人事業主の方は自身の報酬や仕事の取りやすさに影響してくる可能性も考えられます。
気軽に税理士まで、疑問に思った質問をとことんぶつけられる機会は少ないでしょうから、今回はCEOパートナーの提携先としても連携を取っております【SAO税理士法人】までインボイス制度についてたくさん質問をしてきました!
誰でも一度は抱えたことのあるぶっちゃけた疑問を質問していますので、ぜひぜひ参考にしていってくださいね。
\プロの税理士を頼るべき4つの理由をご紹介!/
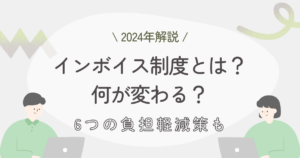
【インボイス制度】税理士法人に9つの質問を投げてみた!

今回は東京都に事務所を構える【SAO税理士法人】まで、ぶっちゃけた質問も込めて9つの回答をいただきました!
- インボイス制度ってそもそも何のためにあるの?
- インボイス制度にはどんなときに対応が必要?
- インボイス制度の仕組みと特徴を今一度教えて
- インボイス制度のメリットとデメリットは?
- インボイス制度にはぶっちゃけ対応するべき?
- インボイス制度による負担はどう乗り越える?
- インボイス制度の登録に必要な手続きは?
- インボイス制度のよくある勘違いはズバリ?
- インボイス制度の改正点など知っておきたい情報は?
インボイス制度ってそもそも何のためにあるの?
「インボイス」とは、一定の事項が記載された請求書や納品書など、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段となるものを言います。
インボイス制度は、消費税の仕入税額控除をより適正に行うために導入されました。
従来の請求書制度では、取引内容の詳細が不明確な場合や、誤って多くの消費税が控除されてしまうリスクがありました。
インボイス(適格請求書)を導入することで、売り手と買い手の双方にとって、正確な消費税額を記載した請求書を取引の証拠として使用し、税務上の透明性を向上させることを目的としています。
インボイス制度にはどんなときに対応が必要?
インボイスへの対応が必要な状況は、課税事業者が取引を行う場合です。
特に、以下のような場面で対応が求められます。
- 課税事業者同士が取引を行う場合
課税事業者が仕入れ税額控除を受けるためには、取引相手から適格請求書(インボイス)を受け取る必要があります。
そのため、インボイスを発行しないと、取引先が控除を受けられない可能性があり、取引に支障が生じることがあります。
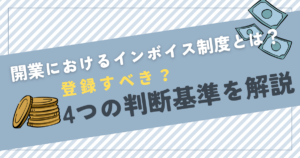
インボイス制度の仕組みと特徴を今一度教えて
インボイス制度では、適格請求書には指定の情報を含めることが義務付けられています。
以下の要件に沿った適格請求書を発行することによって、取引の詳細と消費税の計算がより透明になり、税務当局にとっても検証が容易になるという仕組みです。
- 適格請求書発行事業者の登録番号
インボイスを発行できるのは、税務署に登録された「適格請求書発行事業者」のみです。請求書には、この登録番号を記載する必要があります。
- 取引内容の詳細
請求書には、取引した商品の種類や数量、金額を明記し、税率ごとの区分も明示する必要があります。
- 消費税額の明記
商品やサービスの価格に対して、消費税がどのように計算されているか、税率ごとに消費税額を明確に示します。
- 発行者の情報
インボイスを発行する事業者の名前や住所、取引の内容や取引日も記載されます。
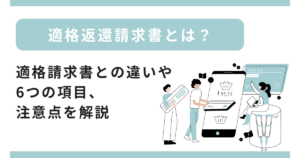
インボイス制度のメリットとデメリットは?
インボイス制度のメリット・デメリットは次のように挙げることができます。
【メリット】
- 取引の透明性が向上
消費税の計算が明確になるため、取引がより公正で透明なものになります。
税務調査の際にも、インボイスがあることで消費税額が明確に示され、説明が容易です。
- 仕入税額控除の確保
インボイスを受け取ることで、買い手側は消費税を適切に控除できるため、税負担が軽減されます。
- 適格請求書発行事業者としての信頼性向上
インボイスを発行することで、事業者が適格請求書発行事業者として登録されていることを示し、取引先からの信頼性が高まります。
【デメリット】
- 事務負担の増加
インボイスを発行するためには、適切な会計処理が求められます。
特に小規模事業者や免税事業者にとっては、インボイスの作成や管理が負担になることがあります。
- 免税事業者への影響
免税事業者はインボイスを発行できないため、課税事業者との取引で不利な立場に立たされる可能性があります。
取引先がインボイスを必要とする場合、免税事業者はその要求に応じることができないため、取引が減少するリスクがあります。
- システム導入コスト
インボイス制度に対応するために、会計ソフトや管理システムの導入が必要になる場合があり、それに伴うコストが増加します。
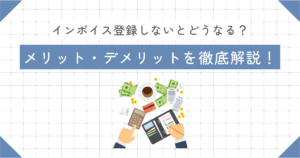
インボイス制度にはぶっちゃけ対応するべき?
多くの事業者にとって、インボイス制度を導入するかどうかの検討は不可避と考えられます。
特に、課税事業者と取引をしている場合や、取引先が仕入れ税額控除を求める場合には、インボイスの発行が必要です。
免税事業者にとっても、取引の減少リスクを回避するためには、課税事業者への転換を検討する必要が出てくる可能性があります。
具体的に対応すべきかどうかは、事業者の規模や取引先の要望、将来的な事業の発展を見据えて判断すべきですが、大規模な取引を行っている事業者やBtoBの取引を行っている場合は対応が必要です。
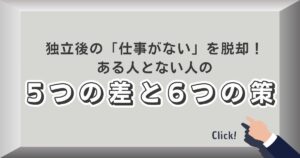
インボイス制度による負担はどう乗り越える?
コスト面での負担もそうですが、適格請求書の発行など、今までとは違った負担が発生してしまうのも事実です。
負担を乗り越える術はいくつかあります。
- 会計ソフトやERPシステムの導入
インボイス対応が可能な会計ソフトを導入することで、適格請求書の作成や管理が容易になります。
これにより、事務作業の負担を大幅に軽減することができます。
- アウトソーシングの活用
税理士や会計事務所などの外部の専門家に手続きを委託することで、複雑なインボイス対応をスムーズに進めることができます。
- 社内体制の整備
インボイス制度への対応には、事務作業が増えることが予想されるため、適切なスタッフの配置や教育が重要です。
また、業務の効率化や分担を見直すことで、負担を軽減することができます。

インボイス制度の登録に必要な手続きは?
インボイス制度に対応するにあたって必要な手続きを具体的に見ていきましょう。
税務署に「適格請求書発行事業者登録申請書」を提出する必要があります。
これは、国税庁のウェブサイトからダウンロードでき、必要事項を記入した上で税務署に提出します。
申請が承認されると、税務署から登録番号が付与されます。
この番号はインボイスに記載する必要があります。
登録が完了すると、適格請求書としてのインボイスを発行することが可能となります。
ただし注意点として、登録開始日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間は免税事業者に戻ることはできません。
インボイス制度のよくある勘違いはズバリ?

免税事業者はインボイスに関係ない…?
免税事業者でも取引先がインボイスを必要とする場合、対応を求められることがあります。
免税事業者が課税事業者に転換しないと、取引先が税額控除を受けられないため、取引に影響を及ぼす可能性があります。



インボイスがないと、全ての経費が認められない…?
インボイス制度は消費税の仕入税額控除に関する制度です。
そのため、消費税に関係のない取引や経費については、インボイスがなくても認められます。
ただし、消費税の控除を受けるためには、インボイスが必要になるという点が重要です。
※当面の間、消費税の控除には経過措置があります。次項「インボイス制度におけるその他知っておきたい情報は?」をご参照ください。



免税事業者はインボイスを発行する資格がないため、消費税を記載した請求書も発行できない…?
免税事業者は、インボイス(適格請求書)を発行することはできません。
しかし、従来通りの請求書や納品書は発行可能です。
ただし、取引先はその取引に対して仕入税額控除を受けることができない点に注意が必要です。
※当面の間、消費税の控除には経過措置があります。次項「インボイス制度におけるその他知っておきたい情報は?」をご参照ください。
課税事業者になりたい場合は、インボイス制度に登録して課税事業者となる必要があります。



インボイスを発行しなければ、ビジネス取引そのものができなくなる…?
インボイスを発行しなくても取引自体は可能です。
ただし、インボイスを発行できない事業者(免税事業者など)との取引では、取引先は仕入税額控除を受けられなくなるため、取引先にとって不利益が生じることがあります。
このため、取引先がインボイス発行事業者との取引を優先する可能性は高いですが、取引そのものが禁止されるわけではありません。
インボイス制度におけるその他知っておきたい情報は?
【2023年~2029年の経過措置】はぜひとも知っておきましょう。
インボイス制度の導入に伴い、制度に慣れるための経過措置が設定されています。
この経過措置期間中、一定の条件を満たせば、取引先がインボイスを受け取らなくても部分的な仕入税額控除が認められる仕組みがあります。
- 2023年10月1日~2026年9月30日: この期間は、インボイスがない場合でも80%の控除が可能。
- 2026年10月1日~2029年9月30日: 次の段階では、控除率が50%に減少します。
- 2029年10月1日以降: 完全にインボイスがない場合は、控除は認められなくなります。
経過措置について日本税理士会連合会による詳しい情報はこちら
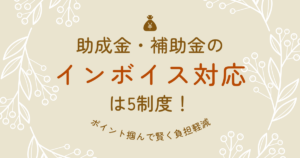
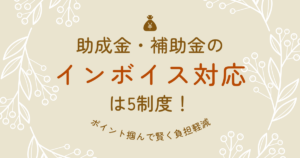
インボイス制度を税理士法人に質問するならCEOパートナー!
なかには、インボイス制度について個別に質問したい!という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんなときはCEOパートナーまでお問い合わせいただければ、税理士法人まで直接おつなぎすることが可能です。
税務・起業サポートのプロに経営相談ができる
CEOパートナーからご紹介する税理士法人はただ単に税務を行うだけでなく、起業や事業経営サポートの面でも強みを持っています。
そのため税務の観点だけでなく、経営者に寄り添ったインボイス制度の対応におけるアドバイスが可能です。
制度への疑問解消に留まらず、自身の状況に応じたアドバイスや具体的なサポートを受けたい方はぜひ問い合わせてみましょう。


インボイス制度にかかる業務を丸投げできる
もし一人でインボイス制度の登録や必要な対応を行うのが不安な場合、CEOパートナーからご紹介する税理士法人の担当者まで相談すれば、かかる業務をすべて請け負ってもらうこともできます。
あるいは対応手順などを教えてもらい、あとは自身で対応するといったこともできますので、気軽に相談してみましょう。
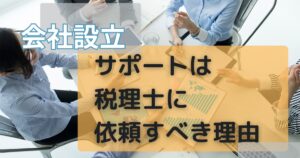
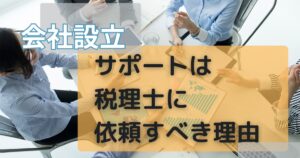
節税相談も積極的に行えば間違いなし
なんといっても税務に精通した税理士法人なので、節税における知識は誰よりも豊富です。
インボイス制度により負担を増やしたくない方は、ぜひ積極的に相談してみてください。
インターネットなどで調べても分からない、適切な節税の方法を教えてもらえるかもしれません。


まとめ
インボイス制度について相談するなら、税理士が最適な専門家です。
9つのぶっちゃけた質問に対する回答をご参考いただき、他にも個別に相談したいことがあればぜひCEOパートナーまでご相談ください。
今回の記事作成にあたりご協力いただいた、【SAO税理士法人】も、CEOパートナーからご紹介のできる税理士法人です。
起業や会社設立、創業融資をはじめとした資金調達サポートにも精通していますので、併せて相談を検討してみてくださいね。



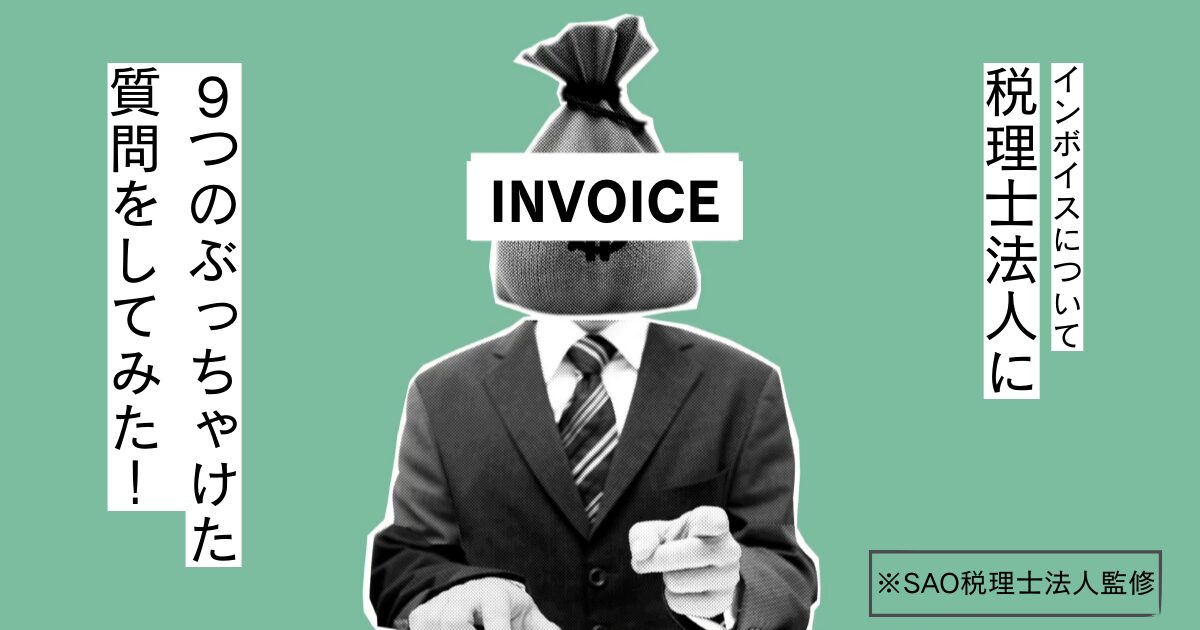









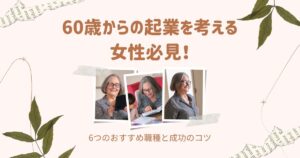

コメント