2006年に会社法が改正され、今までハードルの高かった会社設立が誰でも容易にできるようになりました。
それでもやはり固定概念はなかなか消えないもの。
会社を設立するというのはとても難しそうで自分ではできないもの、という風に考えている方も少なくないでしょう。
確かに個人事業主に比べると会社を設立する、法人化するということはやることや必要書類が増えるという事になります。
その半面、社会的信用は個人事業主に比べると高まり融資などが受けやすくなるというのも事実。
将来、事業拡大を目指しているのであれば自身の会社を持ち、法人化する事をおすすめします。
ではここで疑問なのが「会社設立は自分でできるの?」という点です。
なんだか難しそうな会社設立は自分でできるのでしょうか。
本記事では「会社設立は自分でできるのか」という疑問について徹底解説していきます。
その他にも会社設立の流れやよくある質問をQ&A形式でご紹介!
会社設立をしたいけど自分ではできないから、と諦めかけている方!
ぜひ参考にしてください!

自分で会社設立はできる?メリットとデメリット

早速、会社設立が自分でできるかどうかについて解説していきます。
会社設立は自分でできる!
結論からお伝えすると、会社設立は自分でも可能です。
ただし、だからといって誰でもできるわけではありません。
- 会社概要を決める
- 実印を作る
- 定款を作成・認証を受ける
- 資本金の払い込みを行う
- 登記申請書類の作成・申請
これらをすべて自分で行う必要があります。
初めて会社を立ち上げようとする方には、ハードルが高いとも言えます。

自分で手続きするメリットデメリット
では、自分で手続きをする際はどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。
下記を参照してください。
【メリット】
費用を安く済ませられる
会社設立に関するスキル経験が身に付く
【デメリット】
時間と手間がかかり、本業に支障をきたす恐れがある
難易度が高いため、途中でミスが起こりやすい
専門家に任せるメリットデメリット
続いては、会社設立を専門家に任せた場合のメリットとデメリットを以下に記していきます。
【メリット】
面倒な手続きを任せられる分、本業に注力できる
起業するにあたり、専門家に不安な点を相談できる
【デメリット】
一定の費用が掛かる
専門家を探す手間がかかる
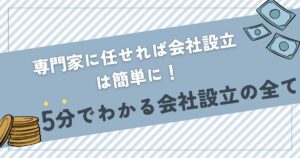
会社設立を自分で行う流れ

会社設立を自分で行った場合と、専門家に任せた場合のメリット・デメリットについてはご理解いただけたでしょうか。
そのうえで、自分で会社を立ち上げたいと思った方に向けておもな流れについて解説します。
商号などの会社概要を決める
まずは、商号(社名)や所在地、設立日など会社の基本情報を決めなければなりません。
決めておくべき事項は以下の通りです。
- 社名(商号)
- 本店所在地
- 会社の設立日
- 資本金額
- 事業の目的
- 株主の構成
- 役員の構成
会社のプロフィールとなる部分なので、慎重に決めてください。
法人用の実印を作成する
登記申請するには会社の実印が必要だったものの、2021年2月からの法改正からはオンラインで行う場合の届出は任意となりました。
とはいえ、書面で申請する場合はやはり印鑑は必要です。
さらに、会社設立後も実印は何かと必要な場面がやってきます。
慌てて作ることのないように、事前に作成しておきましょう。
定款を作成する
定款とは、会社の基本的なルール・規定、運営に関する規則を定めた書類です。
「会社の憲法」と呼ばれ、設立時には必ず作成しなければなりません。
記載内容については、絶対的記載事項として下記5つが挙げられます。
- 事業目的
- 社名(商号)
- 本社の所在地
- 資本金額
- 発起人氏名と住所
こちらは記載漏れがないように、提出前にきちんと確認しておきましょう。
資本金を払い込む
提携を作成した後は、資本金の支払いを行います。
2006年の会社法改正により、資本金が1円からでも会社を立ち上げることが可能になりました。
任意の金額を振り込めば問題ありませんが、あまりに低い資本金だとクライアントやパートナーから怪しく思われてしまう可能性があるので要注意です。
また、この時点では会社の銀行口座はまだない状態です。
よって、資本金の振込先は発起人の個人口座になるでしょう。

登記申請を行う
ここまで終了したら、いよいよ登記申請を行います。
設立登記申請書などの必要書類を準備して法務局に提出してください。
法人登記の申請を行った日が会社の設立日です。
登記申請時には、登録免許税を納付しなくてはなりません。
金額は「資本金額×0.7%」で算出されます。
ただし、その金額が15万円に届かない場合は15万円を支払わなければなりません。
設立後にやらなければいけない3つのこと

ようやく会社を設立できても、やらなければならないことはまだあります。
こちらも計画的に進められるように、事前に準備しておきましょう。
税金関係
会社を運営するためには、さまざまな税金がかかります。
おもな種類は下記5つです。
- 法人税
- 地方法人税
- 法人住民税
- 法人事業税
- 固定資産税
ルールに則って支払うためには、登記が完了後に必要書類を税務署・都道府県税事務所・市町村役場などに届出が必要です。
フローが多いですが、会社運営には必要不可欠なので忘れずに行いましょう。

保険関係
健康保険や厚生年金保険といった社会保険の手続きも必要です。
関係各所へ届出を行いましょう。
よくある勘違いとしては、社員がいないから加入しなくてもよいと思っているパターンです。
これは間違いであり、たとえ社員が社長1人のみであっても社会保険には加入しなければなりません。
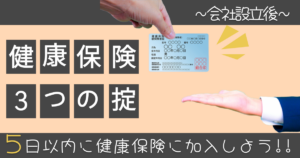
労働関係
従業員を雇い入れる場合は、さらなる手続きが必要です。
労災保険や雇用保険に加入させなければなりません。
労災保険は労働基準監督署へ、雇用保険はハローワークにて手続きを行ってください。
社員が安心して働ける環境づくりを行うのも、社長の重要な役目です。
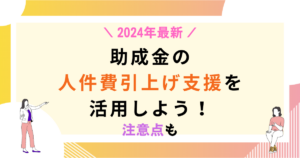
会社設立を任せるならこの専門家で!

一人で会社を設立するのは難しい場合は専門家に頼るのがおすすめです。
以下4つのなかから、自分に必要な専門家を検討してみてください。
- 司法書士
- 行政書士
- 税理士 ←特におすすめ
- 社会保険労務士
司法書士
おもに登記業務を代行してくれるのが司法書士です。
登記申請を代行できるのは司法書士だけなので、ほかの専門家に依頼することはできません。
依頼費用の目安としては20万円以上とされています。
登記業務は複雑で厄介なので、任せてしまえばスムーズに事業を進められるでしょう。

行政書士
国や地方自治体などに提出する行政書類を作成するのが行政書士です。
定款の作成・提出や許認可の申請など多岐にわたる業務を依頼できます。
依頼費用目安は10万円以上です。
許認可の提出は業種によって異なるので、必要な場合は依頼することをおすすめします。
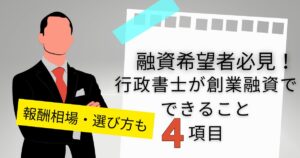
税理士
会社設立や確定申告の際に、税務面からサポートしてくれるのが税理士です。
節税についてのアドバイスも得られるので、相談してみるとよいでしょう。
ここで、税理士への相談を検討している方におすすめの機関があるので紹介します。
それが、CEOパートナーです。
創業関連に強い税理士を紹介するサービスを行っているため、会社設立に特化した相談ができます。
さらに、融資や補助金を受けるまでは費用は一切かからないメリットもあります。
10~20万円程度とされている税理士の依頼費用目安を考えると、ぜひ問い合わせておきたい企業です。
\プロの税理士を頼るべき4つの理由をご紹介!/

社会保険労務士
従業員を雇用する際に検討しておきたいのが、労務関係の手続きの専門家である社会保険労務士です。
社員の労働保険や年金に関する相談、さらに書類作成まで請け負っています。
依頼費用目安は10万円前後とされています。
雇用関連の助成金を検討している方は、社会保険労務士がいるとスムーズに申請が可能です。
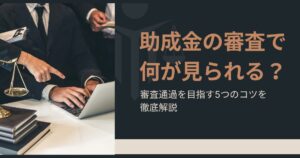
自分で会社設立をする方へ!よくある質問Q&A

最後に、会社を自分で立ち上げようとする方から挙がりやすい質問をまとめました。
自分でやるのと代行、どっちがいいの?
会社設立に必要な時間・費用・難易度を検討したうえで、最適な結論を出しましょう。
すべての作業を自分で賄おうとするのは時間がかかりますし、かといってすべてを任せるとお金がかかっていまいます。
事前に時間・費用・難易度をもとにどこまでを自分でやって、どこからを代行するのかを決めておきましょう。
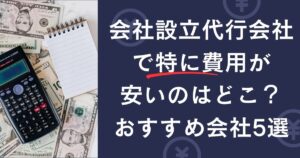
自分でやるとどれくらいの期間が必要?
株式会社の場合は1ヶ月程度を見ておくとよいでしょう。
定款の作成や認証、登記申請を合わせると手続きそのものは3週間ほどで終わります。
ただし、その前後には知識の習得期間や不備を訂正する時間なども必要でしょう。
初めての会社設立でスムーズにいくとは考えにくいため、1ヶ月程度の期間で考えておく方がよいです。
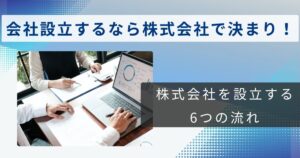
会社設立にはどのくらいの費用がかかる?
株式会社の設立は18~25万円程度かかるとされています。
その内訳は下記のとおりです。
- 定款用収入印紙:4万円(電子定款の場合は不要)
- 定款の認証手数料
資本金額等が100万円未満の場合:3万円
資本金額等が100~300万円未満の場合:4万円
資本金額等が300万円以上の場合:5万円 - 謄本の発行手数料:2,000円(目安)
- 登録免除税:15万円(目安)
専門家に代行依頼をする際は、さらに5万円から30万円程度の費用がかかるでしょう。
代行を頼りたい場合は、最初に見積もりを取ってみてください。

会社の定款を作成するポイントは?
会社設立の際に壁にぶつかりやすいのが定款の作成です。
細かな規定がなく、自由に作成できるがゆえに初心者の方はどのように作ったらよいかわからないと思うことも少なくありません。
ただし、「定款に記載する事業目的は多くても10~20個まで」というルールが存在します。
知らなかったために認証されなかったケースもありました。
余計な手間を防ぐためにも、可能であれば専門家に依頼するのがベターです。
また、定款を書類で提出する際は4万円の収入印紙代がかかるものの電子定款の場合は不要という点も押さえておきましょう。
資本金はどのくらい必要?
決まりはないものの、100万円から300万円程度が最も多いボリュームゾーンです。
会社を立ち上げる際に迷うことの一つに、「資本金がいくらがいいか」という点があるでしょう。
2006年の会社法改正により1円から会社を設立できるようになりましたが、最低でも100万円はなければ社会的信頼は得られにくいのが現状です。
また、資本金の額に応じて税金の額も異なってきます。
1,000万円未満の場合、消費税が最大で2年間免税になるほか、法人住民税も安くなります。
節税を目指しながら運営したいのであれば、資本金は1,000万円未満に設定するとよいでしょう。

電子定款と紙の定款の違いは何?
作成方法や認証方法、かかる金額などが異なります。
| 電子定款 | 紙定款 | |
| 作成方法 | PDFファイルに電子署名してデータ保存 | 紙で印刷して捺印 |
| 認証方法 | 公証役場に出向いて認証を受ける | 公証役場に出向いて認証を受ける |
| 費用 | 無料 | 収入印紙代4万円 |
| 署名 | 代表者のみ | 発起人全員 |
電子定款であっても、公証役場に出向いて内容をチェックしてもらう必要があります。
とはいえ、費用も時間もかからないので、電子定款で進めるのがおすすめです。
どの形態で設立するのがおすすめ?
会社設立の際におすすめしたい形態は、「株式会社」と「合同会社」のいずれかです。
数が多いのは株式会社でしょう。
社会的信用度やリスクの少なさなどから多くの起業家が選択しています。
ただし、会社設立にかかる費用は合同会社の方が安く済みます。
定款の認証が不要なので、手間も時間も抑えてスタートできるでしょう。
信用は株式会社と比べると落ちるものの、最小限の費用で会社を立ち上げたい方にはおすすめです。
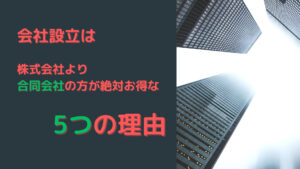
まとめ
会社は自分一人でも設立可能です。
しかし、やることが膨大過ぎてどれから手を付けたらよいかわからない方も多いでしょう。
手間や時間、難易度を踏まえて任せられる部分は専門家に依頼してしまった方がスムーズにいく場合もあります。
相談先は、CEOパートナーを検討してみてください。
紹介する税理士法人は下記のような実績を有しており、事業や経営の相談をするには最適です。
- 公庫面談サポート数が税理士法人で全国1位
- 毎月の創業融資相談件数1,000件以上で税理士法人日本一
最良の形で会社を立ち上げられるようにサポートしてくれるでしょう。


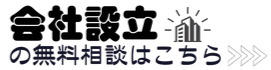
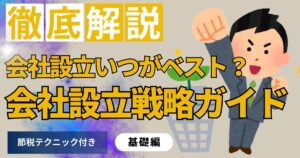
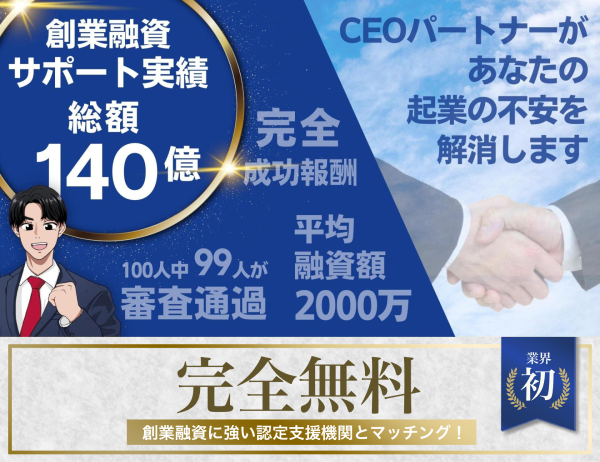


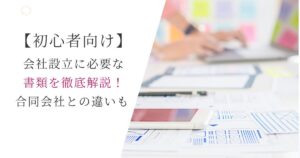
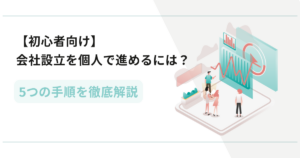
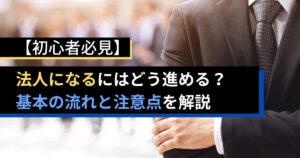


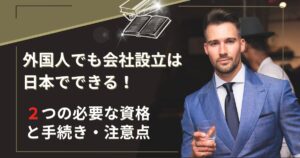
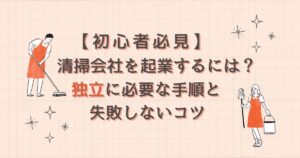

コメント