開業費を個人事業主が適切に仕訳する方法、知りたいですよね。
開業前の個人としては、初めての税務における不安は必ず付き物と言えます。
今回は個人事業主が開業費を正しく仕訳するための具体例やポイント、そして注意点などをご紹介していきます!
税務の難しさは何も一人で抱え込む必要はなく、専門家である税理士を頼るのが一番。
CEOパートナーという、開業時に頼れる税理士のコンサルサービスを同時にご紹介していきますので、ぜひ併せて確認してみてくださいね。
\プロの税理士を頼るべき4つの理由をご紹介!/

開業費を個人事業主が仕訳するには?

個人事業主が開業費を仕訳する上で、知っておきたい知識から具体的な仕訳例までをご紹介していきます。
早速、開業費を正しく管理する方法をここで把握していきましょう。
開業の準備費用を「開業費」として仕訳
個人事業主は開業費にできる範囲が広く、開業前、一般的には半年~1年前から開業準備に必要とした費用を「開業費」とすることができます。
仕訳する際にはそのまま「開業費」として記入していきます。
開業費は繰延資産として償却できる
厳密に言うと開業費は経費とは異なります。
繰延資産という資産の科目として処理し、毎年少しずつ経費にしていく「償却」を行なっていくことができます。
償却できることのメリットとして、確定申告時に経費申告する金額を自由に調整できる「任意償却」を選べば、利益の大きい年に一気に経費に、少ない年に少なめに申告することでキャッシュフローの調整が叶う点が挙げられます。
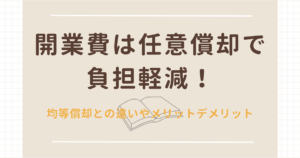
開業費の具体的な仕訳例
ここでは個人事業主が仕訳するときの具体例をご紹介しましょう。
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
| 開業費 | 25,670円 | 元入金 | 25,670円 | 〇/〇 広告宣伝費 |
| 開業費 | 34,340円 | 元入金 | 34,340円 | △/△ 調査用の旅費 |
借方勘定科目は開業費とし、貸方勘定科目は元入金とします。
また、開業した日付を開業日として登録します。
開業費はまとめて入力することも可能で、1行にまとめた金額を開業費として入力し、摘要欄に「別紙明細あり」などと記入して別途明細を保存しましょう。
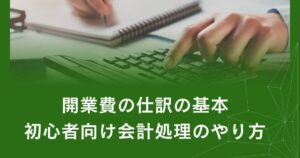
開業費として認められない費用に注意

開業準備に要したからと言って、必ずしもすべてが開業費として認められるわけではない点に注意が必要です。
ここでは、個人事業主の開業費として認められない費用を3つお伝えしていきます。
1つで10万円以上の固定資産
複数項目を購入し、まとめて10万円以上となった場合は開業費として問題ありませんが、1つで10万円以上する、例えばパソコンやその周辺機器などといった高価なものに関しては固定資産となってしまいます。
固定資産は開業費として認められず、別途固定資産として償却をしていく必要があるのです。

返還されるであろう敷金
事務所など仕事場となる物件の賃貸契約を行なう場合、オーナーへ支払う敷金は開業費として認められません。
敷金は退去時に返還されるものという一般的な認識であるため、完全に手放す金額とは考えられず開業費にはならないのです。
商品の仕入代金
商品の仕入に要した費用は開業準備の費用として、開業費となりそうですが実際は認められません。
仕入代金は売上原価として経費計上するため、開業費とは別の扱いとなります。
個人事業主が開業費を正しく仕訳するポイント

開業費の仕訳を間違ってしまうと、確定申告時など、後々に支障が出てしまうでしょう。
開業費の正しい仕訳につながるポイントを、個人事業主に特に気にしてほしい部分に特化してご紹介していきます。
領収書など明細は必ず保管する
大前提として、開業費として使ったお金を申告するにはその裏付けとなる証明がなければなりません。
領収書などといった支払明細は、必ず受け取って保管する癖を付けましょう。
また、理想の仕訳は明細ごとに分別しての入力ですが、別で明細の確認可能な集計を行なっている場合は、「開業費」としてざっくりまとめて入力する形も認められます。
その場合は明細と領収書を必ず照らし合わせる状態で保管するようにしましょう。
開業後の経費などと混合してしまわないよう、開業前の書類は別で管理するのもポイントです。
合計10万円未満は仕訳帳で経費計上
開業費が合計で10万円未満の場合は、仕訳帳への記入のみ行ないます。
管理の仕方は特に通常の経費と変わりありません。
1章でご紹介した仕訳例を参考に、仕訳帳へ記入してみてください。
合計10万円以上は減価償却資産台帳にも記入
開業費の合計が10万円以上となった場合には、仕訳帳に加え、減価償却資産台帳への記入も併せて行なう必要があります。
繰延資産として、取得・減価償却・売却・除去などといった経緯をすべて漏れなく記入します。
開業費の修正を行なう場合は仕訳帳と減価償却資産台帳の両方を修正する必要があり、忘れず行なわなければなりません。
また合計10万円以上の開業費は、10万円未満の場合とは仕訳帳への記入方法も異なりますので例を下記に挙げておきます。
- 開業費は資産の科目、開業償却費は経費の科目として記入
- 年度の償却金額を「開業費全額÷5年×当該年度の月数/12」で算出
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
| 開業償却費 | ○○(年度の償却金額)円 | 開業費 | ○○(年度の償却金額)円 | 開業準備費 |
個人事業主は青色申告の選択がおすすめ

個人事業主は開業時に青色申告か、白色申告を選択できます。
開業費による損を防ぐには、青色申告の選択が断然おすすめです。
その理由を見ていきましょう。
白色申告だと赤字が繰り越せない
白色申告を選択すると、赤字の繰り越しが認められていないために翌年への繰り越しができません。
一方で青色申告を選択すると、赤字の繰り越しを翌年以降3年間行なうことが認められます。
繰り越しが行なえることで償却額の調整が柔軟になり、開業初年度など、利益の少ない年に経費を少なく申告して赤字回避、利益の大きい年に一気に償却することで節税につながります。

最大65万円の所得控除が節税につながる
開業費の管理とは少し別の観点にはなりますが、青色申告を選択することで、確定申告時に最大65万円の所得控除が受けられます。
所得控除が受けられることが節税につながり、開業費の償却額の調整も併せて自由に行なえることから更なる節税が期待できるのです。
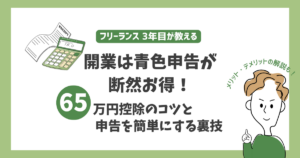
開業費の仕訳で迷ったらCEOパートナーに相談
個人事業主、特に開業したての初心者が開業費の仕訳を完璧に行なうのは難しさがあると言えます。
税務のことは、税務を専門とした税理士を頼るのが一番。
ここでは開業時に頼りたい税理士のコンサルサポートサービス、「CEOパートナー」についてご紹介していきます。
\プロの税理士を頼るべき4つの理由をご紹介!/
税務に強い税理士による開業サポート
CEOパートナーでは開業費の仕訳に留まらず、開業に必要な手続き全般におけるサポートを行なっています。
さまざまに手続きが存在するなかで、特に難しいとも言える税務関係の手続きをサポートしてくれる税理士が身近にいるのは大変心強いことです。
税務で悩む時間があれば、税理士を頼って本業に時間を効率よく回しましょう。
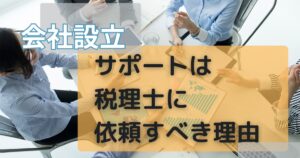
開業前なら無料で資金調達相談ができる
CEOパートナーは資金調達サポートを一番の強みとして掲げているサービスです。
資金調達の相談は完全成功報酬型を採っており、融資実行が叶うまでは一切の費用がかからずに何度でも相談が可能となっています。
開業前の資金調達においても不安を抱いている方は、ぜひ開業前から相談を始めることをおすすめします。

開業費に限らず確定申告は税理士に任せて安心
税務の専門家であるため、確定申告時に頼ることももちろん可能です。
開業費に限らず、事業全般における経費管理や帳簿の付け方、確定申告の仕方まで、一貫してアドバイスやサポートを受けることができます。
個人事業主として開業済みの私自身も実際、確定申告は税理士を頼って行なっています。
本業に集中し、余計なストレスをなくすためにも専門分野は専門家を頼ることがおすすめです。
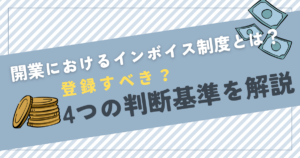
まとめ
開業費を個人事業主が正しく仕訳するには、合計額に応じて仕訳帳や減価償却資産台帳を入力し、繰延資産として償却していくのがポイントです。
開業費として認められない費用の確認や、領収書の保管・青色申告の選択など、損につながらない対策をとっていくことで大きな節税につなげることが可能でしょう。
また、少しでも不安があるなら税務の専門家である税理士を頼るべきです。
CEOパートナーでは開業サポートに強みを持つ税理士と即日マッチングが叶います。
開業前からの相談がおすすめですので、ご自身の負担を減らすためにも一度気軽に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
\プロの税理士を頼るべき4つの理由をご紹介!/


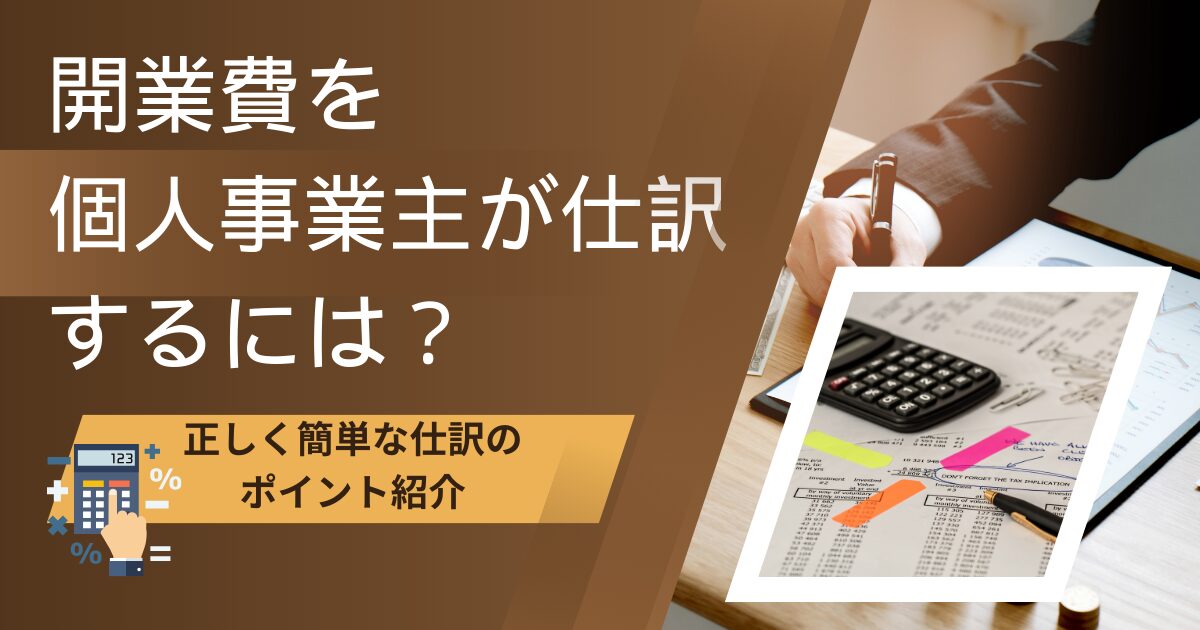








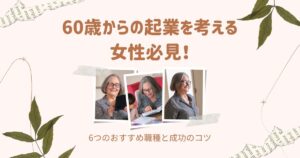

コメント
コメント一覧 (2件)
[…] あわせて読みたい 開業費を個人事業主が仕訳するには?正しく簡単な仕訳のポイント紹介 開業費を個人事業主が仕訳するには、合計額に応じた仕訳の仕方や開業費として認められない […]
[…] あわせて読みたい 開業費を個人事業主が仕訳する方法とは?注意点や仕訳のポイントも解説 […]