「創業融資の難易度ってどれくらいなの?」
創業融資を受けたいけれども、そもそも難易度がどれくらいなのかと気になりますよね。
実は、最も融資を受けやすい日本政策金融公庫でも通過率は50%程度だと言われています。
しかし、融資審査を問題なく通過している人もいますし、窓口相談時点で断られてしまう人がいるのも事実です。
その違いは「創業融資の難易度は何を基準として変動するのか」を知っているか、知らないかの差でもあります。
そこで今回、創業融資の難易度が決まるポイントや、ポイントを踏まえた上で難易度を下げる方法をまとめてみました!
少しでも審査通過の可能性を高めたい方は必見の内容となっています。
この記事を読んで、融資審査を攻略していきましょう。
創業融資の難易度は?

創業融資の難易度は、一概には言えませんが、ある程度の目安となる審査通過率としての数値が出ています。
難易度を把握しておくことで、審査準備に向けた適切な心構えができるはず。
審査通過の目安は50%~60%
あくまでも目安であり、その年によっても数値に変動はありますが、審査に通過する人の確率は50%~60%と言われています。
50%~60%というのは公表されている数値ではありませんが、日本政策金融公庫の融資業務に従事していた方や、融資サポートを得意とする税理士の方の肌感覚として、このような数値が出ているのです。

業種によっては審査が厳しくなることも
実は、審査の厳しさは景気変動や環境変化の影響を大きく受けます。
不況状態にある業種で、たとえば最近倒産の多い業種となると、審査時の判断は厳しくなります。
そのため、どれだけ審査対策を万全にしていたとしても「業種の状態がよくない」ことを理由として審査落ちとなる可能性もあるのです。
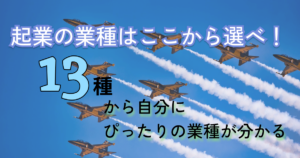
創業融資の難易度が決まる3つのポイント
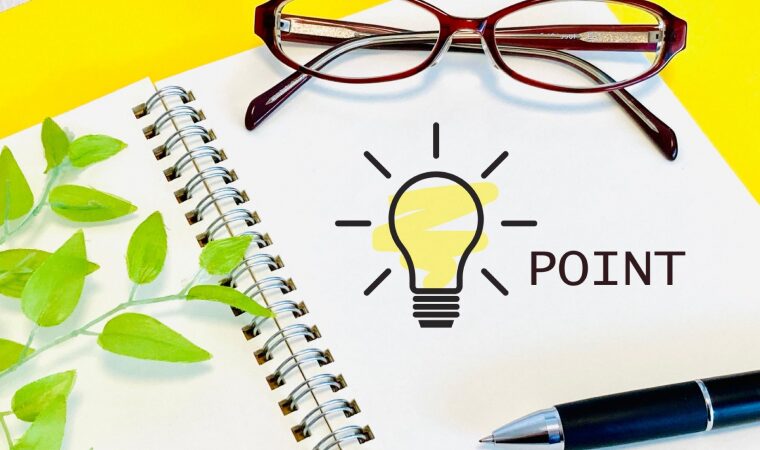
融資審査を受ける際に担当者が見るポイントは気になりますよね。
最低限、ここでご紹介する3つを抑えていれば、融資を受けることは難しくありません。
10年以上創業融資に携わった税理士から聞いた3つのポイントをまとめていきます。
- 数字で明確化!事業計画書の作成
- 自己資金で熱量を表す
- 経営者の素質が見られる経験・実績
上記の3つを抑えて融資の難易度を下げていきましょう!
数字で明確化!事業計画書の作成
提出書類の中で、一番重要といって過言でないのが「事業計画書」です。
事業計画書の記載内容は細かく決まりがある訳ではなく、会社のビジョン・事業内容・収益見込みを分かりやすく伝えるのが目的です。
特に収支の数字や根拠となるデータがあると高く評価されます。
例として、事業計画書の記載内容は以下になります。
- 事業のビジョン
- 事業内容やコンセプト
- 創業者のプロフィール
- 競合や市場規模、ニーズについて
- サービスや商品の仕入れ・取引先
- 販売戦略
- 返済計画
各項目に根拠を持った数字を含めた上で、融資機関に伝えることができれば、審査の通過率は上がります。
いかにして事業内容・根拠を伝え、事業計画が現実的かつ明確であることを説明できるかが大きなポイントとなるのですね。
もっと具体的に事業計画書の書き方について知りたい方は、関連記事も併せてご確認ください。
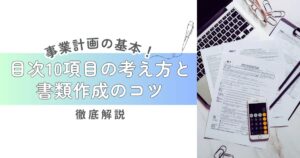
自己資金で熱量を表す
自己資金が多ければ、多いほど審査通過率は上がります。
自己資金は事業への本気度を図る材料として見られるからです。
ただし、目安として最低でも100万円が用意されていれば、ある程度、創業初期の運営を賄える金額は融資されると言われています。
大前提として、自己資金がまったくのゼロといった状態で創業融資を受けようとしても、審査通過はかなり難しいです。
確認してみると、思ったよりも自己資金にできる項目に当てはまることがあるので、ぜひ関連記事から確認してみてくださいね。

経営者の素質が見られる経験・実績
融資機関にとって、お金を貸す人が信用できる人なのか、経営者として事業を発展させていけるのかを判断しなければなりません。
経営者としての経験があればプラスに評価されますし、経営者でなくとも、創業予定の事業に携わった経験があればあるほど、プラスになります。
「創業したい!」とはいうものの、経験や実績がないままであれば、「本当にこの人、創業してやっていけるの?」と貸付側も不安になるわけです。
ですが、あなたが全くの業種未経験であっても、創業予定の業種に役立つスキルの経験などがあれば、うまくアピールすることで一つの経験として見てもらえることがあります。
自分では経験に自信がなかったとしても、税理士など、第三者に話すことで意外と結び付くスキルが見つかることも珍しくないのです。

創業融資の難易度を下げる3つの方法

創業融資は、創業者にとって利用しやすい融資とはいえ、審査通過は決して簡単なものではありません。
過去に実績のない個人への融資は金融機関にとって、失敗率の高さから貸付リスクが高いと考え、慎重に検討されるのです。
そこで今回、融資に申し込む前に行うと格段に審査が通りやすくなる方法を具体的に3つお伝えします。
知っていると、今後の融資審査の不安を解消することができますよ。
ぜひ、前向きに対策しておきましょう。
創業融資の専門家に依頼
一番ハードルを下げる方法は、創業融資の専門家にサポートしてもらうことです。
専門家は、融資機関が見ているポイントを熟知しており、どのようにアピールするべきかも知っています。
その専門家をお供にするだけでも、鬼に金棒です。
さらにメリットがあるので、箇条書きでまとめてみました!
- どの融資機関が最適か判断できる
- 融資機関を効率よく見つけることが可能
- 融資以外の資金調達(補助金・助成金)も相談可能
- 起業後の経営について相談可能
専門家に依頼したいけれども、最終的に融資を受ける事ができずサポート料を支払うのは嫌ですよね。
もしも融資が受けられなかった場合は、料金を支払わない成功報酬制で専門家に依頼することができます。
その創業融資の専門家はこちらから見つけることができます。
しかも10年以上創業融資をサポートしてきた税理士事務所を紹介してくれるので、あなたの融資の大きな支えになること間違いありません。
成功報酬制でやっているので、税理士側も結果を出すために本気で向き合ってくれておすすめです!
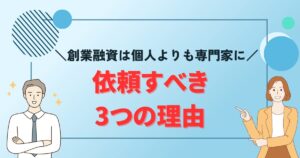
創業融資の希望額を下げる
当然ですが、融資希望額が高いほど審査ハードルも同時に高くなります。
審査に通過はしても、希望額通りの融資が降りなかった、なんてことも珍しくありません。
前項でご紹介したように、税理士など専門家を頼ることで適切な希望額にて融資申込が可能となりますが、「本当にこの金額が必要なのか?」とご自身で振り返ってみることも大切です。
たとえば、店舗の内装を業者にすべて依頼するのではなく、可能なところは自身でやることで外注コストを抑えることができます。
また、事業計画書を見直し、優先順位をつけ、削れる費用をできるだけ見つけていきましょう。
利益を生むために出費を抑えることも経営者としての力量です。
本当にこの金額が必要なのか細かくチェックし、融資希望額を計算し直しましょう!
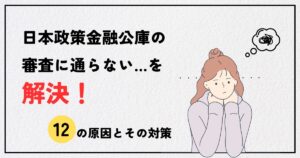
自己資金を3割以上確保
自己資金は多ければ多いほど融資を受けやすくなります。
融資額に対し自己資金が3割以上で、審査に通りやすくなることがわかります。
日本政策金融公庫の2023年度新規開業実態調査では、融資を受けた方の創業資金総額の平均は1,180万円となっており、そのうち融資による調達額が平均768万円、自己資金は平均280万円となっています。
つまり、創業資金総額の3割以上の自己資金が用意されていることが、ベストと言えるのです。
とはいえ自己資金の用意は簡単ではありませんが、預貯金以外にも認められる項目があります。
たとえば、事前に事業準備として使ったお金は自己資金として認められる、などです。
何が自己資金として認められるか、関連記事から前もって把握しておくことができます。

まとめ
創業融資の難易度は、申込者個人の状況や市場を取り巻く環境変化なども影響するため、一定の数値を公表するには難しさがあります。
ですが融資機関が確認する主な3つのポイント「事業計画書」「自己資金」「実績」を理解し、それぞれ対策をすれば審査通過率がアップする=難易度を下げることができるでしょう。
一つの手段として、最前線でサポートしている専門家の意見を聞くのは非常におすすめですよ。



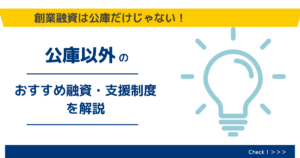
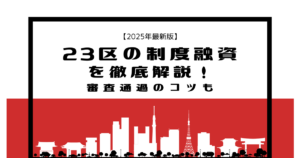
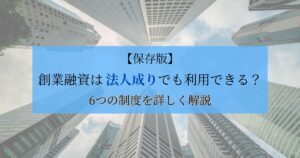

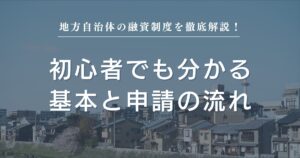
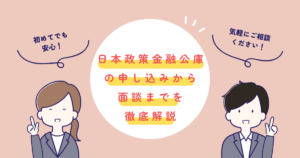



コメント
コメント一覧 (19件)
[…] 返済時の金利は融資決定時の金利が適用され、変動することのない固定金利です。融資審査に通過し確定となった金利が1.90%だった場合、返済開始時期の金利が2.30%であっても適用されるのは1.90%となります。 […]
[…] 直近の財務状況が黒字であれば、審査は通りやすくなると言えます。 仮に赤字であっても、前年の業績が黒字かつ利益剰余金(内部留保)が見込めるのであれば、大きな問題ではないでしょう。 但し、財務状況をどう見るかは、各社の基準や担当者の判断によるところも大きいため、あくまでも要因のひとつとして捉えておくことです。 […]
[…] 1からすべて自身で用意するのももちろん良いですが、不備があって審査が通らなかった、もう少し上手く、効率的に作成できたかもしれない、となると時間ももったいないですよね。 […]
[…] 関連記事:創業融資の難易度は高い?審査通過率90%にする方法 […]
[…] 関連記事:創業融資の難易度は高い?審査通過率90%にする方法 […]
[…] 関連記事:創業融資の難易度は準備次第で変わる!審査が通りやすくなる3つの基準 […]
[…] 関連記事:創業融資の難易度は高い?審査通過率90%にする方法 […]
[…] 関連記事:創業融資の難易度は準備次第で変わる!審査が通りやすくなる3つの基準 […]
[…] 関連記事:創業融資の難易度は準備次第で変わる!審査が通りやすくなる3つの基準 […]
[…] 関連記事:創業融資の難易度は準備次第で変わる!審査が通りやすくなる3つの基準 […]
[…] 資金使途や必要金額の根拠が確認できなかった場合、審査に通らない傾向があります。 […]
[…] 関連記事:創業融資の難易度は準備次第で変わる!審査が通りやすくなる3つの基準 […]
[…] あわせて読みたい 創業融資の難易度は準備次第で変わる!審査が通りやすくなる3つの基準 創業融資の難易度を下げるための秘訣をまとめて紹介!担当者が見ているポイントを知るだけ […]
[…] 関連記事:創業融資の難易度は準備次第で変わる!審査が通りやすくなる3つの基準 […]
[…] あわせて読みたい 創業融資の難易度は準備次第で変わる!審査が通りやすくなる3つの基準 創業融資の難易度を下げるための秘訣をまとめて紹介!担当者が見ているポイントを知るだけ […]
[…] 関連記事:創業融資の難易度は高い?審査通過率90%にする方法 […]
[…] 関連記事:創業融資の難易度は高い?審査通過率90%にする方法 […]
[…] あわせて読みたい 創業融資の難易度は?通過率60%?難易度を下げる3つの方法を紹介 創業融資の難易度を下げるための秘訣をまとめて紹介!担当者が見ているポイントを知るだけでも […]
[…] 結果として、融資審査を通過し600万円の融資を受けることができました。決定打は口約束だった契約を契約書にしてもらうことで独立後も売上があることを証明することができたこと、 […]