創業に必要な“資金調達”の専門サポートを受ける
CEOパートナー
「創業融資の使い道って?どこまで認められる?」
創業融資は、事業との関連性を説明できれば使い道はなんだって大丈夫そうな気がしますが、実は明確に使い道が定められています。
定められた使い道に沿って活用していないと判断されると、調達額の一括返済などを求められ、事業として非常に苦しい状況に陥る可能性があります。
そのため、なんとなくではなく、使い道についてはしっかりと事前に知っておくことが大切です。
ここでは使い道として定められている「運転資金」と「設備資金」のそれぞれの判断基準、さらに3つの注意点や認められる項目について、具体的にご紹介していきます。
また、ご自身の認識で間違いないか、確認してもらえる第三者機関のご紹介も行っていますので、ぜひ気軽に活用してみてください。
知らなかったことで後悔しないためにも、本記事を通してしっかり学んでいきましょう。
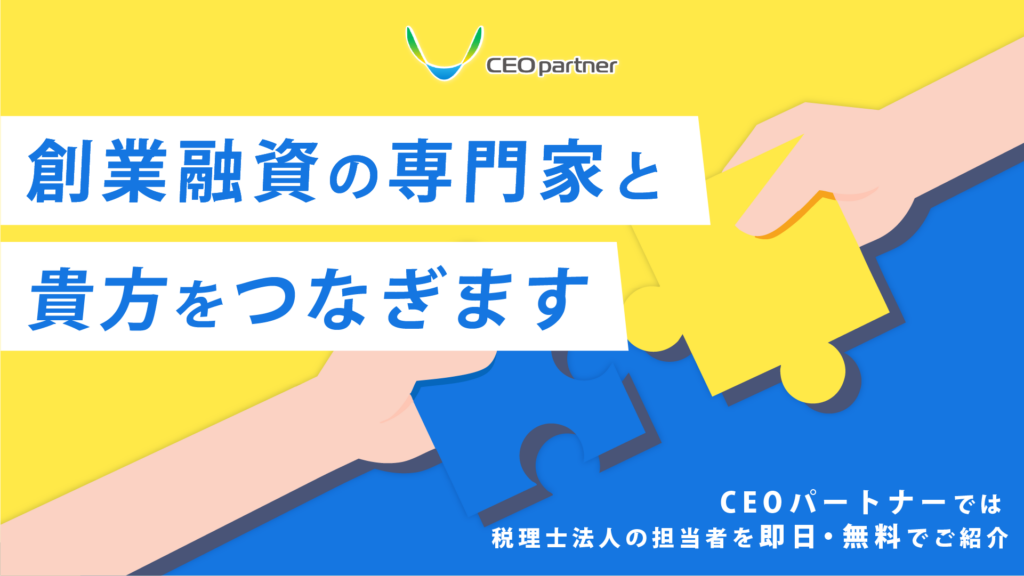
CEOパートナーでは、創業融資をはじめとした資金調達サポートをプロとする税理士法人の担当者を、即日・無料でご紹介しております。
事業計画書の作成代行や面談対策をはじめ、融資だけでなく助成金や補助金の情報提供・お申込みサポートを行っています。
創業後も顧問税理士として頼ることが可能ですので、ぜひお気軽に無料問い合わせをご活用ください。
\相談してから融資を考えてもOK!/
創業融資の使い道における2つの判断基準

創業に必要な“資金調達”の専門サポートを受ける
CEOパートナー
創業融資の使い道をざっくりと述べるなら「事業に関連する必要資金」とすることができますが、厳密には「運転資金」と「設備資金」の2つに区別することができます。
実際に制度の概要に明記されている場合がほとんどで、「運転資金」か「設備資金」のどちらかに振り分けることができるかどうかで、創業融資の使い道として妥当なのかを判断することができます。
2つの基準「運転資金」「設備資金」について、詳しく解説を行いましょう。
日常的に必要な「運転資金」
毎月のように、その都度で発生する資金を「運転資金」と呼び、事業の日常的な運営・成長に必要な資金を指します。
月々継続的な出費が必要となる費用が該当する場合が多いです。例えば、固定費や変動費などですね。
創業融資の申請時には、事前にどれくらいの運転資金を必要とするのか、金融機関まで明確に伝えなければなりません。
例として、以下のような項目が挙げられます。
- 給与など人件費
- チラシ・メルマガなどの広告宣伝費
- テナント契約金
- 仕入れ・事務用品など消耗費
提出書類の一つである「事業計画書」に明記する必要があるだけでなく、面談においても、各項目についてどういった視点から運転資金として判断しているかを確認される可能性が高いです。
必ずご自身で把握し、すべて説明できるようにしておきましょう。
仮に、実際に融資が実行されたのち、申請時には説明のなかった項目への投資や、過剰な投資が確認された場合には、金融機関からの不信感につながってしまいます。
あまりにも運転資金から大きく外れた使い方をしていては、最悪の場合、一括返済を求められることも。
事業計画書の作成時から、運転資金として確保しておく必要のある経費を取捨選択し、根拠をもって計算を行い、明確にしておきましょう。
創業融資の申請時に希望額に含む運転資金は一般的に、3ヶ月~半年分が妥当とされています。
↓ ↓ ↓

一括投資となる「設備資金」
事業に必要な設備のための資金を「設備資金」といいます。
つまり、毎月のように継続的に費用が発生する「運転資金」とは異なり、一度購入すると長く使える設備への投資資金です。
基本的には、創業時に一括で投資すれば、壊れたりなくなったりしない限り、半永久的に使い続ける資産となります。
例として、以下のようなものが該当します。
- 機械装置、車両
- 内装工事
- パソコン機材
- 事業用サイト作成費用
会計上、資産計上が必要になりますので、厳密には30万円を超える投資が該当します。
設備資金は一般的に、運転資金よりも融資限度額を高額に設定されていることが多いですが、使い道がさらに限定されます。
創業融資の申請時に設備資金を希望するとき、投資予定の設備の見積書を提出する必要があり、見積書以外の設備への投資は認められません。
設備資金は高額かつ、限定的であるからこそ、必要性を第三者へうまく伝える必要があると言えます。
\プロの税理士を頼るべき4つの理由をご紹介!/
創業融資の使い道における3つの注意点

創業に必要な“資金調達”の専門サポートを受ける
CEOパートナー
創業融資を受ける際には、資金の使い道を明確に申告しなければなりません。
適切な使い道の提示は、審査時や信頼性の構築において重要だからです。
以下では、やりがちな創業融資の資金使途に関する3つの注意点について、詳しく解説していきます。
- 過剰な高額希望は審査に通らない
- 申告以外の使い道はバレる
- 事業への関連性が不透明
それぞれ、見ていきましょう。

【当サイト限定】融資決定までは完全無料の徹底サポートです
無料で即日、創業融資など資金調達に詳しい税理士法人を紹介してもらえるのは正直、ここだけ。
自力で適切な専門家を探すのは効率的ではありません。
資金調達のタイミングを逃さないで!
過剰な高額希望は審査に通らない
起業後の資金繰りが不安だからといって、とにかく多めに、と希望額を高額に設定して申請する方は珍しくありません。
しかし、創業融資の審査では、資金の使い道が事業の成長や運営に直接関係しているのか、本当にその金額が必要なのかどうかといったところを、冷静に判断されます。
そのため計画にない資金分を含めて、余分に高額な調達を希望してしまうと、審査を通過することが一気に難しくなります。
審査担当者は、提出された書類をもとに事業計画との整合性や、財務計画との一致を確認しているのです。
「なんの項目にどれだけ必要だから、この希望額になっています」と、根拠を示した希望額の設定を行えることが好ましいです。
とはいえ、ご自身ではどうしても、資金繰りの不安などから余分に調達しておきたい気持ちになってしまうのは自然なこと。
場合によっては申請前に専門家を頼ることで、資金繰りに問題ない金額かつ、現実的で審査担当者へ納得感を与えられる金額を適切に案内してもらえます。
\プロの税理士を頼るべき4つの理由をご紹介!/
申告以外の使い道はバレる
創業融資を受ける際には、予め申告した使い道以外の項目へ投資することは避けましょう。
金融機関は融資を行った後も、事業の進捗や財務状況を決算書や固定資産台帳でチェックしています。
もし資金の使い道が申告時と異なると発覚した場合、金融機関からの信頼性が損なわれ、全額一括返済や、返済条件の変更などの問題が生じる可能性があります。
さらには、信用が落ちているために今後の借入が困難になることも。
申告以外の使い道はリスクが高いため、融資の申請時に計画していた使い道に沿って活用しましょう。
事業への関連性が不透明
創業融資の使い道は、事業の成長や運営に密接に関連している必要があります。
使い道が事業戦略と一致していない場合、融資を受けることが難しくなります。
たとえば、飲食店の開業が主な事業内容であるのに、Webデザインの資格を取る際に必要なスクールの受講費を運転資金として調達希望としている場合。
申請者には何か考えがあるのかもしれませんが、一見すると審査担当者からは理解ができず、使い道にそぐわないと判断されてしまいかねません。
そのため、創業融資を申請する際には、使い道と事業目標との関係性を、明確に説明することが重要です。
どのように資金を活用することで、事業の成長や収益増加に寄与するのかを具体的に示すことが求められます。
\プロの税理士を頼るべき4つの理由をご紹介!/
創業融資の使い道として認められるコツ

創業に必要な“資金調達”の専門サポートを受ける
CEOパートナー
創業融資を受けるには、審査担当者まで、資金の使い道を明確に説明することが重要だとわかりました。
とはいえ、具体的にどのような申請のしかたが認められやすいでしょうか。
ここでは、使い道として認められるコツと、伴う注意点について解説していきます。

【当サイト限定】融資決定までは完全無料の徹底サポートです
無料で即日、創業融資など資金調達に詳しい税理士法人を紹介してもらえるのは正直、ここだけ。
自力で適切な専門家を探すのは効率的ではありません。
資金調達のタイミングを逃さないで!
事業を始める・続けるためなら基本OK
基本的には創業融資の使い道は、事業を始めるためや継続するための資金と説明できれば、問題ありません。
設備投資や広告宣伝、人件費などは明確な事業用の資金ですね。
必要経費であるとしっかり説明できる項目に関しては、創業融資の希望として計算することができます。
金融機関の審査担当者は、事業の成長や収益性を見越して、事業に投資しています。
だからこそ、審査では具体的な事業計画を提示し、規模感や成長戦略に基づいた資金の使い道を説明することが大切です。
具体的な項目や金額、経費となる根拠を示し、使い道が明確で合理的であることを証明しましょう。
ものによっては経費として曖昧な投資や、自身では間違いなく経費だと考えていても、客観的に判断すると経費として認められないような項目が発生します。
独断で申請して否決されてしまうよりも、事前に一度専門家へ相談して、専門的な観点から判断してもらいアドバイスを受けることが、審査通過への近道です。
\プロの税理士を頼るべき4つの理由をご紹介!/
運転資金は3ヶ月~半年分が妥当
事業が安定するまでに運転資金として調達しておきたい金額は、通常は事業の3ヶ月~半年分に収まることが多いです。
業種や規模にもよりますが、3ヶ月~半年の間で売上がある程度安定し、利益を運転資金へと充てることができるようになるからです。
運転資金の調達を希望するときは、市場分析を通して見えてきた事業安定までに要する期間と、それに伴って必要とされる投資の金額を、明確に示すことがポイントです。
場合によっては半年分以上を希望したいこともあるかもしれませんが、希望が高額になればなるほど、それだけ根拠のしっかりとした計画を提示する必要があります。
運転資金の算出方法については、次の記事を参考にしてみてください。

自宅兼事務所は総床面積で区別
創業時に自宅を事務所として活用する場合、審査では住宅ローンや住宅購入費と、事業運営費を区別する必要があります。
創業融資は事業目的のために利用される床面積に対してのみ、調達が認められています。
自宅兼事務所の場合、事務所として利用される総床面積を算出します。
詳細な床面積の計算や、事業と住居の明確な分離を示すことで、審査担当者の理解を得ることが重要です。
専用の事業スペースや入口の設置などの工夫をすることで、さらに説得力が高まります。
創業融資の使い道や計画は専門家に相談しよう

創業に必要な“資金調達”の専門サポートを受ける
CEOパートナー
創業融資は誰をも頼らず、一人で申請したときの成功率は、なんとたったの20%と言われています。
調達した資金の使い道はもちろん、事業内容やその計画における説明がしっかりと行えないようだと、「融資するに値しない」と判断され、審査に落ちてしまうのです。
一発で創業融資を受けて、希望の使い道に沿った投資を行うなら、必ず専門家を頼るようにしましょう。
最近では、創業融資に精通した税理士法人など、士業の専門家が創業融資サポートを専門としたサービスを行っていることがあります。
専門家を頼ることで、専門家自身が培ってきた知見や、金融機関との太いパイプを活かして、サポート希望者にとって非常に有利な審査対策を進めることができるのです。
創業融資の調達時だけでなく、税理士法人を頼る場合であれば、税務の相談や経営アドバイスを受けることもでき、今後の事業を成功させるために必要な心強い味方となります。

【当サイト限定】融資決定までは完全無料の徹底サポートです
無料で即日、創業融資など資金調達に詳しい税理士法人を紹介してもらえるのは正直、ここだけ。
自力で適切な専門家を探すのは効率的ではありません。
資金調達のタイミングを逃さないで!
説得力ある事業計画書が完成する
創業融資を受けるためには、説得力のある「事業計画書」や「収支計画書」を作成する必要があります。
しかし、こうした書類の作成には、財務知識やビジネスプランニングといった高度のスキルが必要です。
初めて創業する方にとって不安なスキルであることは言うまでもなく、かなりの時間と労力をかけることになります。
ところが専門家に相談することで、的確なデータ分析や財務予測、市場調査などを行い、信頼性の高い計画書を作成することができます。
また、専門家は金融機関の期待に応えるための適切な情報の盛り込み方や、適切な表現方法をアドバイスしてくれます。
適切な使い道で成功率を上げる
創業融資の審査では、使い道の明確性と事業への関連性が重視されます。
専門家はさまざまな業界・業種へのサポート経験を持っており、市場に応じた適切な使い道の提案が可能です。
たとえば、「この業種には広告宣伝費をいくらくらいかけて、このくらいの期間で利益を上げられるだろう」などと一般的な傾向を知っています。
そのため、初心者の独断での申請とならず、市場に適した計画と使い道の提示で、審査担当者にとってより納得感の高い申請ができるのです。
融資以外の調達手段にも対応できる
創業時の資金調達手段は、何も創業融資に限られたものではありません。
補助金や助成金などの給付金や、クラウドファンディング、投資家からの出資など、手段はさまざまに存在します。
クラウドファンディングや投資家からの出資は、国の機関を相手にしたものではないため専門家のサポート範囲外である可能性が高いですが、補助金や助成金については、専門家を頼ることで創業融資同様、有利に審査対策を進めることができます。
給付金は創業融資と併用すると、より効果的に資金繰りに寄与すると言われているため、積極的に活用を検討するとよいでしょう。
創業時に活用できる給付金については、次の記事をぜひ参考にしてみてください。
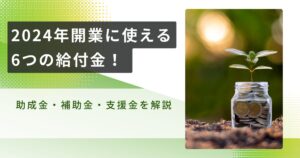
まとめ

創業融資の審査に通る使い道は「事業に必要かどうか」が基準です。
日常的に必要となる「運転資金」と、一括投資が基本の「設備資金」のどちらかに該当するかをチェックしてみましょう。
資金の使い道を明確にすることで、事業との関連性を示すことができ、審査側の信頼感を高めることができます。
もし、これは創業融資の使い道にしてもいいのか?と判断に迷った場合は、創業融資の専門家に相談することをおすすめします。
専門家にサポートを依頼することによって、適切な使い道から逸れることなく申請ができ、審査の成功率を上げることができるからです。
事前に、事業に必要な項目を洗い出し、専門家とともに確認するようにしましょう。
専門家といっても、どこにお願いすればいいの?と迷われる方は、ぜひCEOパートナーを頼ってみてください。
無料・即日で簡単に、創業融資に精通した税理士法人とマッチングが叶います。
創業融資が実行されるまでは完全無料の「成功報酬型」なので、コスト面での心配がなく安心して相談することができますよ。

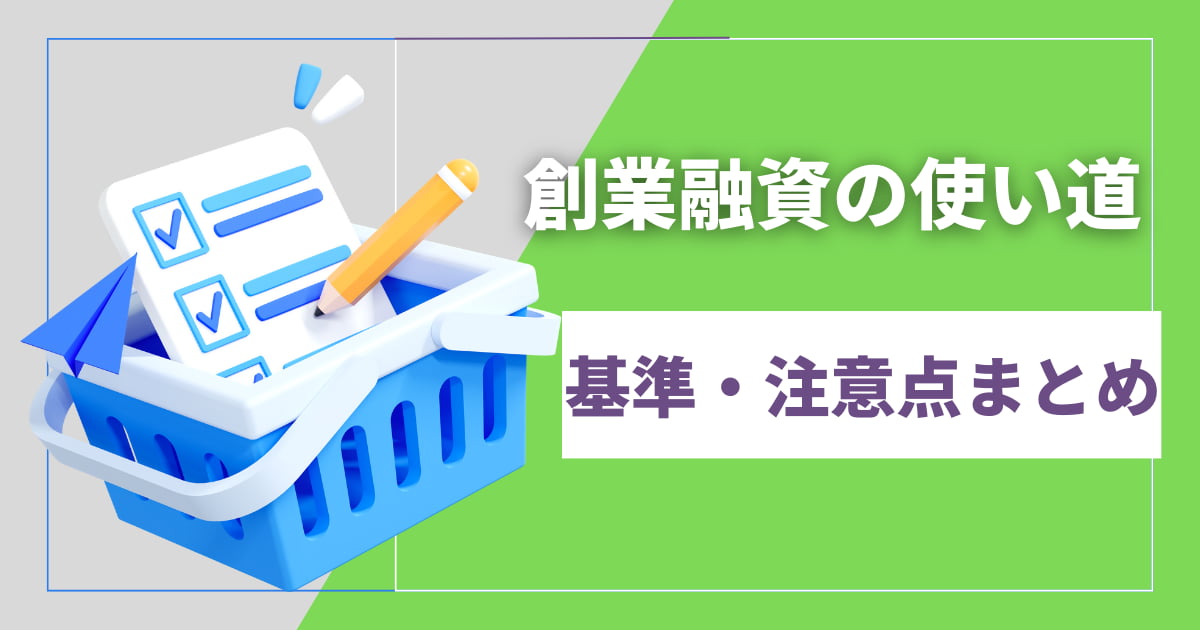
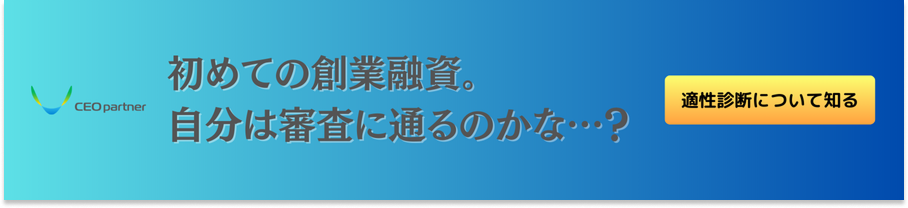

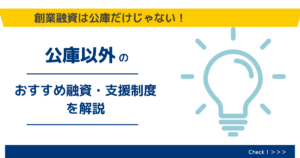
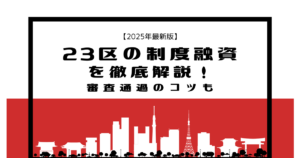
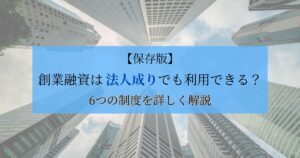

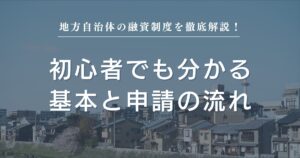
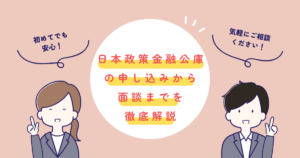



コメント
コメント一覧 (9件)
[…] 残りの2,400万円は設備資金としての融資となり、運転資金への流用は認められていません。 […]
[…] 融資額は3500万円以内であり、融資期間は、運転資金10年以内 設備資金10年以内(据置12か月以内を含む)となります。 […]
[…] そこで、見積もりを出して、資金用途を明確にすることが大切です。 […]
[…] 資金の使い道は、事業計画書に明確に記載する必要があるのです。 […]
[…] 関連記事:創業融資で重要な使い道!どこまでOK?2つの基準を解説 […]
[…] 関連記事:創業融資で重要な使い道!どこまでOK?2つの基準を解説 […]
[…] こちらの融資限度額は3000万円となっており、使い道は新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金と定められています。 […]
[…] 事業に必要な資金でもある運転資金は3か月分で計算されることが多く、その理由として商品の仕入れから売上の回収までの期間が3~4か月間と言われているからです。 […]
[…] また、運転資金の見積もりとして、仕入原価や人件費、広告宣伝費、水道光熱費等を3カ月分を出すようにしましょう。 […]