「創業融資っていろんな種類があるけど、結局どこを使うのが賢いんだろう?」
創業融資がどんなものかという仕組みを把握されている方が、次に悩むのが“どの創業融資を利用するか”ではないでしょうか。
創業融資を扱っている機関は複数ありますし、同じ機関の中でも複数の制度や種類が存在していることも。
複数ある中でどの創業融資を利用するのか、一つひとつ比較した上で自身の判断だけで決めるのは難易度の高いことだと言えます。
本記事では創業融資は結局何がいいのか、どれがおすすめなのか、明確に分かるようにご紹介していきます!
また創業融資を利用するときのポイントや、ぜひ頼りたいおすすめのサービスをご案内。
創業融資を受ける上での迷いがすべて解消すると言っても過言ではない内容となっておりますので、最後までしっかり目を通してみてくださいね。
創業融資のおすすめは新規開業資金

創業融資は調べれば調べるほど多くの種類が出てくるため、結局どれを利用すればいいのか分からなくなりますよね。
創業融資に関連する記事をいくつも作成しているからこそ、個人的に一番おすすめだと胸を張って言えるのは“新規開業資金”です。
ここでは新規開業資金の何がおすすめなのか、詳しくご説明していきますので一緒に見ていきましょう。
創業融資を決めかねている方は必見です。
【一覧】ここがスゴイ!他融資制度との比較
新規開業資金の何がいいのか、比較対象があったほうが分かりやすいですよね。
まずは新規開業資金とその他よく使われる創業融資の特徴を一覧で掴みましょう。
| 対象者の幅広さ | 金利のお得さ | 融資限度額の高さ | 担保・保証人負担の低さ | 返済期間の長さ | 据置期間の長さ | スピードの速さ | 審査の通りやすさ | |
| 公庫の新規開業資金 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 地方自治体の制度融資 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | 〇 |
| 信金の独自融資 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
一覧から読み取れるように、〇部分が多く利用しやすいのは新規開業資金です。
今回取り上げた3つの創業融資、新規開業資金・制度融資・信用金庫の独自融資はどれも主要な融資制度ですので優劣付けづらいですが、△の制度が〇の制度よりは劣ると見てください。
新規開業資金に関しては金利は地方自治体の制度融資に劣りますが、その他は非常に利用者想いな、利用しやすい仕組みになっていると言えます。
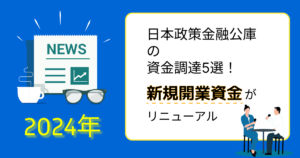
初めての利用でも原則“無担保・無保証”
新規開業資金の一番のおすすめポイントは、なんと言っても「原則」無担保・無保証である点です。
融資を受けようとすると担保や保証が必要になるのが一般的ですが、新規開業資金を利用すれば担保や保証を要求されることがないのが特徴です。
金融機関側が少しでもリスクを減らすために設定されるのが担保と保証。創業経験など、実績のない個人が高額融資を受けようとすると金融機関からは難色を示されるのが現実ですので、そこを「無担保・無保証でOKですよ」と構える日本政策金融公庫は利用者にとって非常にありがたい存在だと言えます。
※「原則」無担保・無保証人とされるのはこれから創業予定の方~税務2期終えていない方に限ります。詳しくはこちら

限度額7,200万円とどこよりも高額
新規開業資金の限度額は7,200万円となっており、創業融資として一個人に渡せる金額としてはどこよりも高額と言って過言ではありません。
実際に、地方自治体の制度融資だともちろん自治体にもよりますが2,000万円ほど、信用金庫の独自融資だと1,500万円前後と新規開業資金には及びません。
自治体や地域の信用金庫の制限に左右されず、間違いなく高額融資を可能としたいのであれば新規開業資金を検討するが吉でしょう。

どの金融機関よりも審査に通りやすい
審査の通りやすさはピカイチと言えます。
日本政策金融公庫は創業前の個人や中小零細企業を金銭面にて積極的に支援することを目的とし活動していますので、そもそもの姿勢が「融資しましょう」という姿勢でいます。
その上で申込者の信用情報やこれまでの実績、事業の成功可能性などから総合的に判断し、審査結果を決めます。
民間金融機関にとっては「リスクしかないので厳しい」という判断をされがちな創業初心者でも、公庫の新規開業資金なら審査通過は十分に期待できるのです。

創業融資のおすすめ番外編|公庫以外ならココだ

創業融資ならズバリ、新規開業資金がおすすめな理由をご紹介してきましたが、ここでは新規開業資金以外のおすすめをご紹介していきます!
新規開業資金には勝りませんが、それでも負けない部分は十分にあります。
一つの融資制度だけでは不安な方や、新規開業資金の審査に通過できなかった場合に備えて併せてチェックしておくことをおすすめしますよ。
公庫より金利が低い!?自治体の制度融資
地方自治体の制度融資は一番の魅力として、金利が低いことが挙げられます。
厳密に言うと自治体が利子補給といい、金利の一部を負担してくれることから、利用者本人の負担率が低くなるという仕組みです。
例えば東京都渋谷区の場合、年1.7%のところ、渋谷区が1.6%負担してくれるために本人の負担率はなんと0.1%に。
これは新規開業資金では実現できない金利の低さです。
難点としては、制度融資は利用者と金融機関の直接のやり取りではなく、間に自治体を挟むため融資実行まで3か月ほど時間がかかるほか、担保や保証は条件をクリアしなければ発生するケースがほとんどなところ。
しかしどこよりも低金利である魅力や、自治体特有のサポートが受けられる点から利用する方は多くいらっしゃいます。
スピードを求めず、新規開業資金ほどの高額な限度額がなくても事足りる方、創業したい自治体の制度融資の内容が充実しているなら候補に入れる価値は十分にある創業融資です。
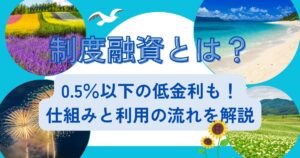
公庫に負けない親身な対応、信用金庫
信用金庫は民間金融機関の中で唯一、創業初心者への融資に積極的な機関です。
大手銀行や都市銀行など、比較的規模の大きい銀行は大企業や権力を持った起業家にしか基本的に高額融資は行いません。
理由は、返済能力があると判断できない企業や個人に高額な貸付を行うことは、一度渡した金額を回収できないリスクが高く、銀行からすればメリットがないからです。
一方で信用金庫は利益よりも、組織の存在価値に重きを置いた活動を行っています。
信用金庫は地域の経済活性化を支援すべく存在している組織であるため、他の民間金融機関と比べ顧客との距離が非常に近く、親身な対応を行っているのが特徴です。
そのため公庫に負けない親身なサポートが受けられるほか、地元のあらゆる中小零細企業や個人に密着してきた実績から、地元ならではのさまざまな情報を提供してもらえるメリットがあります。
融資限度額はこれまで記事を執筆してきた経験上、平均して1,500万円前後と公庫ほど高額ではありませんが、地元に根付いた事業を行いたいと考えている方にはぴったりの創業融資と言えます。

創業融資を利用するときのポイント

創業融資の利用には知っておきたいポイントが3つあります。
スムーズに創業融資の申込から審査通過、融資実行まで運ぶためにもぜひ事前にチェックしておきましょう。
また、個人的には創業融資だけでなく、助成金や補助金の情報も仕入れておくべきだと考えます。
資金調達の方法は融資だけではないのです。
ご紹介していきますので、順番に見ていきましょう。
書類準備は創業2~3か月前から始める
新規開業資金の申込から融資実行までは1か月ほどで完了する場合がほとんどですが、余裕を持って実際に創業する時期の2~3か月前には準備を始めるようにしましょう。
申込には書類の準備が必要であり、決して1種類で完結する量ではないため、そのためにもある程度余裕を持った時間が必要です。
また自治体の制度融資や信用金庫の独自融資の場合はさらに時間がかかるため、4~5か月前から申込準備に向けて動き出すのがよいでしょう。
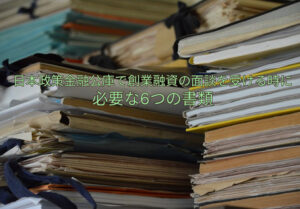
自己資金・信用情報・計画は整えておく
創業融資の申込はなんとなくで行っていいものではなく、気を付けるべき3つのポイントが存在します。
- 自己資金は創業資金総額の3分の1を準備しておくと安心
- 信用情報に傷がついていると審査に通りにくくなる
- 事業計画は実現性かつ説得力を持たせて成功性を強調する
以上3つは特に力を入れて準備したい部分であるとともに、審査時に一番見られる部分です。
自己資金や事業計画はしっかりと自身で創業に向けて準備していることのアピールとなり、クレジットカードの支払いや公共料金、携帯代などといった毎月発生している支払い義務を問題なく果たしていることは、返済能力の判断材料としてかなり重要視されるポイントです。
審査に通過できなかった人は3つのポイントをクリアできていない場合がほとんど。
信用情報に傷をつけないこと、自己資金を準備することは普段の生活から意識する必要がありますので、今一度ご自身の状況を振り返ってみて不足しているなら早急に準備を進めましょう。

併せて助成金・補助金も見ておく
資金調達といえば創業融資、と創業融資だけにしか目を付けていない方は少なくないのでは。
創業融資には返済義務が生じますが、助成金や補助金の利用が認められると返済の必要なく、まとまった資金調達が叶います。
助成金や補助金は国が用意しているもののほか、地方自治体が用意しているもの、更には大企業が用意しているものもあります。
- ものづくり補助金
- 小規模事業者持続化補助金
- キャリアアップ助成金
- 創業助成事業(東京都)
- 大阪起業家グローイングアップ事業(大阪府)
上記が代表的で、よく利用される助成金・補助金です。
もちろん他にも種類は豊富にあり、地方自治体は独自の特徴を持ったものをいくつも展開しています。
中小機構のサイトJ-Net21の支援情報ヘッドラインでは、自身が助成金や補助金を受けたい地域に絞り、情報を検索することができます。
時期により募集している助成金や補助金の種類や数は変動しますので、ぜひ一度ご自身でチェックしてみてくださいね。
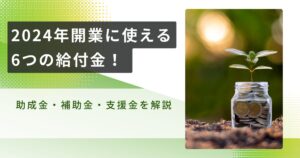
創業融資のおすすめは一人で申込まないこと
創業融資の利用を決めたとき、申込は必ず通る道ですよね。
申込は一人でやるのが当たり前だと思っていませんか?
実は創業融資の審査通過を成功させるためのおすすめは、一人で申込まないこと。
その理由と、頼るべきサービスをご紹介していきますので、融資審査通過のためにも最後まで目を通してみてください。
一人で申込むと審査通過率が下がる…?
審査時に見られる判断基準としては自己資金やこれまでの実績、計画性や事業の成功可能性などが代表的で、ほとんどは書類や面談を通して証拠などを提示し、アピールすることとなります。
書類や面談の準備が疎かになっていたり、説得力が足りずアピール力に欠けていたりすると、「この事業が成功する未来が見えない」と判断され、融資を断られてしまいます。
創業初心者が一人で適切な準備を行ない、日本政策金融公庫など融資担当者に認められるようアピールするのはそう簡単なことではありませんね。
せっかくアピールできる部分があっても、一人で主観的に進めるだけではうまくアピールができず審査通過率が下がってしまうと言えるのです。

一人で申込むと書類作成がめんどくさい
正直、書類作成はめんどくさいですよね。
創業融資に申込むには6~10種類ほどの書類を準備する必要があります。
一人で申込もうとすると書類作成もすべて自身で負担することとなりますし、初めて作成する書類と一人でにらめっこするのはかなり大変な作業であると言えます。
仕事しながら創業を目指しているなど、創業準備だけに十分な時間を割ける方は少ないでしょう。
めんどくさいだけでなく、時間が掛かってしまい、更には内容作成に悩んで途中で投げ出してしまうリスクも考えられます。
一人で書類作成するのは非効率と言えるのですね。

一人で申込むと面接対策で苦労するかも
新規開業資金に申込みを行うと、書類審査だけなく必ず面接審査が実施されます。
面接は融資担当者とコミュニケーションを図ることとなりますので、当然ながら一人で対策を行うのは不可能に近いです。
実践練習を通して第三者にアドバイスをもらいながら、内容を充実させていく必要があります。
自分一人の判断では「この説明で理解してもらえる」と感じていても、担当者からすればツッコミどころ満載、というのはよくある話です。
Face to Faceで行われる審査であるからこそ、ぶっつけ本番ではなく事前に第三者の意見を取り入れながら対策を行う必要があるのです。
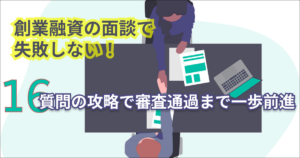
全部解決するのが【CEOパートナー】
審査通過率が下がる、書類作成がめんどくさい、面接対策への苦労…。
一人での申込がおすすめできない理由をお分かりいただけたでしょうか。
こうした問題がすべて解決されるのが、CEOパートナーの存在です。
CEOパートナーとは創業に詳しい税理士とマッチングできるサービスで、問合せをしたその日中に窓口より案内が入り、税理士を紹介してもらえます。
全国に約8万人いる税理士の中から創業に詳しく、自身の悩みを解決してくれる税理士を見つけ出すのはかなりの苦労を伴います。
効率よく税理士と出会える上、創業融資の書類準備から申込、面接対策までを効率よく運べるのはCEOパートナーを利用する方にしか得られない特権です。
しかも嬉しいのが、融資が実行されるまでは何度相談しても無料な点です。
完全無料で利用でき、万が一融資を決められなければ請求されることは一切ありません。
融資が決まった際に支払う費用も、融資額の3~5%と出資法に基づいた金額設定なので安心です。
気軽に強力なパートナーを得て希望額に近い資金を無事に調達したい方はぜひチェックすべきサービスですよ。
\創業融資のプロ・税理士法人を即日紹介/
※フォーム送信後5~10分でお電話を差し上げます
まとめ
創業融資のおすすめはズバリ新規開業資金なので、迷ったらまずは新規開業資金を検討してみるのがよいです。
審査の通りやすさや7,200万円という高額の融資限度額、原則無担保・無保証で借入ができるなど、創業初心者が非常に利用しやすい条件が揃っていますので申込して間違いはありません。
もちろん利用しやすいとは言っても、適当に申込をすれば誰でも審査に通過するわけではありませんので、4章でご紹介したCEOパートナーをうまく頼って効率よく審査通過まで運びましょう。
資金調達が成功しなければ事業は始まりません。創業融資をうまく活用して好スタートを切りましょう!




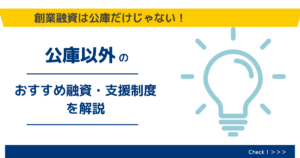
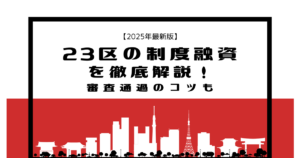
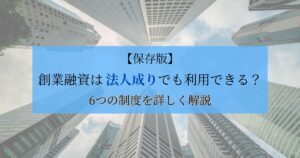

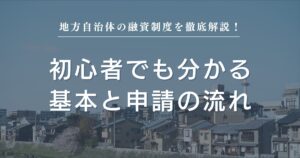
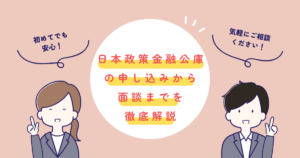



コメント
コメント一覧 (9件)
[…] 地方で起業するにあたっては、ある程度実績を作ってから移住し、起業する方が成功確率は上がると思います。 まずは小さく起業し、それなりの実績と手ごたえが掴めたのであれば、そこから規模を拡大していくのも一考です。 新創業融資は「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方」が対象となります。 該当するのであれば、活用しない手はないでしょう。 関連記事:創業融資のおすすめはこの5つ!自分にぴったりの創業融資がわかる […]
[…] 参考記事:創業融資のおすすめはこの5つ!自分にぴったりの創業融資がわかる […]
[…] しかし、融資を受ける際には法人口座の開設を求める金融機関もあります。 […]
[…] 関連記事:創業融資のおすすめはこの5つ!自分にぴったりの創業融資がわ… […]
[…] 資金を調達するために融資を受けたい人のなかには、融資を受ける金融機関の候補として信用金庫を検討している人もいるでしょう。 […]
[…] […]
[…] 会社設立と聞くと真っ先に「融資」が浮かぶのではないでしょうか。 […]
[…] 資金を調達するために融資を受けたい人のなかには、融資を受ける金融機関の候補として信用金庫を検討している人もいるでしょう。 […]
[…] あわせて読みたい 創業融資のおすすめはズバリ?利用する際のポイント3つも徹底解説! 創業融資は結局何がいいか、どれがおすすめかをズバリご紹介。創業融資利用のポイント、頼り […]