開業を検討している方にとって、開業費への知識は身に付けておきたい部分でしょう。
開業費は経費の一部となり、なんでも計上していいわけではなく開業費として認められるもの・認められないものがあります。
ここでは開業費の基本的な情報を解説するとともに、用意しておきたい開業費の目安や仕訳のやり方、節税につながる3つのポイントをご紹介していきます。
正しい知識を身に付けて、後悔なく開業準備を進めていきましょう!

開業費とは?

まずは、開業費の基本的な解説です。
開業費とは、会社を設立した後に営業開始までに支出された開業に必要な費用のことをいいます。
具体的に該当する費用は、開業準備期間中に発生した賃借料や広告費、通信費、交通費などです。
事業を開始する際には、必要となる費用なのであらかじめ準備しておきましょう。
開業費と創業費の違い
開業費とよく似た言葉に創業費があります。
いずれも、事業を始める前に必要な費用という意味では同じですが明確な違いがあるのでここで覚えておきましょう。
創業費は法人登記するまでにかかった費用のことです。
つまり、創業費は法人にしか使わない言葉ということになります。
開業費は個人事業主でも法人でも使うことが可能です。
勘定科目につける際に誤った計上をしないようにお気を付けください。

繰延資産として償却できる
開業費は経費ではなく、繰延資産として償却できるということも覚えておきましょう。
繰延資産とは、過去に支出した費用のうち、効果が来期以降にも影響されるもののことをいいます。
開業費は開業前の準備費用なので、開業年度だけではなく来期以降も影響するという考えから繰延資産とされています。
繰延資産は一旦資産の科目で処理し、その後毎年少しずつ費用として計上が可能です。
こうすることで、節税効果ももたらすことができるのです。

開業費として認められるもの

続いては、開業費として認められるものと認められないものについて解説します。
今回はその一例としていくつか挙げますが、それぞれ混同してしまいがちです。
認められるか迷った場合は、税理士などに相談するといいでしょう。
開業費として認められる項目
まずは、開業費として認められる費用について解説します。
<個人の場合に認められる費用>
- 打ち合わせのための費用
- 開業に関する調査のための旅費やガソリン代
- 広告宣伝費
- パソコンの購入費用や通信費
<法人の場合に認められる費用>
- 広告宣伝費
- 市場調査費
- 名刺や印鑑の作成費用
- 研修のための費用
個人と法人では認められる費用に違いがあるのでご注意ください。
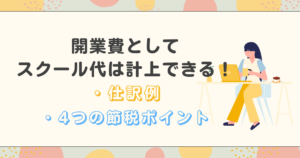
開業費として認められない項目
一方、開業費として認められない費用はどんなものがあるのでしょうか。
<個人の場合に認められない費用>
- 10万円以上かかったもの
- 仕入れ代金
- 敷金、礼金
<法人の場合に認められない費用>
- 10万円以上かかったもの
- 仕入れ代金
- 敷金、礼金
- 事務所の家賃や水道光熱費
10万円を超える備品は固定資産に該当します。
開業費としては認められないのであらかじめ知っておいてください。

開業費はいくら必要?
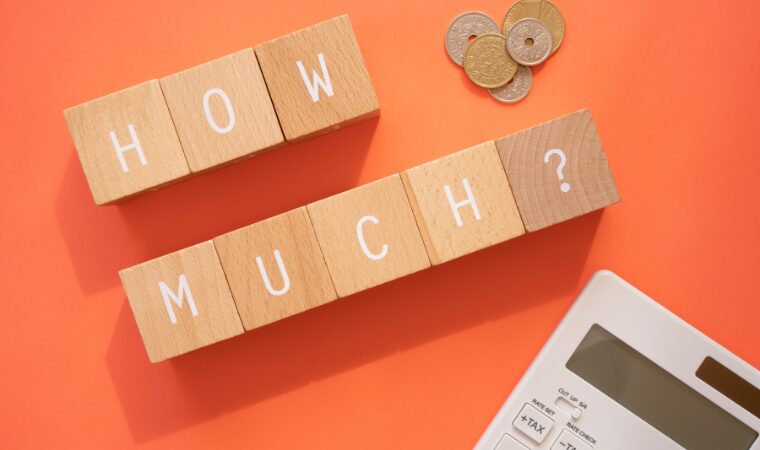
事業を始める際に必要な開業費。
実際にどの程度用意しておけば良いか分からないという方も多いでしょう。
必要な開業費についても解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
最低100万円は必要
業種によっても異なりますが、一般的には最低でも100万円程度は必要といわれています。
とはいえ、これはあくまでも一般的な場合ですので自宅をオフィスとして使用する方やプライベートの資産を事業に活用するという方はこれ以下の金額で開業費が済んでしまう場合もあるでしょう。
開業費を節約したいという方は、自宅にあるものを事業で利用したり必要機材を中古で購入したりというような工夫が必要になってきます。
事業計画をもとにシミュレーション
開業費が100万円必要というのは最低でもなので、場合によっては1,000万円近くになることも珍しくはありません。
事前の計画なしに、いざ用意してみたら開業費が足りなくなってしまい事業がとん挫してしまうということも考えられます。
そのためにも、まずは開業費がどの程度必要なのか事前にシミュレーションしておくことが大切です。
開業費の調達方法は大きく3つ
その開業費を実際に調達するにはどんな方法があるのでしょうか。
主に次の3つの方法が考えられます。
まずは自己資金を充てることです。
事業を始めるという計画があれば、事前に貯金をしたり知人から借りたりすることも可能でしょう。
続いては、創業融資を受けるという手段も考えられます。
そのためには、事業の継続性や確実性を金融機関にアピールしなければなりません。
融資を受ける際には、綿密な事業計画や創業計画書が必要になるのできちんと準備をしておきましょう。
助成金や補助金を活用するというのも有力な方法です。
創業融資はお金を返済する必要がある一方で、助成金や補助金であれば基本的に受け取ったら返す必要はありません。
ただし、そのためにはさまざまな申請や書類作成をしなければならないのである程度の労力と時間を費やすことは念頭に置いておいてください。
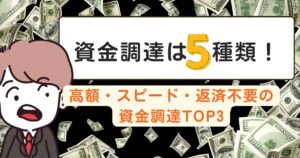
開業費の仕訳のやり方

続いて、開業費の仕訳方法について解説します。
お伝えしてきた通り、開業費に該当するものとしないもので仕訳をして計上する必要があるので、その方法についてもチェックしてきましょう。
開業費の計上
一般的には、明細ごとに入力することが望ましいものの、詳細な内訳を別途でまとめて集めている場合などはまとめても問題ないとされています。
ただしその場合は、明細が分かるものや領収書等を保管しておく必要があるのでご注意ください。
また、開業費は開業した年に全額経費計上できる一方でその年以降に経費計上することも可能です。
開業したばかりで利益の少ない1年目ではなく、利益が出てきた頃に計上すると節税効果もあります。

開業費の償却
開業費は開業前に発生した費用なので、その間の発生した費用も償却することが可能です。
基本的には何年前の費用でも開業費として取り扱うことができますが、あまりにも昔の費用は税務署から調査の対象になる可能性があります。
さかのぼることができるのは、半年から1年前程度です。
一方、先述した通り繰延資産としても償却できるので、開業費を活用して賢く節税しましょう。
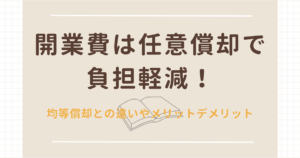
迷ったらCEOパートナーへ相談
とはいえ、開業費について一人で仕訳を行うのは非常に難しいです。
事業によっては、複雑な仕訳が必要なために本業に支障が出てしまう可能性もあります。
そんな時は、CEOパートナーにご連絡ください。
お悩みにピッタリな税理士を無料で紹介しています。
開業費についてはもちろん、創業・独立について不安なことがあればいつでも相談可能です。
\プロの税理士を頼るべき4つの理由をご紹介!/

開業費を節税する3つのポイント

仕訳は難しいものの、開業費を上手く計上することで節税にもつながります。
そのポイントを3つまとめましたので、こちらも参考にしてみてください。
領収書やレシートの保管を忘れない
まずは、基本的なことですが開業費として発生した領収書やレシートはきちんと保管しておくようにしましょう。
いくら開業費として計上したくても、証拠が残っていなければ認められない可能性は非常に高いです。
ただし、
- 慶弔費用
- 電車賃など金額が少ない旅費交通費
- 割り勘で支払った食事代
といったレシートや領収書を発行できない費用の場合は、出金伝票を残しておくようにしましょう。
いずれにしても、場所を決めるなどをしてきちんと保管しておくことが大切です。
仕訳帳・減価償却資産台帳へ正確に記帳する
開業費は、合計金額が10万円を超えると仕訳帳と減価償却資産台への記帳が重要になってきます。
そうしなければ、開業費を繰り越し資産として計上できず節税もできなくなってしまうからです。
記帳するポイントとしては、
- 開業費は資産科目に記帳する
- 開業償却費は経費科目に記帳する
です。
いずれも正しく記帳するようにしましょう。
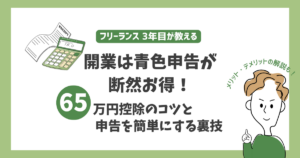
開業前の発生費用もカウントする
帳簿を付ける前の期間であっても、開業費として償却できるため開業前に発生した費用も計上しておいてください。
こちらも、きちんと領収書やレシートを残しておくことが大切です。
開業費として扱う予定の費用は、誰に対しても説明ができるようにしておきましょう。
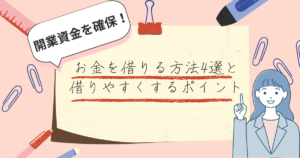
まとめ
開業費は開業する際に必要不可欠な費用でありながら、上手に活用すれば節税効果も発揮します。
ただ、そのために行わなくてはならない仕訳方法は非常にややこしい作業です。
正確に行うだけでも骨が折れるので、プロの税理士に依頼することをおすすめします。
CEOパートナーでは、適切な税理士をご相談から24時間以内に紹介しています。
開業を目指す多くの人が利用しているので、この機会にいかがでしょうか。
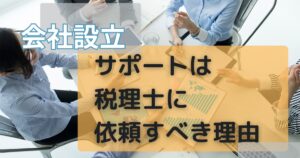

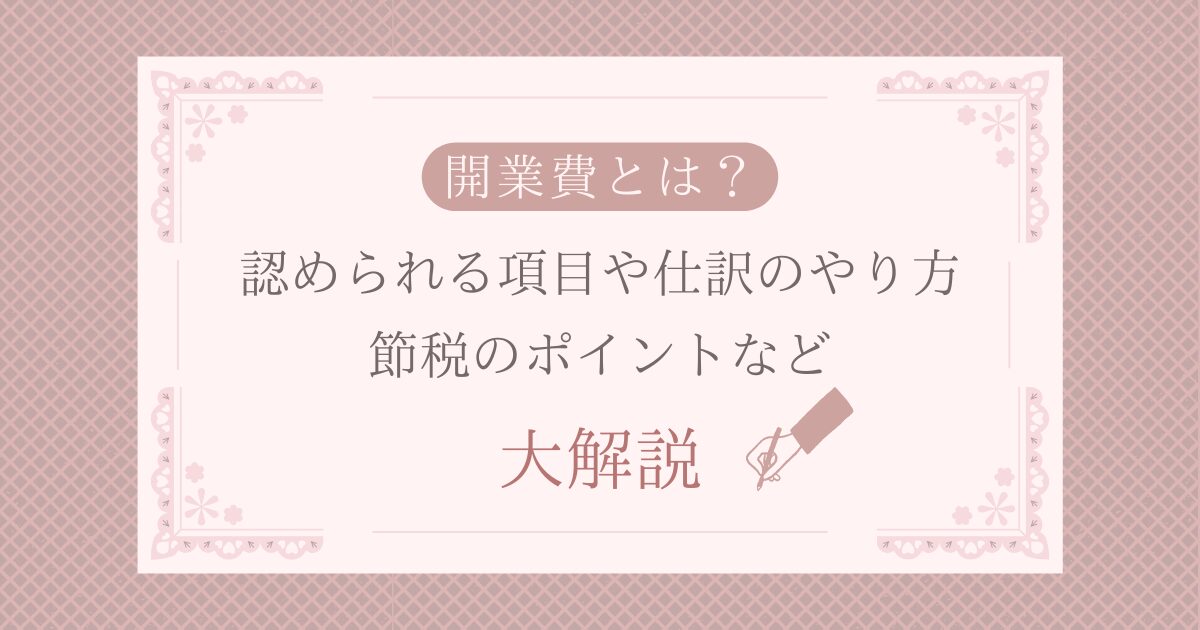
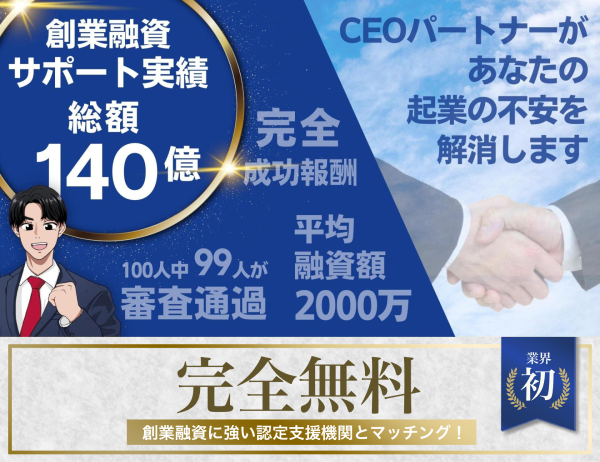







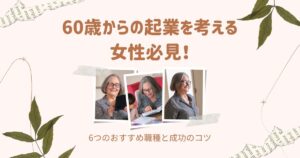

コメント
コメント一覧 (4件)
[…] あわせて読みたい 開業費とは?認められる項目や仕訳のやり方、節税のポイントなど大解説 開業費は賢く調達、経費計上することで節税につながります。開業費の基本知識と同時に、 […]
[…] あわせて読みたい 開業費とは?認められる項目や仕訳のやり方、節税のポイントなど大解説 開業費は賢く調達、経費計上することで節税につながります。開業費の基本知識と同時に、 […]
[…] あわせて読みたい 開業費とは?認められる項目や仕訳のやり方、節税のポイントなど大解説 開業費は賢く調達、経費計上することで節税につながります。開業費の基本知識と同時に、 […]
[…] あわせて読みたい 開業費とは?認められる項目や仕訳のやり方、節税のポイントなど大解説 開業費は賢く調達、経費計上することで節税につながります。開業費の基本知識と同時に、 […]